野鳥観察日記TOPへ
2009 1 1 室林道ラインセンサス
氏神さまへの初詣、お寺への年始回り、二歳先輩の方と昔話に花を咲かせながら、快晴の空の下をのんびり歩いた。家に戻り、さて、今年の初バードウォッチングは何処にしようか。HPの賑わしにオシドリの写真でも、ところが、オシドリのいる新堤池はまともに北風が吹き抜け、ウインドブレーカーを着込んでいても寒いのなんの。オシドリも木陰に隠れて出てこない。退散と相成った。気を取り直して室林道へ。常とは反対のコースから歩き出した。カワラヒワが明るい声で鳴いていた。オスとメスの2羽で、つがいなのかもしれない。人間の世界と同じくメスの方が上にいた。室林道から西に伸びるコース(牛沢下谷下線)を歩くことにした。室林道(筑田牛沢線)よりも新しい林道である。未舗装の部分もあってそれが良い。高度を上げると視界が開け遠く弓張山系の山々が連なる。豊橋や豊川の市街地もすっきり見渡せる。新幹線がゆっくり移動(遠いので)。足元には自動車部品メーカーの工場が見える。周りは主にヒノキの植林。雑木の多い室林道本道とは鳥の種類が多少はちがうのであろうか。沢沿いにはホオジロやアオジがいた。入り口でも見たカワラヒワが群になってヤシャブシの種を啄ばんでいた。そうなると期待してしまうのは、ここへマヒワが来てくれないか、という事。室林道は直ぐ隣、期待しよう。高圧送電線の鉄塔が直ぐ側に見られる所に来た。急な斜面に堅固な基礎が造られていた。ここの搭は一級のサイズである。工事の様子は室林道のセンサスの最中に何度も見てきた。塔の基礎付近に来たときに、若いヒノキの林の中からマヒワの声がしたのであった。担いでいた三脚を下ろした音で一斉に飛立つ。「やあやあ飛んでいってしまったか」。残念がっていたが、直ぐに舞い戻って来てくれ、今度は、頭上にあるヤシャブシにとまった。そして、真剣に実を啄ばみ始めたのであった。やれうれし、これで新年のHPのモデルは決まったな。20、30羽はいたであろう。黄色い色の鳥は結構いる。室林道では、キビタキ(スターである)、キセキレイ、カワラヒワ、アオジなどだろう。中でもマヒワの黄色が私としては一番気に入っている。古代色の鶸色もこの鳥の色からつけられたと聞いたことがある。由緒正しい鳥をお正月にみられたのは嬉しいこと。
オシドリ
①木陰からちらりと見えるのに出てこない ②ようやく1羽が ③日光が気持ちよいのか ⑤オスとメス仲良く
室林道とマヒワ
①-⑥室林道からの眺めはなかなかのもの ⑦-⑩マヒワのオス ⑪⑫マヒワのメス
2009 1 4 碧南火力発電所
ずっと気になっていた場所である。なかなか行く機会がなかった。正月なら道も空いているだろうと思って、思い切って出かけることにした。音羽から蒲郡に抜けたらあとは碧南まで一直線(気持ちいいほど真っ直ぐである)。吉良を過ぎると左前方に2本の煙突が見えてくる。それが碧南火力発電所。発電所の南端に一般の人に解放された区域があり、電気館、広場、エコパークが隣接している。主にエコパークを歩いて野鳥を探すことにする。様々な樹木が植えられているが照葉常緑樹が多いようだ。実の成る樹も多くて野鳥たちの楽園といったところか。冬季はどんな鳥がいるだろうか。まずはヒヨドリ、一番鳴き声が聞かれる。個体数ではメジロが一番かもしれない。常緑樹とメジロの体色は相性が良い(捕食者が見つけ難い意味で)し、実が一杯のこの地に一番似つかわしい鳥であろう。冬の鳥では、アオジ、ツグミ、シロハラ、ウグイス、ジョウビタキであろうか。コースには海鳥の観測シェルターや小川などがあって変化に富んでいる。シェルターは大変立派なものであるが今は開店休業の状態だ。シギ・チドリの渡りの季節に訪れたい。カモを見るためには高台に登らないといけない。海とは隔てられた一角に凄い数のカモがいた。数えることなんて出来ないし、やる気も起きない程の個体数である。広場から歩道橋を渡ってエコパークに向かうのであるが、歩道橋からは碧南からの眺めが一望できる。西は海である。貨物船が何艘も停泊していた。遠くには渥美半島や知多半島が見え、半島の切れた先には、三島由紀夫の潮騒で有名になった神島も見える。東は濃尾平野、更に山々がぐるりと見渡せる。一際高く雪を頂いた白い山は、木曽御岳、中央アルプス、南アルプスである。南には、愛知県最大の矢作川の河口が見える。上空にはトビがゆったりと帆翔。トビに混じって白っぽい姿のミサゴが。思わずカメラを向けた。2本の煙突からは白い煙(一本はほとんど分からないほど透明な煙)がたなびき、発電機とおぼしき大きな建物から低い音が聞こえる。石炭火力発電機とは出力では比ではないが、環境への優しさでは断然勝る風力発電機が並んでいたのは印象的だ。
発電所からの風景
①トンネルをくぐり広場へ ②広場は静かだった ③発電所が迫る 歩道橋から④碧南を望む ⑤⑥発電所の台所(燃えカスも莫大) ⑦-⑩エコパークのコース
⑪-⑬発電所のシンボル ⑭御岳 ⑮南アルプス(聖・兎・赤石) ⑯中央アルプス
コースで見た野鳥
①沢山いたヒヨドリ ②ジョウビタキ(メス) ③カワラヒワ(オスとメス) ④カワラヒワ(オス) ⑤同(「メス) ⑥キジバト ⑦‐⑨スズメ ⑩ツグミ
⑪ゆったり帆翔のトビ ⑫ムクドリも多い ⑬⑭トビと一緒に舞うミサゴ ⑮大きな魚を捕まえたミサゴ ⑯ハシビロガモ ⑰-23カモの大群(パノラマ写真です)
24部分を拡大
2009 1 5 萩と近辺の野鳥
正月休みで体も少々鈍っていたこともあり、最後の休みに思い切って一日中、鳥を見て歩こうと思い立った。コースは、観音山林道を登り大代に出て、峠を下った先の鳥川(とっかわ)から室林道に出て、我家に戻るという壮大なものであった。観音山では2羽のカヤクグリを観察する。2個体の確認は初めてだったので大層嬉しかった。観音山の山頂へ登ろうとしたが、途中で藪になってしまい断念。無理すれば可能であったかもしれないが、まだまだ先は長いと思い引き返した。大代ではヒガラが、そして急な下り坂でそろそろ足の痛みが出てきた。スタートして4時間経っていた。鳥川を歩いて気が付いたのは、炭焼窯とか、平成の名水とか、建て看板が沢山立っていたということ。ホタルは鳥川の自慢である。奇麗な川のある箇所で、川底に何かが捨てられていた。何かあるのかなと思っていたが、近くに、「カワニナの餌としてここに好物を捨ててください」という看板が立っていたことで納得。メロンの皮も好物らしい。贅沢なものだ。車で通り過ぎるとあっという間の距離でも、2つの足で歩くと随分と掛かるものである。6時間弱を掛けて1周した。最後は足も痛くなり家に着いたときはほっとした。
①②萩の里山 ③④⑤観音山 ⑥⑦観音山から眺める ⑧⑨鳥川 ⑩萩への峠に到着(疲れた) ⑪室林道から下りてきた(ホッとした)
2009 1 10 平尾・財賀寺
最近では最も多い11人の子どもたちが集まった。雲は全くない。強風が雨雲をすっかり追い払ってしまった。ゴーゴーと山全体が唸っている、そんな表現がピッタリの日、山の尾根伝いに歩を進めて行く。平尾CCの池では再びカワセミが出迎えてくれた(先回の、駒場池探鳥会でも大いに楽しませてくれたのだが)。どうやら2羽いるようだ。つがいなのだろうか。ここからは豊川自然歩道を歩いてゆく。山の尾根まで一気に登る探鳥会名物の心臓破りの階段が見えてみた。子供たちの背中を見ながら大人2人はマイペースで登る(子どもたちに負けないようになんて思わないほうがよい)。尾根は木立が遮っているといっても風が吹きぬけ音がもの凄い。大勢でいるから安心できるが、1人2人ではきっと心細いだろう。自然の怖さの一面を子どもたちそれぞれが感じているのでは。最後に奥の院の急な坂道を降りると到着。ひとりずつ鐘を突いてお参りした。一番の楽しみのお昼の弁当。山門の隣の日溜りの広場でシートを広げて思い思いに食べる。ここでちょっとした出来事が。1人場所が確保できない子が出来てしまったのだ。涙目の子を上級生が迎えて事なきを得た。あとは遊びタイム。大人は昼寝を貪る(そう願いたいが、いかんせん外はやはり寒い)?。子どもは遊びの天才だ、とはよく言った。大きい子も小さい子も一緒に遊ぶ(変に上級生が気を使っていないのが返って気持ち良い
。再び強風の山の中をさまようように進み、見覚えのある萩の家々の近くまで来た。皆疲れた素振りも見せず萩小に戻ってきたのだった。
2009 1 11 室林道ラインセンサス
寒い。室林道で初めて氷柱ができた。時折、空から雪のようなものが落ちてくる。寒さに、野鳥もあまり活発に動けないのか、センサスの間、鳴き声が聞こえてくることが少なかった。耳を澄ませて声を聞く、そんなバードウォッチングが大好きである。アオジvsクロジ、エナガvsヒガラ、などは聞き分けが難しい鳥。声と姿が一致した時はやはり嬉しい。はっきり聞こえるのは、ハシブトガラス、カケス、ウグイス、ウソなどである。中でもカケスの声が今までのセンサス時よりも多かった。ウソは、黙々とサクラの花芽を啄ばんでいた。果たして、今年の開花は無事出来るであろうか。鈴をぶら下げた猟犬が通り過ぎてゆく。今まさに狩猟期の真っ最中である。シカやイノシシが対象になろうが、農作物への被害も多く、かといって撃ち取られるのは可哀想。複雑である。
2009 1 18 羽根・長根の田んぼ
畦の草には白く霜がついていた。草の毛が模様のように浮き出て見えるのはなかなか美しい。正月が過ぎると田んぼの田起こしが始まる。すると、それを待ちかねたように野鳥たちがやって来る。土の中からミミズなどが掘り起こされるからだ。冬鳥の代表格でもあるツグミ、飛来してからは暫く山で過ごし、今の時期に一斉に平地に下り田んぼで採餌する。その変化は見事と言うしかないほど。今朝の羽根・長根の田んぼも例に漏れることはなかった。ツグミは噤むが語源らしい。あまり頻繁に鳴くことは無いのは確かである。採餌の途中頻繁に上空を見上げるのは捕食者に対する警戒心からであろう。同じ田んぼにいるムクドリはそのような行動はあまり見ない。ムクドリは群れで採餌するので、交代で警戒担当をしているのかもしれない。それに比べツグミは、基本的には単独で採餌する。だから、採餌と警戒を独りでやらなければならないのだ。見ていると警戒により時間を費やしているように思える。ヒバリの行動も活発化しているように思える。ヒバリの初さえずりが楽しみである。(昨年の羽根・長根での初さえずりを観察したには3月15日であった)
羽根・長根の風景とツグミ
霜の結晶が美しい ツグミの個体数が増えた(長いヒゲがあったのとは)
2009 1 24 羽根・長根の田んぼ
この冬一番の寒気襲来と気象予報士の言葉にすっかり怖気づいていた。確かに寒くはあったが震えあがる程ではなかった。随分と冬の探鳥会を経験したが、もっと寒いことは何度もあったような気がする。萩小の資源回収を手伝った子どもたちがそのまま参加してくれた。今回も11人と大勢だ。今回は代表的冬鳥のツグミを覚えることを目当てとする。そのツグミの最初の姿は川原の田んぼ(下加茂神社の近く)で見た。茶系羽色がなかなかである。コースのポイントポイントではきまってモズの姿があった。尾をクリクリ回す小粋な姿が絵になる鳥だ。羽根・長根の田んぼに来ると冬の厳しさを思い知らされることになる。北風が田んぼを吹く抜けている。一見何もいないように見える田んぼだが、実は、数多くの野鳥が生活しているのだ。セグロセキレイやハクセキレイは良く目立つので直ぐに分かるが、カワラヒワの群が採餌していてもなかなか気付かない。人の気配で一斉に飛立つ姿に逆に驚いてしまうのだ。電線にスズメがとまっている。それがまた見事なほどきれいに並んでいる。寒かったので田んぼ道をランニングすることにした。私も子供たちの後を追いかけて走ったが、寒さをしのぐには好いかも。1年生から6年生まで賑やかな探鳥会であった。
2009 1 25 室林道ラインセンサス
再び寒さが厳しくなり野鳥たちには一層厳しい季節となった。室林道は南斜面に開けているので比較的暖かいが、それでも日の当りの悪いところには氷柱が成長していた。マヒワがヤシャブシの実を突いている脇で、ウソがサクラの花芽を啄ばんでいた。両者に共通するのは、時間を惜しんで食べていること。いさかいや小競り合いなどすることなくひたすら啄ばむ。センサスコースの折り返しでメジロがやはり黒く熟れた実を食べていた。こちらは頻繁に互いにちょっかいを出していたことが印象的であった。冬を生き延びてこそ自分の未来がある(遺伝子的にいえば)。今まさに選択圧が掛かっているのだと感じた。
冬を生き延びるためにひたすら食べる
①-③マヒワとヤシャブシ ④-⑥メジロとタラノキ ⑦⑧ウソとソメイヨシノ
2009 1 27 葦毛湿原
会社の休みをとり用事を済ませた後、久しぶりに葦毛湿原に向かった。久しぶりは道を忘れてしまったくらいに本当だった。それでも何とか到着。停めた車から見た光景が最高だった(湿原本体よりも)。シメとイカル、あのデカイ嘴と強面(シメのこと)が20羽以上も群れていたのだ。枝に止ったり、地上で木の実を食べたり大賑わいである。用心深いスズメたちはシメよりも離れて食事中。さらには群をつくる事のないツグミも仲間入りしてきた。相変わらず空を仰ぐ恰好をしているが少し滑稽であった(可哀想かな)。冬の湿原は静かだ(ひと気がない)。林の中からはシロハラの声がする(一番多い)。湿原であるから川の流れもある。水を堰きとめたため池にはヒドリガモがたった3羽だけいた。やはり最初に見つけたシメ・イカルが一番だったようだ。
2009 1 30 寺ノ入林道ラインセンサス
暖冬を証明するような暖かい朝を迎えた。用事を済ますと11時になっていた。しかし、折角の休みをぼんやり過ごしていては勿体無いので、家には帰らずその足で三河湖に向かった。直ぐにでも雨が落ちてきそうな雲いきだ。仕方がないので傘を腰に差して(人目が無いので)歩き出す。静かな山の中は小鳥たちの冬を生き延びるための懸命な営みの熱気に溢れていた。マヒワがスギの実を啄ばんでいた。室林道ではヤシャブシを好んでいるマヒワも、ふんだんにあるスギの実を知らぷりは出来ないようだ。人工林には野鳥が少ないとよく言われる。多様な樹種の森の素晴らしさは否定できないが、スギの林でも種子食の鳥にとっては大切であることは、冬の採餌を見ているとよくわかる。ヒガラは寺ノ入林道で最もよく見られる鳥のひとつであろう。ごく小さな声を上げ林の中を移動するが、カラ類の中でも小さな姿なので直ぐにわかる。カラ類といえば、シジュウカラとヤマガラが囀っていた。地上にも小さな鳥が頑張っている。沢沿いに棲息するミソサザイである。いつも声ばかりのこの鳥がサービス精神よろしく、尾羽をピンと上げて出迎えてくれた。といよりは、別の個体と競い合っているのに出くわしたのだった。ミソサザイの姿を見たいばかりによく冬の山に出掛けたものだ。もちろん今でも逢えたら嬉しい。冬の山に似合うのがカケスだ。しわがれた声が山の空気を切り裂いて響くのだ。腰に差した傘が役立つ時がきた。我慢を重ねた雲がついに耐え切れず雨粒を落とし始めた。カメラを背負って来なかったことは正解であった。雨が降っても寒さは全く感じない。それどころか、手袋をはめずに真冬の寺ノ入林道を歩けるのはあまり記憶にないほどである。おかげで気持ち良く2時間30分のセンサスを終え山を下りた。
2009 2 1 室林道ラインセンサス
新しい年が始まったと思ったらもう12分の1が終ってしまった。時間というものは何だろうと思う。暖かい北風というあまり経験することのない状況が2・3日続いている。室林道にも強い風が吹いていて送電線がブーンとうなっている。しかし、寒さは感じない。本当に寒いのは、風が吹き付けなくて、日差しがあまり無い所、いわゆる底冷えという奴である。時間帯が遅い(12時少し前)影響もあろうがあまり鳥の声が聞こえない。ヒヨドリとハシブトガラスとか、大きな声の鳥の数が少ないのだ。ウソやヤマガラは居るには居るが元々それ程大きな声では鳴かない(囀りは別である)。だから、本当に鳥が居なくなったのでは、と思えるくらいである。2日前に寺ノ入林道でヤマガラとシジュウカラの囀りを聞いたので室林道でも期待していたのであるが、はっきりと囀っている個体には出合えなかった。なにやら白い綿のようなものが舞っている。よく見ると小さな竹とんぼのようなもの。竹の軸のつけ根種が付いている。枯れや植物の種が強風にあおられて空高く舞い上がっているのだ。新しい命がまた引き継がれてゆく。
室林道
日差しが強くなってきた
 |
 |
2009 2 7 新城総合公園
安田先生から薦められて今年の6年生を送る会は、新城総合公園で行なった。小春日和の穏やかな青空のもとで子どもたち18人は思いっ切り走り回った。その分野鳥の姿は少なめではあったが、あれもこれもと欲張るなという事だろう。ピーカンの晴天に野鳥の方は人前に出るのが気恥ずかしくなったのであろう。そんな中でもハシブトガラスとトビのちょっとしたいさかいは目を楽しませてくれた。小鳥たちは口をつぐんでしまったようだ。それでも、エナガの群が公園の雑木林を群になりながら採餌するのをちょっとだけ見られた。運が良ければヤマセミもいるらしい池にはマガモとカルガモの姿があった。公園内のコースにはいたるところに遊び道具が設置されており、早く遊びたい子どもたちは気が気ではない。お昼ご飯を食べるまでは鳥を見る約束で我慢させる。そして楽しみの弁当の時間。思い思いに陣取ってお昼ご飯。私は自炊の野菜炒めをおかずに。コンビニ弁当でなくて良かった。遊ぶ前に大事な儀式がある。6年生を送る会だ。一列に並んだ6名の6年生に下級生から挨拶。その後に6年生から答礼を返した。それぞれに稚拙ではあるが気持ちを込めた挨拶であった(この時には何時も感動を覚える)。最後は広場で思いっきり遊んだ。私も牧野さんと遊具を回って遊んだ。中でも水平からジャンプするスリリングな変形滑り台は面白かった。童心に返り時間を過ごしたことは私にとっても有意義であったと思う。探鳥会や子供たちのお陰と感謝するばかり。バスの中で心地良い披露を感じつつ帰途に着いた。
2009 2 14 室林道ラインセンサス
果たして冬鳥が居るのか知らん、そんな気持ちにさせるほどものすごく暖かい(気象庁が記録を取り始めて一番という)。心配をよそに冬鳥たちは元気にいた。ウソ・ヒガラ・ルリビタキ・ミソサザイの地鳴きを聞くことができた。ルリビタキは奇麗なオスで、道路をホップするようにして採餌していた。暖かい風が山の斜面を吹き渡ると、黄色い煙が舞い上がる。花粉症の人が見たら震え上ってしまうだろう。室林道は杉林も豊富である。お陰で、種子食のマヒワやカワラヒワなどのアトリ科の野鳥には好評である。アカゲラがキョキョと鳴いて飛び去った。アカゲラの羽には他に無い真っ赤な部分がある。その赤さに対抗するように、数輪のヤブツバキの蕾が開いていた。
2009 2 15 我家周辺
あまりに暖かいので変な感じである。野の草花も春と思って開いてしまっている。オオイヌノフグリ、ナズナ、ホトケノザが笑っている。ツグミが春のような風に吹かれ上空を見上げていた。彼等はどのようにしていまれ故郷への旅立ちの日を決めるのであろうか。空を見上げているのは望郷の念、それとも、捕食者への警戒?。前者であって欲しいと思うのは身勝手であろうか。ツグミを撮っていたら空からセグロセキレイのけたたましい声がした。慌てて見上げると、2、3のセグロセキレイにモビングされているタカの姿があった。どうもハイタカ類のようだ。オオタカにしては少し小振りのようだ。ハイタカかもしれない。旋回中のタカにピントを合わせシャッターを切る(上手く写っていたらおなぐさみ)。歩いているのが幸せになる上天気であった。
野鳥たちものんびり、しかし、気をつけろ! 上空ではタカが狙っているぞ!
①ヒヨドリ ②ハクセキレイ ③ホオジロ ④⑤ムクドリ ⑥セグロセキレイ ⑦-⑨ツグミ ⑩-⑯ハイタカ(のようだ)
2009 2 21 室林道ラインセンサス
2年生と1年生の子ども3名、先生とその妹さん、自分、都合6名の程よい人数で探鳥会を行なった。天気は良いのであるが風が強い、羽根・長根の田んぼは厳しいと思い急遽室林道に車2台で向かうことにした。室林道は底冷えする、しかし、明るい日差しが注ぐ中を歩くのは気持ち良い。野鳥の方は少な目であった。カワラヒワ・マヒワ・ヤマガラなど。先生は、微かな声を見逃さずに、「今、鳥の声が聞こえました」と言う。少なからず感心した。持ち寄ったお菓子で、山上でのパーティーと洒落込んだ。歩いてお腹を空かせた子どもたちは、あっという間に平らげた。野外で食べるものは何でもうまい。妹さんにも時々は探鳥会に参加してもらいたものだ。「春になったら、オオルリやキビタキを見せますよ」と話した。
探鳥会メンバー
2009 2 22 室林道ラインセンサス
昨日の土曜探鳥会であまりに鳥の姿が少なかったので、もう一度確認すべくセンサスを開始した。結果、それほど少ないという感じはなかった。冬鳥では、マヒワ、ウソ、シロハラを確認。今日は、彼らよりも留鳥であるヤマガラやシジュウカラの方が目に付いた。両者とも、囀り個体も表れた。各地からのウグイスの初鳴きの便りを聞くようになった。我が室林道では未だ囀りまでは聞いていない。懐かしい声との再開の日が楽しみである。
2009 2 22 羽根・長根ラインセンサス
冬鳥はどんなだろうか、幸いにも今日は北風もあまり吹いていない。タヒバリやカシラダカ・カワラヒワの群が、明るくなった日差しの中で乱舞する光景を期待してみたものの、最近は、目を見張るような群にはとんとお目にかかっていない。群を養う力が無くなったのだろうか。辛うじて30羽くらいのカワラヒワが田んぼで採餌するのを見つけた。カシラダカは本当に見かけなくなった。原因は分からないが淋しい限りだ。冬鳥の代表格のツグミはまずまずの数を確認する。もう暫くはこの地に留まるだろう。あぜ道にもあちこち春の息吹が見られた。タンポポの輝く黄色は春の訪れを最も感じさせる。小さな花ではあるが、ホトケノザの紫色、オオイヌノフグリの青色は、園芸種の花々にはない素朴さがあって大好きだ。
田んぼも春の息吹
①タンポポ ②ペンペングサ ③小麦 ④ホトケノザ
 |
 |
 |
 |
2009 3 15 寺ノ入林道ラインセンサス
雨上がりの爽やかさと、赤道の近くまで戻った太陽の光の強さ、ダブルのご馳走である。そそくさと用事(運動を兼ねた掃除)を済ませ、寺ノ入林道に向かったのは10時30分過ぎ。少々遅いか。風はかなり吹いていた。足早に雲が流れてゆく。山が鳴いている。だから、小鳥の鳴き声がかき消されてしまう。囀りならばまだしも、小声の地鳴きは聞き難い。ところが、いないように思えた小鳥たち、実は沢山いたのだ。最初はキクイタダキ、日本産野鳥で一番小さな鳥、絹糸のようなか細い囀りを聞くことができた。それにつられるように他の鳥たちも鳴き始める。ヒガラのツピツピツピ、ヤマガラのツーピーツーピ、カラ類の快活な囀りを聞くと気分が晴れるようだ。囀りの本命のウグイスは室林道に比べると少ない気がした。標高の差が気温の差となり囀りの差にも出ているのだろうか。囀りをするのは樹の上ばかりではない。ウグイスは藪の中にいるし、ミソサザイは林床で囀る。昨日室林道で聞いたミソサザイの囀り、ここ寺ノ入林道でも囀り個体を確認した。重いカメラのシャッターは一度も押さなかったけど、気分は上々であった。
2009 3 18 茶臼山ラインセンサス
2009年最初のセンサスは3月も半ばになってしまった。遅くなった原因は目出度い事ではあるが。休みを取って満を持して茶臼山に向かった。道中何の問題もなく(例年だと凍結する箇所もある)、スキー場こそ残雪はあるが、一般道路には残り雪は殆ど見当たらなかった。おまけに春を通り過ぎたような陽気。標高1200メートルのセンサスコースも暑さを感じるほどである。最初に出迎えてくれたのは、沢から聞こえるミソサザイの囀りとノスリの鳴き声であった。何十倍と大きさが違うのに鳴き声だけで判断すると同じくらいの鳥に思えるのが面白い。駐車場には車の姿はなく閑散としている。その周りの木々でホオジロが囀っているのが大層よく響く。早速双眼鏡を首からぶら下げカメラを担いで歩き出す。暫くはホオジロ、ヤマガラの鳴き声(囀りも含めて)がする。スキー場の脇ではコガラ、シジュウカラの採餌する姿があった。リフトが頭上を通る付近で20羽ほどの群に出会う。アトリ科であることは間違いないが特定できなかった(行きと帰り二度見たのに残念)。ハギマシコである可能性も。ウグイスの囀り個体も確認できたが未だ少ない。あと数日でぐんと増えるのでは。やはり気温の違いが現れているのではと思う。アトリ科ではベニマシコの姿があった。道端の植物の実を食べている。平日の茶臼山で出会う車はほとんど老夫婦が乗っている。その中の1台からの人からザゼンソウの在りかを尋ねられた。そうそう今咲いているんだったなー。フィールドスコープを担いでいる人にも出合った。いわゆるデジスコで鳥を撮る人である。フィールドスコープにデジタルカメラの組み合わせは、写真レンズに比べ(超望遠は超高価)安上がりなので人気があるのだ。アイピース(接眼レンズ)を介しているので周辺像の乱れは残るが、天体写真と違い、中心付近の像が良ければ気にならない。但し、飛翔中の姿を撮るのは殆ど不可能であろう。飛んでいる姿こそ鳥の本来のものと思うのだが。南アルプスの雪山姿をおさめるのも楽しみであったが、黄砂のせいか、今ひとつくっきり見えなかった。しかし、寒さに震えることなく、のんびりと茶臼山の周りを歩くことができ、楽しい一日を過ごすことができ好かった。
茶臼山ラインセンサス 鳥・山・水
①②木の芽を啄ばむベニマシコ(メス) ③④草の実を捜すベニマシコ(オス) ⑤ライトにとまるハシブトガラス ⑥囀るホオジロ(オス) ⑦-⑨囀るシジュウカラ(オス) 南アルプス3000メートル峰たち ⑩赤石岳 ⑪荒川岳 ⑫聖岳と兎岳 ⑬上河内岳 茶臼山の兄貴分の山 ⑭蛇峠山 ⑮大川入山 ⑯恵那山
⑰茶臼山からの南アルプスの眺め ⑱茶臼山湖 ⑲矢筈池 ⑳茶臼山とゲレンデ
2009 3 21 前田町
休日の東名高速を使って前田町の野鳥を観察しに来た。道路が込み合っていないか少々心配であったが、帰り、豊田JCから岡崎間で渋滞に遭遇した。何処まで行っても1000円は良くも悪くもインパクトがある。遠出してのバードウオッチングには朗報か。毎日、出勤前の20分、前田町の田んぼ道をウオーキングしている。ヒバリが囀り、ケリが縄張りを守る、繁殖の季節の到来である。今日もまさにそんな日になった。ヒバリは田んぼで採餌し、地上で囀りを開始し、おもむろに空に飛び上がる。きっと、メスたちはオスのディスプレイを冷静に眺めているのだろう。田んぼが埋め立てられていた。次々と自然が消えてゆく。前田町の野鳥の行く末が心配だ。埋め立て地の近くでセッカの越冬個体のペアがいた。あぜ道には春の花が咲き出した。お馴染みのタンポポ、ナノハナ、オオイヌノフグリ、ペンペングサ。小川の脇では好きなスミレの姿もあった。水路は3面張りなので自然の姿とはいえないのかもしれないが、水のある風景は安らぎを感じるものだ。前田町の小川は澄んでいて見ていても気持ちが良い。
2009 3 21 室林道ラインセンサス
ウグイスの囀りは日に日に増えてきている。新たにメジロが囀りに加わった。コジュケイが大きな声で鳴いている。田んぼからはキジの声、山ではコジュケイがキジの代わりとなる。一方で、マヒワ、ヒガラの声も聞かれた。そろそろ繁殖地に向かって北上するのだろう。室林道でもサクラの開花が始まった。気になるのはその数。この冬も、ウソがせっせと花芽を啄ばんでいたからだ。案の定花びらはまばらである。崖に白いノイバラの花が咲いた。水脈の近くではショウジョウバカマの紫色。淡いタチツボスミレの紫色も顔を出し始めた。あとは南からの野鳥たちの訪れを首を長くして待とう。
2009 3 28 羽根・長根の田んぼラインセンサス
ヤマザクラの薄いピンクとハンノキの新緑の織りなす美しい風景を見ながら羽根・長根の田んぼ道を歩いた。3月の初めの頃よりも気温が低い状態が続いている。今日も、冬の北風が田んぼを吹き抜けていた。ペンペングサが激しく揺れる。長根川を見るとセキレイたちが嘴を川面に打ち付けている。2羽のセグロセキレイが場所取りで小競り合い。直ぐに分かれて採餌をする。2つ目の橋の下流でキセキレイとハクセキレイが、同じ様に尾を上下に振りながら採餌していた。ハクセキレイの方が警戒心が低いのか、どんどんこちらに近づいてて来た。確かにハクセキレイは割りと近くに人がいても気にしないようだ。春の鳥もやって来た。ツバメの夫婦が互いの絆を確認するかのように飛翔していた。鳥は飛んで何ぼ。その意味では、今この場所でツバメを脅かすものは何もない。もうひとつはやはりペアのコチドリ。水溜りを足早に歩いている。黒い土の中に溶け込んでいても目の金縁取りが日に輝き、コチドリの存在が分かる。冬鳥たちもまだまだ生まれ故郷に帰る様子はない。ツグミ、タヒバリがそれぞれの形で採餌していた。カワラヒワの群は春の日に最も似合う。黄色い羽色が太陽の色と一緒だから。いつのまにか、これぞ春に風景と言えるレンゲの花が咲いていた。少しばかり眠たそうな花の形ではあったが。
①②羽根・長根春の風景 ③-⑤セグロセキレイ ⑥ハクセキレイ ⑦キセキレイ ⑧カワラヒワ ⑨タヒバリ ⑩-⑫ツグミ ⑬コチドリ
2009 3 28 我家周辺の野鳥
フィールドノートだけ持ってルナと散歩した。朝から吹いていた北風も大分納まってきたので、あたりの景色もゆっくり眺められる。山々に鮮やかな若い緑色が広がってきている。その緑と接するように咲くヤマザクラの白い色も。田んぼの上を飛ぶのは2種類のツバメ。普通のツバメと腰の白線が大層目立つイワツバメである。2種類のツバメは色形だけではなく飛び方も違う。イワツバメは羽ばたきと滑空を交互に行なう。普通種のツバメは羽ばたきが主体である。山陰川の堤防に植えられたソメイヨシノが5分咲きくらいになった。川面に映ってなかなかいい光景だ。自然のものではないがレンギョウの濃い黄色も春らしくていい。ルナが匂いを嗅ぐような仕草をする。彼女は野の花の香りをどのように感じ取っているのだろうか。第2東名の工事用道路を舗装していた。着々と準備は進んでいる。それこそ莫大なお金をかけての工事、どこが潤うのやら(少なくとも一般庶民は税金を払うだけ)。工事の脇で見つけたのが色の全く違う2羽のアオジとジョウビタキのオス。彼らもやがて生まれ故郷の地を目指して北上する。これから庭に植える花の苗を買いに行こうと思う。
2009 3 31 宮路山から西切山ラインセンサス
休みを取ったので、用事を済ませ、宮路山と西切山林道をラインセンサスした。宮路山は豊川市の西に位置し、隣の、蒲郡市と隣接している標高360メートルあまりの山である。山頂からの四方の眺めは素晴らしい。特に、三河湾の眺めが気に入っている。私の小学校時代の遠足の中でも、宮路山から蒲郡の海岸までの縦走は、今でも記憶の奥底に残っている。赤坂の街から宮路山への登り道はヤマザクラと新緑の織錦。それに引き換え、道脇のソメイヨシノはガッカリな姿である。こちらも室林道と同様に、冬鳥でサクラの花芽が大好物のウソが、すっかり平らげてしまったようだ。谷からはウグイスの谷渡りが、山側からは本格的に囀りをし始めたメジロが、本格的な春の訪れを告げていた。宮路山は花も多い。有名なのはコアブラツツジ。ドウダンツツジの仲間で、春は可愛らしい釣鐘状の花、秋は(こちらの方が人気があるが)燃えるような紅葉、さらに、ヤマザクラ、ヤブツバキなどが山を彩るのである。それらも良いが、私としては、可憐なタイツボスミレを是非お勧めしたい。上品な色が何ともいえない。山頂直下の駐車場に車を停め、西切山林道をラインセンサスする。この林道は、この地の中でも、最もコマドリの逗留の可能性が高い所であった。4月上旬サクラの咲く頃の早朝に、コマドリの初囀りを探して林道を歩くのが、17年来の楽しみである。しかし、コマドリに異変?。確認個体数が激減しているのだ。逗留地である音羽も、繁殖地である茶臼山でも、コマドリの美しい囀りを聞く機会がめっきり減ってしまった。今日のセンサスでコマドリやその他の夏鳥を確認出来るとは思ってはいない。いないことが分かればよいのである。センサスを開始して間もなく、2種類のキツツキが姿を見せた。オリーブ色のアオゲラ、白と黒のまだら模様のアカゲラ、共に、頭部とお尻の真っ赤な色が大変美しい。アカゲラはつがいで、2羽が互いに呼び合っているようだ。頭上から聞こえるのはメジロの囀り。メジロは昔からウグイスと並んで囀りを愛でられた鳥。ウグイスは大名に、メジロは商人たちに愛されたという。やはり、夏鳥の気配はなかったが、もう間もなく美しいすがたと歌声に出会えるだろう。彼等は生まれ故郷の日本に来てどんなにか嬉しいことだろう。沢山の苦難を乗り越えて(途中で命を落としたものもいるだろうに)ようやく着いたのだ。許せないのは、そんな鳥たちを狙う密猟者だ。自分の満足のためになんと卑劣なことをしていることだろう。
2009 4 4 室林道ラインセンサス
里山は新緑に彩られている。野鳥たちの繁殖の季節の始まりである。留鳥たちは地の利を生かしいち早く縄張りを主張し、番う相手を見つけはじめている。一方、繁殖と休息とを異なる場所で過ごすことを選んだ鳥たちは、抗しがたい気持ちの赴くままに、生まれ故郷の森や草原、さらにはツンドラ地帯を目指して旅立つ覚悟を決めている。平地ではツグミやジョウビタキが、そして、山ではマヒワたちが北に向かう日を待っている。室林道でも、マヒワが最後の採餌に明け暮れていた。一方で、故郷を目指す鳥たちは。今日は、そんな鳥たちの一陣を見つけた。室林道の藪から聞こえる虫の声。いや虫ではない。れっきとした鳥ヤブサメ。ウグイス属では小さな部類に入るこの鳥は、林床の枯れ葉色と同じ茶色の体を持ち、そこで暮らしている。シシシシ・・・・と虫の鳴き声そっくり。声の発生源を定位することが大変困難な鳥である。一ヶ所で鳴いているのは間違いないのであるが、まるで前からも後ろからも聞こえてくるようである。小さなヤブサメと一緒に来た訳ではないだろうが、今年初めてのサシバも。この中型のタカは日本が生まれ故郷。越冬地からやって来てまもないのだろう。彼は、声を上げることなく、羽ばたきと滑空を繰り返して山の端に消えた。ヒノキの林を移動する鳥たちの中にヒガラの姿を見た。そういえば、少し甲高い声で囀りをしていたのは、シジュウカラではなくヒガラだったのかも知れない。両者の囀りを聞いていると時々迷うような時がある。里からドカンと花火の音がした。春祭りを告げる音である。ドシンと音をたて地上に下りたテンが、金色の毛並みを輝かせて走り去った。
2009 4 5 西切山ラインセンサス
先週に続いて再び西切山をセンサスした。目的は夏鳥の飛来確認。その中でもコマドリの確認をするためである。結果は、コマドリはおろか、それ以外の鳥たちの姿・声もまったく無かった。地の鳥たちの囀りはまことに盛んであった。ウグイス・ホオジロ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロはコースのいたる所で囀っていた。コースの部分部分では個体数に差がある。多いのは樹種の豊かな所、少ないのはヒノキの単独林、その図式はここ西切山林道でもそのまま当てはまる。かといって、単独林は駄目かというとそうでもない。ウグイスはそこでもいるし、エナガ、マヒワ、ヒガラといった鳥はかなりの個体がそこで採餌している。囀り個体のようにはっきり存在を確認できないだけかも知れない。ヒガラやマヒワの地鳴きははっきりと聞き取れないことがままあるからだ。昨日室林道でヤブサメを確認したので、夏鳥の確認を期待して歩いた。しかし、コースからはそれらしい声は聞かれなかった。
2009 4 10 茶臼山・高値・蛇峠山・室林道
会社の休みを取って長野県最南部の山を登った。最初に向かったのはやはり茶臼山。もしかして夏鳥が来ているかもしれないかと思ったからだ。それと、距離的には近いとはいえ、これから向かう高嶺・蛇峠山と比較するのは意味がある。行きは設楽町から茶臼山高原道路(今は無料となった)を通る。その高原道路で車を止めて野鳥を観察する。そきは牧場地帯で今までは来たことが無い場所なので新鮮な気持ちになった。直ぐ近くではヒガラが囀り、カケスがふわふわと舞うご機嫌な所。開けた場所を双眼鏡やフィールドスコープで鳥の姿を探すのは、バードウォッチング一番の醍醐味である。私はどちらかと言うと道路にそってラインセンサスする機会の方が多くて、姿よりも鳴き声ばかりで探すことに慣れてしまっていて、このような場所でのんびりと定点観察するのに憧れさえ感じる。200メートルほどの牧場にまばらに生えている木々に鳥の群が舞い降りた。なんだろうと双眼鏡を向ける。どうやらカシラダカみたいに見える。春先の、カシラダカの集団囀りが頭に浮かんだ。今年の最初の茶臼山観察では出会えなかったので嬉しくてならない。茶臼山周回道路を車を止めながら進む(何時もは歩き)。平地と同様にウグイスを初めとする野鳥の囀りで満ちていたが、やはり高原と思わせる鳥も出現した。1つはルリビタキ。平地で越冬したものが繁殖のために山に戻って囀りをしていたのだ。もう1つはゴジュウカラ。カラ類のなかでは見つけ難い部類に入るが、今日の山歩きでは、茶臼山・高嶺・蛇峠山すべてでこれら2種類の鳥を観察することができたのは大層興味深かった。高嶺へは売木村経由とした。売木峠・平谷峠2つを越してゆくが、峠から流れる川では、沢音に負けない大声でしかも美しく囀るミソサザイたちに会うことができた。大げさに言えば数百メートル置き、それこそいたる所から声が聞こえたきたのである。高嶺山頂からの360度の眺めは素晴らしい。南には愛すべき茶臼山、北は茶臼山の兄貴分の恵那山と大入川山(5月に登ろうと思っている)。東は南アルプスが圧倒的な存在感で聳えている。思わず手を合わせたくなるような光景だ。高嶺でも夏鳥を期待していたが、残念ながら果たせなかった。最後は3山の中では最も高い蛇峠山。治部坂峠(1200メートル)から別荘地を通り抜け馬の背(1400メートル)まで車で行ける。そこから先は歩き。初夏の陽気でもあり、重いカメラを担ぎでいると汗が滲んでくる。ウグイス・コガラ・ヒガラは無論のこと、例のゴジュウカラとルリビタキの囀りも聞こえる。これで、1300メートル以上の標高では、両者の存在を確認することができたと思う。蛇峠山からは東の空高く南アルプスを、北の空には御岳・乗鞍が微かに望むことができた。乗鞍を見たのは初めてなので大層嬉しかった。南アルプスを見て感じたのは、茶臼山・高嶺・蛇峠山それぞれで、山脈との距離や角度が変わって山の形が違って見えるということである。茶臼山では聖・赤石が大きく見え、蛇峠山では、北岳が茶臼山ほど小さく(遠く)見えないのである。午後2時に帰途につくことにした。国道153号線を軽快に走り、東海環状・東名高速を使う。午後5時以前に音羽・蒲郡インターを下りると料金が半額にならないので、時間を気にしながら帰った。萩町に着いても未だ日は高い。そこで、夏鳥が来ていないかしらと室林道に寄ることに。何時もの半分だけ歩いて今日の野鳥三昧を終えた。
①茶臼山からの高嶺山頂(展望台が見える) ②高嶺からの平谷の町並 ③険しい高嶺の谷 ④高嶺山頂から蛇峠山と南アルプスを望む ⑤蛇峠山馬の背にあるGPS基準点 ⑥蛇峠山から茶臼山を臨む ⑦蛇峠山は中継アンテナが林立する ⑧蛇峠山の東に聳える南アルプス ⑨高嶺で撮影したゴジュウカラの囀り
2009 4 18 宮路山
2009年度のスタートは宮路山から。若緑が美しい登山道を、主役の子どもたち8名と大人7名が寄り添い、ゆっくりと山頂目指して行く。途中、車庫前で店開きするようにして田植えの準備をしているのを見つけ、農家の方と話をする。親切にも、ビニルハウスで緑色に育った稲苗をみせてくれるという。萩小でも授業として稲を育てているので、皆、興味津々のようだ。宮路山への道を高度を上げてゆくにつれ、街の喧騒(主に車の音である)も薄れ、代わりに、野鳥たちの囀りが一杯に広がってきた。ウグイスやカラ類(シジュウカラ・ヤマガラ)はもちろんのこと、遣ってきて間もない夏鳥たちの声も加わっていた。あいうえお順に言おう。アカハラ・オオルリ・キビタキ・センダイムシクイ・ヤブサメ。この中にコマドリの名がないのは淋しいが。山頂真下の急坂は短いが楽ではない。息を弾ませ階段を一歩一歩登る。振り返れば色とりどりの若葉の風景画。足元では薄紫色のタチツボスミレが可憐に咲く。山頂からは先に着いた子どもたちの大きな声がする。水平に枝を伸ばした樹に数人の子が登っていた。毎年、隠れ家と称して遊んでいる樹である。スタートして3時間歩いてきた体は、子どもでなくともエネルギーの補充を欲していた。思い思いの場所で弁当をあける。私は牧野さんと一緒に食べた。牧野さんからはコロッケと漬物、私からはゆで卵を提供した。中腹で曇空にノスリが舞っているのを見た。そして山頂では、普通種のツバメに混じり、ひときわ高速で飛ぶアマツバメに出会うことができた。たった1個体ではあったが予想しないことであったので驚き、そして、嬉しさがこみ上げてきた。やがて山を下りる時間がやってきた。登りよりも下りのほうが足には辛いものだ。階段なんか造ってくれないほうがよっぽどか良いのにといつも思う。
宮路山探鳥会の一日
①音羽川沿いに進むと ②③田植えの準備に出合った ④いよいよ登りにかかる ⑤一休みする ⑥ようやく山頂直下までやってきたあと少し ⑦その前に急な登りがある ⑧途中、振りかえると新緑のすばらしい景色が広がる ⑨1時間半遊んだ後に下山、その前に記念撮影を ⑩森の中の階段コースを下る
⑪ようやく平らな道に出てほっとする ⑫少し時間があったので公園で川遊び(子どもは元気だ)
2009 4 24 寺ノ入林道ラインセンサス
たぶん夏鳥のオンパレードであろうと期待し、寺ノ入林道へやって来た。予想と一致しないことが多いのが自然相手の宿命ではあるが、今日の寺ノ入林道は予想以上であった。何時も目立っているウグイスがどこに行った?と思うくらいに様々な野鳥の歌声があった。今年初確認もあった。寺ノ入林道といえばサンショウクイ。ヒリリヒリリと鳴きながら特徴ある羽ばたきで円を描いている。托卵鳥のツツドリの鳴き声に被托卵鳥のオオルリはピリピリしていることだろう。キビタキが囀るすぐ側で、キビタキの寂びの部分を採用したと思はれる節回しで鳴く鳥がいた。日頃聞いたことの無い声に緊張する。声からは結論を出せなかったので体色から予想してみた。コサメビタキ?、エゾビタキ?。結局分からなかったので、写真を撮り後で調べることにした(どうやらコサメビタキ)。平地に比べるとまだまだ緑色が若く、ヤマザクラの花びらも残っている。改めて寺ノ入林道の位置(標高)を実感することになった。
春爛漫の寺ノ入林道
①緑のトンネル ②周りは新緑で一杯 ③薄暗い場所もあり ④いろいろな木々の色々な緑色 ⑤雑木ばかりではないヒノキも元気一杯 ⑥⑦キビタキが早速現われる ⑧珍しい鳥を見つけた、コサメビタキである
2009 4 24 裏谷
最初から寺ノ入林道と裏谷の2ヶ所を巡ることに決めていた。愛知高原の中心的な段戸山に広がる裏谷とそこに辿り着く道すがらは、10数年前には、茶臼山などと同じくらいに頻繁に出かけ野鳥観察の原点と言ってもよい所であった。対向車が来て欲しくない!
通るのにも勇気がいるような深い谷が迫る道が延々と続くのがこの地域の特徴である。しかし、鳥好きの私にはたまらない所だ。沢音に負けないほど大きな声でオオルリやミソサザイが歌っているし、針葉樹の林には絹糸のような声の持ちのキクイタダキがいる。段戸湖の畔に車を停め裏谷原生林へと向かう。寺ノ入林道と同様にここでも野鳥の声で溢れかえっていた。最もよく聞かれたのはヒガラのソプラノ。美声といえばウグイス・オオルリ・コマドリ・キビタキ・クロツグミを古来から和声四品と称し愛でている。5種なのに四品なのかといえば、ウグイスは別格なのだそうだ。今日の裏谷では4種まで楽しむことができた。ただコマドリだけは叶わなかった。ただ、一声だけカララ・・とコマドリの声がしたことは確認できたのだ。ところがその声は偽者である可能性がでてきたのだ。駐車場から向かう際、大きなレンズを担いで足早で奥に行く人に出会い挨拶をした。随分高そうだな!と思った。野鳥の撮影であることは間違いない。コマドリの声は、そんな人たち10人ほどがバズーカ砲を向けている先から聞こえてきた。なかなかの見ものである!。あきらかに本物をおびき寄せるためのテープの音であることは瞬時にさとった。残念!。コマドリはここ何年とみに個体数を減らしている。音羽での通過個体、茶臼山や蛇峠山での繁殖個体、理由ははっきりしないが殆ど確認できずにいる。ここ裏谷でも以前にはいたのだが。面白く思ったのは、その光景が、同好の士がたむろし獲物を探すというハンターのそれによく似ていたことである。テープを使うのは密猟者がよく使う手である。野鳥写真愛好者を密猟者と同じにしてはいけないと思うが、なにか釈然としないものが残るのは確かである。フレームの外の出来事は出来上がった作品の中には現れてこないからといって何でも有りではないだろうに。まして、土地の所有者の了解を得ず入り込み、さらに、邪魔になるからと木々を切り払ったり、マナーの悪いカメラマンのことが話題から消えることが無いのは残念だ。そんなのは本当の愛鳥家とはいえない。そこで、その人たちに一声かけて通り過ぎた。「コマドリを撮るんですか?」「えも最近は見たことないですよねー」おなじ夏鳥であるコルリがすでにやって来ていて囀りをしているので、コマドリがいれば必ず囀りが聞かれるはずだ(過去の記録ではコマドリの方が先に来ていることが多かった)。最後に見たくないものを見たという、少々残念な裏谷であった。
①段戸山周辺 ②団子島林道 ③段戸路への入り口 ④裏谷原生林 ⑤若い緑が美しい ⑥裏谷のキビタキ ⑦-⑩ソウシチョウ(日本産野鳥ではありません)
2009 4 26 室林道ラインセンサス
三河湖・段戸山裏谷と野鳥観察し、オスたちの囀りの凄まじさを肌で感じた。いよいよ、我が室林道の野鳥たちの出番である。昨日は一日中雨が降ったので満を持して囀りをしてくれるだろう。林道の入り口でオオルリが囀っていた。樹上から聞こえるのはホオジロの囀りである。キビタキはさらに賑やか。2羽で掛け合いコールをする個体もある。双方譲る気配はないが、ツクツボウシの鳴き声を真似た個体の方がやはり迫力があって、メスには分がよさそうである。薄暗い林ではクロジが活動していた。いつの間にか1羽のオスが道路わきで餌をとっていた。驚かさないようにしてカメラに収めた。オスたちの囀りに誘われるようにして付近を行ったり来たりするメスのオオルリを確認した。すぐ近くに、萩小6年生の児童たちが設置したオオルリ用の巣がある(人数分なので随分多い)。利用してくれたら素晴らしいが。もうひとつ嬉しい事があった。サシバが林道で採餌していたのだ。嘴に餌を咥えた個体が飛び去るのを確認できた。付近で繁殖行動をしている可能性がある。ひんやりする天気で季節が戻ってしまったようだ。けれども、生き物たちは着々と子育てを進めているみたいだ。
室林道の子育て
①ヒヨドリ ②ホオジロ ③-⑤キビタキ ⑥クロジ ⑦オオルリのメス ⑧⑨ソングポストで囀りるオオルリのオス ⑩-⑫囀るオオルリ ⑬⑭サシバ
2009 4 29 汐川干潟
数年ぶりに汐川干潟でシギ・チドリを見た。野山の野鳥ばかり見ていたので、急に、海岸に行きたくなったのだった。それに、今がまさに旬なので。これを逃すと1年待たないといけないのも、汐川へと駆り立てた要因である。豊川を渡る時に水位をちらりと見たところ、かなり高い感じがしたので、これは時間を誤ったかなと少し後悔した。干潟に到着したところ、案の定、波打ち際は堤防まであった。まあ上天気だし、のんびり待てばいいや。風だけはかなり強かったがあとは言うことなし。5センチ7倍の双眼鏡で見ると、海の中にいるアオサギやダイサギ、カワウがさかんに餌をとっているのが分かる。さらには、白くスマートな姿のコアジサシが、10メートルほどの高さから海面に突撃する姿もあった。彼等は小魚を捕っているのだ。暫くはコアジサシの行動を観察する。そして、急に頭上から数羽の鳥の声が聞こえたのだ。これがカラスか何かだったら気にも留めないのだが。ところが、その声はまさにシギのそれであった。大きな下に曲がった嘴がはっきり分かる。「チュウシャクシギだ!」。思わず声が出てしまった。まだ海には降りることは出来ないほど潮が満ちている。その後も何度も姿を見せたが、30分ほどしてついに、少しだけ顔を覗かせた砂浜に下り立ち直に採餌を開始した。あとは雪なだれ式にシギたちがやって来ては、良い場所を確保すべく足早に動きまわる。ハマシギの大きな群れが海面をキラリと輝かせてやって来た。そして、丸い形になって嘴を泥の中に突っ込む。チュウシャクシギの嘴が下に曲がっているのに対して、隣の群の嘴は上に反っている。オオソリハシシギである。嘴の形が全く正反対の鳥同士が、すぐ隣で採餌している。見た目は同じ様に見えるがきっと、泥の中での状態は嘴の形と同様に大きく違っているのだろう。今度はチドリがやって来た。田んぼにもコチドリが来ているが、こちらはメダイチドリ。個体数は田んぼの比ではない。繁殖色のベージュ色がとても鮮やかだ。足早に移動して採餌する。堤防の近くでキョウジョシギが数羽で餌を捕りながら移動していた。京女と言われるだけにシギの中でも鮮やかな色をしている。最後にやってきたのは大柄のダイゼン。成鳥は白と黒のコントラストが美しい鳥だ。こうしてみると、シギ・チドリについても、今まさに北上の真っ只中にあるといえよう。彼らの繁殖地は、日本の遥か北の地である。ここは、さらに北に向かうための中継基地といえよう。彼らのためにも、もう1ヶ所たちとも干潟を失ってはならないと思う。
汐川干潟
①未だ干潟は海の底 ②干潟が姿をあらわす ③④⑤コアジサシが優雅に飛翔・時々ダイビング ⑥待ちきれないシギたちが現われる(手間チュウシャクシギとオオソリハシシギ) ⑦羽の手入れをして待つ ⑧中央個体の右足に標識が付いている ⑨オオソリハシシギが採餌開始 ⑩⑪⑫キョウジョシキが波打ちで餌を捕っていた ⑬メダイチドリもやってきた(夏羽が見事) ⑭⑮⑯最も個体数の多いのはハマシギ、一辺に賑やかになった
2009 4 30 茶臼山ラインセンサス
夏鳥の様子を見に茶臼山に登った(今回は本当に山頂に登った)。豊根村のヴィジターセンターではキクイタダキが囀りをしていたし、オオルリやエゾムシクイなどの夏鳥も来ていた。渓流からはミソサザイの歌声がする。山頂周回コースを歩くとやはり、ウグイスの個体数が圧倒的に多い。さらには、麓で聞いたエゾムシクイの囀りも聞かれる。山頂に向かう。周回道路では聞かれなくなったコマドリ、コルリがいるかもしれないと思ったからだ。結果は変わらなかった。茶臼山ではコマドリは殆どか、全く棲みついていないのだ。茶臼山は彼らにとって棲みやすい場所では無くなってしまったのだろうか。周回道路が広くなり行楽の車が増えた、外来種のソウシチョウが急激に勢力を伸ばしニッチを失った、個体数そのものが減少傾向にある、などが要因であろうと私は推測する。山頂からはこれから向かう長野県南部の山々が見える。はたしてコマドリの声を聞くことが出来るであろうか。
①茶臼山牧場 ②茶臼山より恵那山と大川入山を望む
2009 4 30 高嶺
平谷峠をだらだら下ると平谷の町に出る。そこから見る1500メートルを超える高嶺の山容は堂々としていて、きっと平谷の人々のシンボル的な存在なんだろうなと思う。今年になって未だ、色とりどりのパラグライダーが浮かんでいるのを見ることは無い。ここでも鳴き声の多いのはウグイスである。気温の上昇と共にウグイスも標高の高い場所を目指しているのがよく分かる。そして、ここでもソウシチョウの囀りを聞くことができる。高嶺で一番のソングスポット(と自分は思っている)で車のエンジンを止め耳を澄ます。深い谷底からは沢音が聞こえる。野鳥にとっても水はとても大事なものだ。飲み水、命の次に大事な羽の洗濯水、水の豊富な所には餌も多いし、巣の材料になるコケが生えている。林道のセンサスで感じるのは、おなじカーブでも谷と尾根を比べると圧倒的に、谷カーブで野鳥を観察することが多いということだ。ミソサザイは必ずいる。さらに今日はルリビタキの囀りも聞かれる。肝心のコマドリは?。コマドリの鳴き方から考えなければならない。ミソサザイやルリビタキはほとんど連続で鳴き続けるのに対して、コマドリは間隔が広いのである(当然個体差はあろうが)。場合によっては1分以上にもなる。だから、じっくり腰を落ち着けて聞かないと駄目なのである。およそ10分以上は待った時、一声、カラカラカラ・・・、とコマドリの声が聞こえた。第2声はいくら待ってもやってくれなかった。しかし、間違いなくコマドリのものであった。生息は確認できたが果たして?。繁殖しているのだろうかという疑問がわいてくるのを禁じ得なかった。囀りは弱々しいし、オス同士の競い合いの様子が全く感じられない。ここも個体数は極端に減少しているのだと感じた。中腹でオオルリを発見。光線の加減で明るいコバルトブルーの姿がはっきり見えたのはラッキーであった。おなじ場所からは高嶺の隣に位置する蛇峠山の雄大な姿を拝める。そして、その奥には南アルプスの赤石岳が空中に浮かぶがごとく聳え立っていたのだ。
高嶺にて
①カラマツ林の芽吹きが美しい ②高嶺山頂を望む ③隣にある蛇峠山を望む ④赤石岳の白い峰
2009 5 1 あららぎ高原・大川入山登山
今までは蛇峠山までが私のフィールドであった。国道153号線を治部坂峠を越え先に行くことはなかった。今、慣れない道をあららぎ高原に向かっている。会社友人たちと先輩の山荘に一泊し、翌日(5月1日)に、念願であった大川入山(1908メートル)に登ることを計画していたのである。高嶺からも蛇峠山からも、大川入山は見上げる存在であった。山頂はクマザサの明るい緑に覆われ、独立峰のためさぞかし眺めが良いことだろうと思っていた。さらに数百メートルも高いのである。今まで見られなかった野鳥に出会えるかもしれない。期待は膨らむばかりだ。その反面不安も大きい。はたして頂上まで辿り着けるだろうか?。標高1200メートルのアララギスキー場のゲレンデを登山道に向かい歩き始める。手袋が必要なくらい肌寒いは気分は晴々。周りの景色も素晴らしい。メンバーは5人。皆山歩きの経験はほとんど無い。入り口が分からず寄り道をしてしまった(ゲレンデの最上部から上級者用コースを下るはめになった)。ホオジロ、モスなどを双眼鏡で観察する。姿は無理であったが、ウグイス、オオルリ、コルリの囀りもあった。そして、あれほど無理であったコマドリの囀りも簡単に聞かれたのにはびっくりした。ゲレンデを後につづら折れ遊歩道に入った。最初こそ緩やかな登りであったが、その後に、尾根に登る急坂が待ち構えていたとは。一直線に登る難所が次々現われる。息を整えては再び歩く、それの繰り返し。向かいに見える山、三階峰(1400メートル余り)が標高の目安となった。ようやく山頂よりも高くなり、大川入山までの標高差500メートルとなった。尾根道は南と北で全く様相が違っていた。南は、カラマツ林が広がって明るい緑(標高が高いと未だ芽吹ていなかったが)、北は、シラビソやブナの古木が覆う薄暗い森、さらに、北の谷は冷気が辺りの景色を薄ぼんやりとさせていた。そのあたりであったろうか、コマドリのヒンカラカラカラ・・・のいな鳴きが聞こえたのは。高嶺のように弱々しいものではなかった。これこそコマドリと言えた。もう耳を澄ませる必要は無かった。そこで2人が登頂を諦め引き帰した。それほで尾根に登る急坂はインパクトがあった。あとは尾根道を登ったり下ったり。標高が1700メートルを越すとあちこちに残雪があった。滑らないように気を使うため疲れは一層深まる。そして、野鳥観察としては一番のできごとがやがて訪れることになる。最初の声、あれカエル?、私はそうかもしれないと言ってしまった。けれど、何となく違うようだ。カラス科には違いないと思った。その時は、平地のカラスを想像していた。ミヤマガラス?。ここが2000メートルに少し足りない高山であることを失念していた。やっとのことで声の主を探して、大川入山の高さを思い知らされた。ホシガラス!。高山帯の鳥である。今まで2・3度しかお目にかかっていない。一度は、標高2800メートルの木曽駒ケ岳の這松帯であった。目の前に山頂が見えてきた。現在地点も山頂とそう変わりないくらいだ。ということは、下がって登らないといけないという愚痴も出る。しかし、稜線からの景色はそんな愚痴を言う口をつぐませてしまった。東の方面には中央アルプスと南アルプスの白い峰、それに挟まれた伊那谷が眼下に広がっていた。まさに絶景!西は隣接する恩田大川入山とクマザサで覆われた山肌、茶臼山や高嶺が眼下に見えた。頂上には2組の登山者がいた。いずれも治部坂側から登ってきていた。北には御岳と隣にうっすら乗鞍岳があった。早速昼飯。おにぎりとコロッケを頬張る。旨い!。一息ついで野鳥の様子を見る。相変わらずウグイスの声は多い。ヒガラがやってきて目の前で歌い始めた。ヒガラもウグイス同様に登山道全ての場所で鳴いていた。頂上に数10分いたであろうか。軽くなったリュックサックを背負い、今来た道を再びアララギスキー場へと目指す。雪は登り以上に我々を苦しめた。尾根への急な登りは、今度は、つま先を襲う下り坂となる。下り坂の方が辛いのだ。再度のシラカバ林を抜けてスキー場に着いた時はホッとと同時にやったと思った。よくぞ歩き通したものだと。今朝停めた車が主人を待っていてくれたかのように思えてならなかった。
あららぎ高原と大川入山登山
①清流が流れる ②蛇峠山を望む ③幹には地衣類が(霧が多いからか) ④⑤この川でカワガラスを確認した ⑥大入川山ピークは右側(高嶺より望む)
⑦あららぎスキー場からスタート ⑧向かいの三階峰(1400メートル余り)が目安となった ⑨ようやく見つけた登山道入り口 ⑩尾根を上りきると残雪帯に出くわす ⑪ようやく大川入山が見えてきた ⑫蛇峠山も見下ろす位置に来た ⑬山頂が見える(⑥の反対側から見ているので山頂は左のピークとなる)
⑭山頂から望む中央アルプスの峰々 ⑮山頂でヒガラが歌う ⑯山頂付近はクマザザ地帯 ⑰木曽駒を背景に記念写真 ⑱恵那山を望む ⑲ピークに別れを告げる ⑳疲労もピーク 21ゲレンデに戻って自然と笑顔
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2009 5 4 我家周辺
山口さんを連れて昨晩電話のあった人の田んぼに向かった。ケリの巣が田んぼの真ん中にあって(卵は4つ)どのようにしたらよいか相談の電話であった。ともかく現地で落ち合うことにした。専門家に立ち会ってもらうのが良いと思い山口さんを連れて来た訳である。田起しを1ヶ月待てないか確認すると無理とのこと。作業開始の頃にはヒナが孵るので結果的に死なしてしまうことになる。そこで、卵は山口さんに預けることになった。可哀想だが仕方が無い。動物園で貰ってくれないか聞いてみると言う。巣は本当に簡単に皿状に作ってあった。そこにニワトリとウズラの中間くらいの大きさで、グレーに粒粒の斑点のある卵が4つ並んでいた。形状はニワトリに比べ尖っている。尖った形なので巣からうっかり出ても遠くに転がって行かないという利点がある。皿のような巣の形状に適応した形なのだ。8時間くらいは抱卵しなくても大丈夫との事。周りの田んぼは殆ど田植えを終えた。ツバメが雛に与える餌をさかんにとっている。いつの間にか新緑の濃さが増してきて初夏の様相である。サンショウクイがヒリリヒリリ・・・と鳴きながら飛んでいた。民家の直ぐ近くでも沢があれば、バードウォッチャーに大人気のキビタキ・オオルリの囀りがスズメやヒヨドリのようにごく普通に聞かれるのが、萩の里の今日この頃である。私の家でも、家の中でキビタキの歌を聞くことができる。
田植えの季節に咲く花々
①田植風景 ②オオジシバリ ③ハルジオン ④オオイヌノフグリとカタバミ ⑤マツヨイグサ ⑥花菖蒲(園芸種) ⑦バラのアーチ
2009 5 9 室林道
素晴らしい五月晴。前日までの雨を体中に蓄え植物たちは活き活きと萌え立っている。子どもたち5名と大人3名、2台の車に乗って室林道
へと向かう(時間配分や日差しの強さを考えた結果このようにした)。室林道は標高200メートルほど、森の中でもあり平地と比べてかなり涼しく感じるが、今日もそよ風の助けもあって大変気持ちよく歩くことができた。キビタキ・オオルリの囀りを堪能したが、さらにラッキーなできごとがあった。大きな声で囀っていた個体のオオルリが姿を見せてくれたのだ。これだけでも十分なのだが、サプライズは復路で次々と起こった。それは、3組のオオルリのオス・メスつがいが目の前に現われたのである。サクラの新緑の中を2羽が現われては消え、消えては現われ、その度に子どもたちは真剣なまなざしを向けた。ヤマフジの絡む山の斜面の中にオオルリの姿を見つけたのは、参加した子どもであった(彼は、今日のことをいつまでも忘れないだろう)。日陰でおやつタイム。次から次へと小鳥がやって来るのを横目で見ながらお菓子を食べた
①②③室林道からの眺め ④オオルリの巣箱の前で記念撮影 ⑤⑥帰り道 ⑦-⑫子どもカメラマンの作品(自然な笑顔がすばらしい)
2009 5 10 前田町
オオヨシキリの個体数が気になっていたので、休日の朝、勤め先の建物が見える前田町にやって来た。音羽に比べて田植えが遅い田んぼは、用水路から来た矢作川の水が満々と張られ、そよ風の立てる波が、五月晴の強い日差しを浴びてキラキラと輝いている。あぜ道は綺麗に刈り込まれてはいるが、所々、わざわざ残して観賞しようとしたかのように、ハルジオンの薄くピンク色に染まった蕾が、やはり、初夏のそよ風にゆらゆら揺れて、人々の目を楽しませてくれていた。オオヨシキリは田植えを放棄して葦などが生える場所に営巣している。棲みか一帯の縄張りを守るべくオスのオオヨシキリが、葦の根元から穂先へと順々に上りながら囀りをする姿が見られる。だから、前田町から葦が消えるときには、オオヨシキリも消える運命にあることは想像に難くない。最初の前田町の水田は全て水稲が作られていたのだと思う。そこへ、減反のあおりを受けて耕作放棄地が現われ、現在のようにオオヨシキリの棲息地がバッチ状にできあがった。将来は?。耕作放棄地が商用地として転用されつつあるのは紛れも無い事実である。私が前田町の観察を開始したのが2005年の6月であるから、今年は5年目に入ることになる。その間にも、飲食・美容・居酒屋が開店している。トウモロコシ畑が駐車場に変わってもいる。今日確認できたオオヨシキリの個体数は6羽であった。メスの個体数は入っていないが、決して多いとは言えないと思う。バッチ状になった葦のある場所では必ずオスが囀りをしていた。どう見てもオオヨシキリの明日は明るくはなさそうだ。もう1種気になる鳥がいる。ケリである。ケリは全国的にみると東海地方に偏在し、棲息地は局所的である。開けた農耕地で採餌・営巣をおこなう。前田町はケリもかなり多くいて、その意味でも市街地にある自然が残る場所として重要であると考えられる。人間の田植えと野鳥の繁殖とのせめぎ合い(この場合人間が一方的に攻めている)がここで見られるのだ。ヒナが自活できるまでに田植えを待つようなことは普通しないだろう。間に合わない時は卵は放棄するしかないのだ。ケリの巣のありかを見つけるのは容易ではない(たとえ田んぼの中にある場合でも)。しかし、他の鳥が巣の近くに来ようものなら、急降下爆撃よろしくケリの執拗な威嚇攻撃に見舞われることは必至だ。だからその付近には巣やヒナがいることになる。そんな光景はいたる所で繰りひろげられている。その1つで、明らかに成鳥よりも小さなケリの姿を見つけた。双眼鏡でみるともっとハッキリした。間違いなくヒナの姿であった。近くでは親とおぼしき個体が警戒の声を上げ続けていた。雛に注意を促しているのだろう。特に注意を払う必要のあるのはハシブト・ハシボソガラスであろう。前田町にも多くのハシブト・ハシボソガラスが棲んでいる。ヒナの姿は微笑ましいものではあるが、無事に成鳥にまで育つのを祈らずにはいられない。
今日の前田町風景と野鳥
①‐⑤前田町風景 ⑥田植えの準備を手伝う ⑦店舗工事が始まる
野鳥たち
①-④ダイサギの餌捕り ⑤-⑩地上で囀るヒバリ ⑪-⑬ケリの幼鳥 ⑭ケリ成鳥 ⑮堂々としたキジ ⑯-23葦で囀るオオヨシキリ 24-27親に餌をねだるスズメの子
2009 5 23 寺ノ入林道ラインセンサス
昨日の雨に寺ノ入林道林道の緑が一層瑞々しかった。シロモジの葉に載った水の玉に太陽光が屈折し色とりどりの虹が見える。ツツドリが柔らかな声を上げ初夏の訪れを告げていた。寺ノ入林道といえばサンショウクイ。近年、音羽の地でもよく見られるようになったが、やはり寺ノ入林道の鳥のイメージがある。サンショウクイはヒリリ、ヒリリ、と独特の鳴き声を上げながら林道の上空を飛び回っていた。林の中からはキビタキやセンダイムシクイの囀りがする。今日は、センダイムシクイがよく鳴くようだ。登り坂ではミソサザイの囀りが聞かれた。ここは標高600メートルくらいはある。ミソサザイの繁殖にはやはりこれくらいの標高が最低必要なのかなと思う。ようやくオオルリの姿を発見。オスの成鳥がアカマツの梢で悠々と囀っていた。ここはオオルリが多いが、今日見たのはこの個体だけであった。浜松ナンバーの車が止っていたが、どうやら鳥を見に来ていたようだ。センサスの最後で思ってもいなかった鳥の声を聞く。ホイホイホイ。サンコウチョウである。サンコウチョウは暗い林の鳥。寺ノ入林道には明るい落葉樹の木陰が多いので意外な気がする。2度目の声がした。間違いなくサンコウチョウであった。音羽ではまだサンコウチョウを確認していない。一度探してみよう。
緑が俄然濃くなった寺ノ入林道
①オオルリがソングスポットで囀る ②③ピンクが緑に映えるタニツツギ マルハナバチも訪れる ④シロモジの実 ⑤エゴノキ ⑥-⑨林道は新緑のトンネル
2009 5 23 室林道ラインセンサス
寺ノ入林道から戻り用事をすませた後、室林道へと向かう。午後の日差しが日向と日陰のコントラストを際立てていた。スタート地点で、センダイムシクイが力強く囀っていた。寺ノ入林道でもセンダイムシクイの声が大きいのに驚いたのであるが、繁殖も佳境に入ったということか。オオルリも何時ものように囀っている。萩小の子どもたちが作った巣箱に営巣していたオオルリ、またもや心無い人間の餌食になっていた。巣が持ち去られていたのだ。心から憤りを覚える。寺ノ入林道でサンコウチョウを確認した。室林道としては先を越されてしまった形になってしまったので、室林道にはホトトギスでもプレゼントしなくては。最初からそう期待してやってきた。その希望が叶ったのは、毎年、ホトトギスの声を最もよく聞く箇所に来てからであった。もっとも、ホトトギスの声は素晴らしく大きいので、室林道のどこにいても鳴けば直に分かってしまう。ひそひそ話などには縁のない鳥である。いよいよホトトギスもやって来たのだ。青葉がはち切れんばかりの室林道に木霊するホトトギス。俳句の言葉通りである。ホトトギスの声が聞かれた近くでサシバが舞い上がった。あの独特の声を上げながら。シイの樹の薄暗い中から聞こえてきたオオルリとキビタキの囀り、どうやら2羽が接近しているようだ。オオルリの方は小さな声で鳴くのみ、キビタキはなにやら獲物を咥えているようだ。随分と大きな虫をぶら下げている。枝に打ちつけて弱らせている姿はカワセミを想像させる。上空でまたサシバが鳴いた。
①-③木の葉の中には小鳥たちがいっぱい(ヤマガラ) ④室林道に木漏れ日 ⑤室林道からの眺め(萩の里) ⑥体育館や萩っ子の森 ⑦工業団地と羽根・長根の田んぼ ⑧遠くには豊橋市街地
2009 5 30 羽根・長根の田んぼ
年度最初の羽根・長根探鳥会には子ども5人が参加してくれた。萩小から羽根・長根までの通学路を一年間通して歩いてみよう。それがこの探鳥会の趣旨である。毎年同じ事の繰り返し、しかし、それが大切なのだと思う。もう10年以上の観察記録が先輩達の手によって取られている。傘を持参しようか迷った。しかし、探鳥会の後半は日差しで暑いくらい。子どもたちも我慢できずに長根川に入ってしまった。水の冷たさが気持ちよいらしい。羽根・長根の田んぼはダイサギやアオサギがゆったり舞っていた。静かな雰囲気をぶち破ったのはケリのけたたましい鳴き声であった。彼らは子育ての真っ最中、子どもに近づくものには容赦ない威嚇をお見舞いしていた。羽根・長根の初夏は小さな野鳥が主役である。ツバメ、イワツバメはもとより、セッカ、コチドリが早苗がゆれる田んぼ上空を旋回している。今日も、セッカが2組、コチドリも2組確認する。帰り道、子どもたちはあぜ道に沢山生えている草の穂を摘んだ。そして、油断しているといきなり柔らかい穂が首すじをくすぐる。川原の田んぼではカワセミの鳴き声が聞こえた。子どもに餌を運んでいるのだろうか。
探鳥会光景
川で遊んだり、草を摘んだり 子どもたちは遊びの名人だ
2009 6 6 観音山
サンコウチョウを目当てに観音山に向かったのは6名の子供たちと大人4名。サンコウチョウは誰しも見たいと思う鳥ではあるが、個体数が少ないのでそう簡単にはいかないのも事実だ。私としては、先週のように鳴き声くらいは聞かれるだろうと楽観視してはいたのだが。天気予報では雨は朝方だけと言ってはいたが、現に小雨が降っているし、直に止みそうにないので、それぞれ傘を差して行くことにした。入梅には間があるが、そんな感じの探鳥会となった。すでに青紫のアジサイが庭先で咲いていて、今日の日にピッタリである。電線に止るキジバトやホオジロをスコープで捉える。探鳥会用のスコープの中では唯一の防水タイプなので、「雨何するのものぞ」である。近くの山からはウグイスの声が聞こえる。曇天の日は特に声がよく響いて気持ちが良いものだ。民家周辺では、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、キジバトといったよく見かける鳥が迎えてくれた。倉戸橋の下にはイワツバメの巣があって、親たちが雛に餌を届けている。目の前を通り過ぎるのでイワツバメの特徴である腰の白い線が本当によく分かる。ツバメとの違いをしっかり勉強した。民家を通るルートから田んぼ、さらに山を見るルートに入ると、景色も変わり野鳥も変わってくる。ウグイスの声も益々増えてきたし、キビタキの囀りも聞かれるようになる。観音山が近づく頃には雨はすっかりあがり、薄日が差すまでに回復していた。観音山の方角からホトトギスの声がした。あまり大きな声ではなかったので皆に聞こえたかどうか。そして運命のサンコウチョウの棲む林に到着した。休みなく歩いてきたので本当はここで休憩すべきであるが、まずはサンコウチョウを確認してからと思い、子供たちには、「今からはおしゃべりしてはいけないよ」と、さらに厳しい要求をした。それでもみんな言うことを聞いてくれた。20分は林の中で佇んでいただろうか。ウグイス、キビタキ、センダイムシクイ、メジロがそれぞれの美しい声で囀っている。私といえば、切れ目なく聞こえる野鳥の声の中から、本命のサンコウチョウの声を探していた。名前の由来になった月日星の節回しの前に聞かれるヴェとかヴャとの一声を待っていた。けれどもどうしてもその一声を聞き分けることが出来なかった。時間も経ってしまい已む無く引き返すことに。林から出て休憩タイムとした。少しのお菓子を分け合う。そんな時である、林からその一声が聞こえたのは。私は「今、サンコウチョウが鳴いた!」と叫んでしまった。みんなの顔に一瞬緊張が走り、声を聞いてやろうという顔に変わった。完全な節回しではなかったが、他の鳥とは明らかに違うホイホイホイの節が聞かれ皆納得したようだ。小雨の中傘を差して歩きやってきた子どもたちの労をねぎらってくれているかのようだ(そう思いたい)。帰り道で2羽目のサンコウチョウの声を聞いた。こちらの方も実にしっかりと聞くことが出来、一同大満足であった。さらに、観音山からホトトギスの声。まさに、目に青葉、夏ホトトギスであった。
観音山探鳥会参加メンバー 用意したカメラを持って行くのを忘れてしまい、萩小学校に帰ってから撮りました
2009 6 8 富士山新五合目
東名を東に向かっている時は日が出ていたので、もしかしたら富士山が姿を現してくれるのかなと期待していた。しかし、富士山はやはり高い山であった。脇の山の山頂付近に雲が位置する日には富士山はすっぽり雲の中。富士吉田市街から富士の方向には雲が見えるだけ。登山道路に大きく雪を頂いた富士の写真が掲げてあるが、残念な気持ちを増進させるだけである。野鳥観察には関係ないと気を取り直して、何時ものように、西臼塚駐車場(1240m)、高鉢駐車場1600m)、七曲駐車場(1900m)、新五合目駐車場(2400m)の順にバードウォッチングする。夏の富士山になくてはならない小鳥といえばメボソムシクイ、ルリビタキ、コルリが挙げられる。これらの鳥は標高が高くないと見られない。(緯度が高くなれば徐々に標高は低くなるが)さらに、ウグイス、ミソサザイ、ゴジュウカラ、ヒガラ、変わったところではエゾムシクイがある。要するに、山ろくの原生林は多くの野鳥を養ってゆけるバイオマスが有るということ。これだけの野鳥がいる富士山はやはり凄い!。托卵性の鳥カッコウ、ツツドリ、ジュウイチ、ホトトギスすべていた。標高が上がるにつれてルリビタキの囀りが目立つようになったのが特に心に残る。新五合目は完全に雲の中で寒かった。ここよりも標高の高い所はアルプスと呼ばれる3つの山脈のみ。それとて富士山の肩まで、頭1つ突き抜けている富士山なのである。
①西臼塚駐車場 ②晴れていればこのように ③今日はこれ ④高鉢駐車場遊歩道にて ⑤同、笹にはあちこち細かなクモの糸が ⑥同、ニリンソウ ⑦同、ブナなどの緑が凄い ⑧同、富士山は全身溶岩の山 ⑨高鉢駐車場 ヒガラもここで撮った ⑩新五合目の厳しい自然 ⑪ボケているのは雲の中だから ⑫⑬⑭コガラが近寄ってきた
2009 6 9 茶臼山ラインセンサス
茶臼山に到着したらカッコウが出迎えてくれた。高原らしい鳥のナンバー1と私は思う。托卵鳥の仲間は鳴き声がユニークだ。カッコウ・ホトトギス・ツツドリ・ジュウイチなどがその仲間である。姿を見ただけではどれがどれか私にはよく分からないが、鳴き声を聞けば直に名前を言える。多分誰にとっても分かり易い声だと思う。4羽の中でもカッコウとホトトギスがよく知られている。ツツドリとジュウイチはマイナーだ。今日はメジャーが頑張っていた。共通しているのは声の大きさ。なぜこれほどの大声でなければならないのか?と思う程だ。カッコウやホトトギスが鳴き始めるとウグイスがそれに呼応して鳴き出すのを観察できる。被托卵鳥のウグイスにとってホトトギスの声は空襲警報か雷のように聞こえるだろうか。無意味な行動はないと思はれるので、大声が進化してきた理由があるのであろう。開けた牧場のような所では、カッコウやホトトギスが梢に止ったり鳴きながら飛ぶ姿をよく見られる。飛翔姿は小型のハヤブサのようにも見え、声の大きさとともに被托卵鳥をパニックに陥れる効果があるのかもしれない。運よく、両者の姿も声も堪能することができた。夏鳥の様子、コルリの囀りが多かった反面、コマドリ、アカハラの声はまったく聞かれなかった。マミジロの真っ黒な姿を見られたのはまさに幸運と言ってよい。平日にも関わらずリフトはフル回転。萩太郎山の山頂に広がるシバザクラを観に来た人たちだ。お客さんが大勢来るのはよいが、野鳥たちにとっては迷惑なことであろう。
茶臼山と花
茶臼山の野鳥
①イワツバメの巣 ②-⑤エナガの幼鳥 ⑥-⑧ホオアカ(肉眼ではホオジロかと思った) ⑨-⑫ホオジロ ⑬-⑮ホトトギス ⑯カケス ⑰-⑲カッコウ
2009 6 10 室林道ラインセンサス
一日の昼間の長さがもっとも長い季節に入ってきた。昼間に活動する種が圧倒的に多い鳥類はこのタイミングに子育てを合わせているのだろうか。ヒナの旺盛な食欲を満たすためには、対象となる昆虫やクモなどが豊富であるばかりでなく、昼間が出来るだけ長い方が有利であろう。夜行性の哺乳類の中には秋から冬に繁殖するものが多いことは、採餌時間の長さが問題になることを物語っているのではないだろうか。室林道はそんな野鳥たちの活発な様子を見せてくれた。林道をセンサスしていたら1匹のガ。道路にはらりと下りたのを見つけた。それ自体は珍しくもない。まして、くすんだ色のガとあっては。ところが今回は鳥が絡んでいたのだ。ガが道路に下りたのをみたヒヨドリが襲いかかった。ところが数メートルの近さに私がいるのを見て襲うのをためらった。それどもご馳走をそのままにするのは残念と思ったのか、もう少しで捉えそうな所までやって来た。しかし、身の危険を感じるほうが大きかったのだろう。とうとう諦めて飛び去った。ガ君は命拾いをしてこれも飛び去った。またこんな光景も見た。シジュウカラが2・3羽鳴きながらやって来た。先頭はオスの成鳥であることはお腹の縦線の形で分かる。しっかりとした声で鳴きながら後から来る鳥を見守っている。続く鳥の線は途中で無くなっている。すなわち幼鳥である。幼鳥は枝を回って食べ物を探しながら親に付いていたのだ。萩小の6年生が去年の卒業前にオオルリの巣箱を作ったことは以前にも紹介した。室林道にはその12個の巣箱が異彩を放っている。センサスでは営巣を確認するのも大きな楽しみだ。5月4日、山口さんと室林道で12個の巣箱の1つに営巣しているのを確認した。そのときの驚きは。まさか本当に巣箱にオオルリが営巣するとは。残念ながらその巣は育雛まで至らなかった。何者かに持ち去られたのだ(人間でない可能性も含め)。ところが2件目の営巣が見つかったのだ。コケでお椀状に作られていた巣の中には卵は未だ無かったが、巣箱の優秀さを示すのには十分であろう。
①②オオルリの巣 ③室林道にはこのような看板が立っている ④野イチゴ(子どもの頃よく食べたものだ) ⑤ドクダミの花 ともに梅雨の季節にお馴染み
⑥肉眼では?カメラの目は鋭い ⑦ヤシャブシの球果新旧交代(マヒワなどの大切な食料となる) ⑧花?が胸元を飾るリボンのようだ
2009 6 13 室林道ラインセンサス
ヒヨドリが活発であった。いつも賑やかな鳥のイメージがあり、その通りであるが、季節によっては静かなときもある(そうそう脳天気でもない)。今はハイテンションの時期。つがいの2羽が鳴きながら木々を移動する、子どもが親に餌をねだる、オスがごろごろと喉を鳴らす、などなど実に賑やかなのだ。夏になると姿を消すカケス。今年はお馴染みのだみ声を聞かせてくれている。心なしか元気がないように感じるのは気のせいか。もっとも、ヒヨドリのように鳴かれては一層暑苦しくなってしまう。歩いていたら良い香りが広がっていた。匂いのもとを探したら垂れ下がった枝に絡みついた蔓に咲く白い花からであった。調べてみるとテイカカズラとあった。丁の形の花びらからきているのだろか。ほのかな香りが気に入ってしまった。
①ムラサキシキブに来たハナバチ ②③小さな昆虫 ④⑤ヒノキの若木を移動するウグイス
2009 6 20 寺ノ入林道ラインセンサス
梅雨の晴れ間を見て寺ノ入林道を訪れた。寺ノ入林道で見る草花で印象深いものを挙げよと言われたら、初夏のササユリと秋のキキョウの名前を迷わず出すに違いない。ササユリの楚々とした淡いピンクの花が、緑溢れる中でポツンと佇んでいるのを見ると、日本の自然は本当に素晴らしいなと心から思う。子どもの頃に皆と一緒に近くの山でササユリを摘んだ記憶がある。子ども心にもササユリの美しさは分かるような気がした。もっとも、花より団子の喩えで、ヤマモモやグミの甘酸っぱい実を口いっぱいに頬張ることが本当の目的であったが。まだ開いて間もないのであろう(蕾のものもある)。花弁の色はピンクが勝っていて瑞々しかった。鳥の声を聞きながら寺ノ入林道を歩いてゆくと、あちこちからキビタキの囀りが。かなりの個体数と見た。その中で、警戒音を出している個体を発見。最初に見つけたのはオスであったが、直近くにもう一羽いるのを確認。どうやらメスのようだ。密集した林の中の出来事なので姿を見失いがちになるものの、メスが近くに止ったのをカメラに捉えることが出来た。虫を咥えておりヒナに運ぶ様子。けれども、いきなり巣に向かわずに警戒していたのだと思う。寺ノ入林道で唯一視界が開ける場所では、ホオジロとオオルリが向かい合ったアカマツの天辺で囀り合戦を繰りひろげていた。もっとも、相手のオスは異種であり競争する必要はないので、たまたま近くで鳴いているだけなのだろう。ウグイスよりもオオルリの囀りの方が活発であった。数は少ないが、サンショウクイは相変わらず寺ノ入林道の名物鳥であるし、ここが標高600メートルを超える場所であることを実感させてくれるのは、ミソサザイとキクイタダキの小さいもの鳥である(日本産野鳥の1位と2位)。雲が切れ日が差してきた。どこからともなくノスリの声がした。
寺ノ入林道の女王 ササユリ
寺ノ入林道の野鳥たち
①ホオジロの囀り ②オオルリの囀り ③キビタキのオス ④⑤キビタキのメス ⑥キビタキのメス ⑦キビタキの幼鳥
2009 6 27 室林道ラインセンサス
室林道に向かう道端にカンナの黄色い花が咲いていた。綺麗な花なのに何故かほったらかしにされている事が多いように感じる。それだけ逞しい花でもある。室林道の入り口に到着した途端、サンコウチョウの囀りが聞こえてきた。林が成長し暗い繁みができると、サンコウチョウやキビタキなどの薄暗い所を好む鳥が増えてくる。事実、両者とも室林道では個体数を増やしていると思う。何とか姿を確認したかったが残念であった。今日気になったのはクロツグミの囀りとヤブサメの地鳴きである。クロツグミは室林道では今年初めて聞いた。明るい調子の歌は何時聞いても心地良いものである。ヤブサメの地鳴き個体が増えてきた。囀りが減ってきたとも言える。繁殖のピークが過ぎたのであろうか。不思議なことに囀り個体の同定は極めて難しいのに対して、地鳴き個体の居場所を見つけるのは易しいのである。囀りは救急車の音に似ていて、どちらから聞こえるのか最初は戸惑ってしまうのである。その点地鳴きは音の発進箇所を同定しやすい。今日聞いた地鳴きの個体は繁みの中をちょこちょこ歩き回っていた。ちょうど冬に見かけるミソサザイのような小さな姿である。枯れ枝に似せた茶色の姿は見事な保護色となっている。近くからニホンザルの声がした。ヤマモモの実が熟す時期でもある。彼らにとってはご馳走であろう。昔は子どもたちが徒党を組んで野山を駆け巡った。ヤマモモの実は彼らのおやつであったのだが。
ラインセンサスで出合った光景
①森の中 ②室林道から望む ③室林道の山 ④⑤⑥サンコウチョウ(メス) ヒヨドリみたいですが茶色が強い ⑦-⑩ヤブサメ(小さな鳥です) ⑪⑫⑬アカマツの葉を巡るエナガの幼鳥 ⑭ソングポストで囀るホオジロのオス ⑮-⑳地上に下り虫を捕らえたキビタキの幼鳥
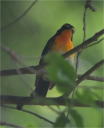 |
 |
 |
 |
 |
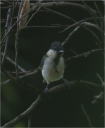 |
 |
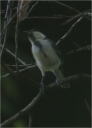 |
 |
 |
 |
2009 7 4 我家周辺
田んぼの上をツバメが滑空する。電線に止っている2羽のツバメの後姿は仲のよい夫婦のようだ。望遠で飛んでいるツバメを撮影するのは中々難しいものだ。逆光でよい雰囲気の景色をバックに数カット撮った。山陰川沿いに歩いた。カンナやキンギョソウが鮮やかに咲いている。昔ながらの花ではあるが綺麗なものはいつまでも褪せないものだ。民家の軒先からツバメが飛び出してきた。きっと大切に巣を守っているのであろう。20羽を越すツバメが電線に整列している。いずれも若鳥たちで巣立ちした時期もさまざまのようである。羽つくろいに余念がなく、あくびをしている個体も。夕方からは土曜探鳥会。もうひと頑張りしなければ。
梅雨の晴れ間、我家周辺の風景とツバメたち
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2009 7 4 龍源禅寺 夜の探鳥会
「今度の探鳥会は大勢集まりましたよ」と先生から電話が入った。夕日が残る萩小学校の校庭に集まった子どもたちの人数を見て驚いてしまった。去年の探鳥会メンバーも参加してくれた。彼らの幼さと青年の同居した顔を見て懐かしく思った。大人数を思い図って、忙しい体の先生方がサポートに駆けつけてくださった。本当に有難うございます。明るさの残る空にツバメが舞う。一番遅くまで働いているのはいつもツバメである。探鳥会でお馴染みの室林道へ向かう道を進む。学校から300メートルほど歩いた所でウグイスの囀りを聞く。あと暫く、お盆が終る頃まではウグイスの歌を聞かれるだろう。盆が過ぎたら来年の早春までお預けだ。昔ミカン畑だった箇所からはモズの声だ。龍源禅寺までの道のりをゆっくり進んだ。もう少し暗くなってから境内に進もうと、途中で休憩することにした。子どもたちは田んぼの中にいる虫を見つけ騒いでいる。話をしない約束をしていよいよ境内に入る。境内ではヒキガエルが鎮座していた。まるで我々を待っていたかのようだ。黒門をくぐって境内へ。探鳥会でムササビを待つ場所が決まっていて、みんなで出現をひたすら待つ。ムササビは数年前に見たきり。しかし、現われる可能性がゼロで無い限り探鳥会で見に行こうと思う。子どもたちは一言も発しないで待った。そんな気持ちが通じたのか闇の中から聞こえてきた。ホッ、ホッ、ホッ、思わず「今、アオバズクが鳴いたよ」と言ってしまった。帰り道にも楽しみが残っていた。みんな思い思いにお喋りを楽しんだ。
伝統の夜の探鳥会 今年は大勢の子どもたちが参加してくれた
2009 7 11 乙女川
以前から行こうと思っていたのに果たせなかった。その気になればすぐ来れる近さが返って仇になった。乙女川の水の流れは男川→乙川→矢作川と繋がる。水かさの多さははさすがに梅雨時のことはある。晴れ間も広がって川全体が輝いている。泡立つ瀬は乙女のレース飾りのようだ。清流にしか棲まないカジカガエルの歌が聞こえた。その美しい声に耳を澄ませていたら、突然に、あまり耳に心地良いとはいえない声がする。どちらかと言えば耳障りである。しかし、私には驚きと喜びの声であった。間違いなくカワガラスのものに違いないからだ。声の方向に顔を向けたら、特徴のあるこげ茶色の鳥が川面から飛立ち、目の前を川の上流に向かって一直線に飛び去って行くのが見えた。本当に吃驚した。まさか乙女川で再びカワガラスに出会えるとは夢にも思っていなかったから。カワガラスは普通の鳥なのに水中で採餌する一風変わった習性を持つ。巣の場所も変わっていて堰の空洞に作る。巣に入るには滝をくぐらないといけないので外敵から襲われる心配がないというわけだ。乙女川を上流に向かい少し歩いてみた。水田も少しあるが殆ど林の中をくねって流れる。だから流れが綺麗なのだ。川底は固い岩盤が倒木のように横切っていて瀬や淵を造り川幅以上に迫力を感じさせ、乙女川よりも強い女の川の方が似合う。ウグイスやヒヨドリの声がする。明るい林からはサンショウクイの声もあった。土手には小さな花々が咲いている。ネジバナのピンクの小花はなんとも愛らしい。普段雑草にしかみられないムラサキカタバミもここでは乙女のような雰囲気を持つ。電線にヒヨドリが止っていた。と思った。ところが様子が変だ。飛んでゆく姿がヒヨドリのものでは無かった。双眼鏡で見るとやはり違っていた。メスか子どもの鳥か判断に迷ったが、まさにイソヒヨドリであった。地上に下りる仕草も見せたがやがてスギ林のなかへと姿を消した。つくづく思う。自然観察は現地に行かないと始まらない。たとえ確率は低くともゼロではないと思って行くべきだと。
①-④雨山地区で見たイソヒヨドリ ⑤ー⑯乙女川の清流と草花 ⑪大雨河小学校(大代・雨山・河原地区からこの名になった?)
2009 7 18 羽根・長根の田んぼ
梅雨明けも間近、晴れていたらさぞかし暑いだろうと心配していた。起きてみたら厚く雲が立ち込め道路も濡れており雨が心配な空模様である。けれども小学校に着く頃には白い雲に覆われ心配なくなった。既に2人の大きい子が待っていて挨拶を交わす。さらに4人の子が集まり羽根・長根の田んぼへと向かう。校庭にいた時、少し丸っこいサギが飛んで行くのが見られた。ゴイサギである。アマサギを見たいと思う。羽根・長根で何度も見てきたアマサギが姿を消して久しい。下賀茂神社付近でウグイスが鳴いた。田んぼの水路ではドジョウもいた。山陰川を渡ると羽根・長根の田んぼに入る。既に、セッカの囀りがあちこちから聞こえる。やはり羽根・長根はセッカだ。アオサギの姿は見たがアマサギはおろか他のサギもいなかった。けれども、セッカの元気な様子が子どもたちの瞳に映ってくれたのではと思う。徐々に薄日が差すようになり、それとともに蒸暑くなってきた。そういえば風がほとんどない。長根川のたもとで一休みしながらおやつを食べる。親子と思われる2羽のハシボソガラスが直ぐ近くの電柱にとまっていた。日頃はあまり可愛いとは思えないカラスではあるが、親子でいる姿はやはり微笑ましい。
探鳥会光景
2009 7 19 茶臼山ラインセンサス
茶臼山の山頂は雲の流れが急で、日差しが出たと思えばパラパラと雨粒が落ちてくるといった、ネコの目のような天気であった。幸いにしてセンサスの最中は本降りにはならなかった。もし降ったらカメラを守らないといけない(双眼鏡は防水タイプ)。ペットボトルを包んだビニル袋が役に立つ。萩太郎山からカッコウ、茶臼山からホトトギスの声が聞こえる。カッコウは茶臼山のシンボルだ。夏の高原らしい鳥のもうひとつにアカハラ・マミジロがいる。よく似た鳴き声であるが姿は全く異なる。所が、これらの鳥の声がほとんど聞かれなくなってしまった。何度も言っているように、コマドリは茶臼山からはいなくなってしまった。これらの状況は危機的であると思う。ウグイスやホオジロといった一般的な鳥の声が聞かれるばかりだ。台頭する鳥もいる。ソウシチョウである。なにも茶臼山に限ったことではない。私が回った1000メート以上の高原にはソウシチョウのいない所は無かった。間違いなく、ウグイスとホオジロはともに、今、茶臼山で最も活発に囀っている鳥だ。
①茶臼山と矢筈池 ②③④⑤ラインセンサスのコースで見た草花など ⑥⑦牧場は緑滴る ⑧突然ヤマカガシが現る ⑨ウグイスと共に多かったホオジロ
⑩-⑭モズがヒナに餌を運ぶ姿(尾羽を回して警戒) ⑮電線で囀るウグイスのオス(尾羽をピンと上げている)
2009 7 25 前田町
室林道から高速道路を飛ばし(制限速度以下)豊田市前田町に向かった。1000円の恩恵も無く唯混みあうだけ。案の定、往路は岡崎で渋滞にはまりハザードを使い、復路は渋滞表示に怖じ気付いて一般道をのんびり帰った。前田町でコヨシキリを確認!これには驚いた。通勤途中では撮影も録音も駄目だ。そこで、休みになったら飛んでゆこうと思った次第。ところが、思うとおりに行かないのが世の習い。コヨシキリはおろか、オオヨシキリの声も全く聞くことはなかった。残念、でも高速代を使って来たのだから一回りして帰ろう。気を取り直して双眼鏡を取り出す。不思議なくらいにオオヨシキリの姿が見つからなかった。トウモロコシ畑で風に揺れる穂にしがみ付くスズメとカワラヒワの群。50羽以上はいたであろう。田んぼを見ると白いサギが3羽首だけ見えていた。ダイサギだ。ケリが畦を歩いている。さすがのケリも少し大人しくなったみたいだ。さらに歩いてゆくと緑一色のあぜ道に黒色の鳥がいた。さらに目立つ真っ赤な嘴。バンに間違いない。警戒心の強い鳥で直に稲の陰に隠れてしまった。オスのこの色は確かに目立つ。きっと、メスへのアピール色になっているのであろう。
①前田町大切な水路 ②鮮やかなオレンジコスモス ③トウモロコシに群れるスズメ ④⑤田んぼにいるバン ⑥ハクセキレイの幼鳥 ⑦鉄塔にとまるアオサギ
2009 8 1 室林道早朝探鳥会
100パーセント雨が降るだろうと予想していたけれどもどうやら何とかできそうだ。しかし油断はできない、黒い雲が次から次へとやって来る。萩小には5時30分過ぎに到着。すでに先生が来ていた。集まったのは2組の兄弟と4人の大人計8人。保育園の年中さんもいて可愛らしいメンバーたちだ。校庭ではハクセキレイやツバメたちを観察する。巣立ちしたツバメの子どもが電線に並んでとまっている。室の民家を抜けて一路室林道へと向かう。ヒヨドリ、キジバト、イカルたちに出会えた。途中、苦しそうなカエルの声が聞こえた。ヘビに呑み込まれていた。ショッキングではあるがこれが真実の姿なのだ。室林道が近づくとウグイスの鳴き声が増えてくる。朝の静かな時間に聞く歌声、贅沢な気がする。曇ってるお陰で汗をかくこともなく、ほどなく室林道の入り口に到着。ここではサンコウチョウの出現を期待していたのであるが、残念ながら願いは叶えられなかった。室林道は霧が立ち込め、さらに、ゆるい風の後押しもあって大変気持ちいい。ウグイスやメジロの鳴き声がする中で用意したお菓子を食べる。まあ何と贅沢なことか! 恒例の記念写真を撮っていたまさにその時、至近距離にいたホトトギスが鳴き声を上げた。その声の大きなこと。最後にビッグなプレゼントが用意してされていたのだった。だれがこんなこと予測できようか。だからこそ自然観察は面白いのだ。少しばかりパラパラ雨が落ち用意した傘を開いたものの、直に薄日まで差す良い天気となり、帰り道を愉快な気分で学校に向かった。先生たちとも別れ帰途に着こうとし途端、我慢しきれなくなった空から大きな雨粒が落ち始めやがて土砂降りとなった。
探鳥会光景
萩小学校を出発、室の民家を抜け室林道へ。畑には、夏の草花や野菜・スイカが。
2009 8 8 室林道ラインセンサス
梅雨明けの真夏の空が室林道に広がっていた。遠く三河湾には積雲の列が連なり、いかにも夏の空といった感じである。そろそろ室林道での関心は、ウグイスの最後の囀りが何時かということ。お盆を過ぎると不思議なくらい囀らなくなる。ササの中からウグイスの地鳴きが聞こえた。声の近くのササが揺れているのはウグイスがいる証拠。動きを追えば姿を見せる瞬間があるはず、カメラのピントをササにあわせウグイスの出現を待つ。囀り個体数は随分と減っているので平年並まで持たせることが出来るか、少し心配になる。野鳥たちはこれから換羽に入る。体力温存で鳴き声も無駄にはあげない。だから室林道はセミの声が独占する。すでにすべての種が鳴いている。定番のアブラゼミとヒグラシ、最近増加したクマゼミ、そしてツクツクボウシ。ツクツクボウシはもっと遅くから鳴きだしていたように思ったが。サンショウクイの地鳴きがした。この鳥は音羽でも増えている。室林道の半分は木々のアーチで日差しを遮られ、夏のセンサスを随分と快適にしている。室林道に足繁く通う要因ともなっているはず。
①ササの中で鳴くウグイス ②③コスモスが早くも咲き出した ④ヒマワリ畑 ⑤-⑪田んぼで群れるスズメ ⑫⑬モズの若鳥 ⑭-⑲ヒマワリの種を啄ばむカワラヒワ
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2009 8 11 茶臼山ラインセンサス
朝、起きしなに地震を感じた。家はなんともないので一安心する。その後の状況はテレビやラジオで放送されたとおりである。茶臼山はどうであろうか?。道路は?。いつもより緊張した気持ちで向かったのは言うまでもない。家を出たときには一面雲に覆われていた。どんどん雲の切れ間が広がって、茶臼山に着いたときには夏とは思えないほど爽やかな風が吹き渡り、周りの山々が克明に見渡すことができた。雄大な南アルプスの連なりは雲の上に頭を出している。愛知県側では名古屋のビル群がはっきりと見て取れる。高層ビルや名港トリトンは巨大なため肉眼で存在を確認できるほどである。鳥はというと、ウグイス、ホオジロの囀り個体が非常に多かった。特に、ホオジロが至る所で囀りをしているのに出くわした。ウグイスと違い姿が見られるのが凄くいい。名古屋市街地までどのくらいあるだろうか?。秋冬でもなかなか見ることができない。ワクワクしながら周回路を進む。そして、奥三河の山々のさらに奥に街がごちゃごちゃと見えた時は、思わず指を鳴らした。長野県側に出ると山が主役である。恵那山は雲の中から出てくれなかったが、蛇峠・大川入はすっきり。さらに進むと、3000メートル峰の連なりが堪能できる。途中に雲がかかりその高さが一層際立つしくみだ。茶臼湖ではテントが張ってあった。子供たちの楽しい声と美味そうな匂いが漂って来そうだ。いよいよ晴れ間が広がり木陰が恋しくなった。遊歩道に入るとそこは別天地、涼しくて静かだ。少数派ではあるが楽しみな鳥も多い。アカハラ、コガラ、ヒガラは高原ならではの野鳥だ。帰化種のソウシチョウはもうどこにでもいる。4時間のセンサスを終えたら汗だくになった。
茶臼山ラインセンサス中の光景 鳥・鼻・自然・街
センサスの路傍で見たもの
①ネヂバナ ②ダンプ ③シシウド ④株立ちのネヂバナ ⑤黄色一色 ⑥森の中の小川 ⑦トンボ(不明)
野鳥
①②エナガ幼鳥 ③ハシブトガラス ④-⑥ホオジロ ⑦-⑨キセキレイ ⑩ノスリ ⑪カワラヒワ(上)とウグイス
茶臼山から望む名古屋市街
南アルプス
荒川岳から南アルプス最深部までの大パノラマ
南アルプス
①頭だけの塩見岳 ②聖岳と兎岳 ③荒川岳 ④間ノ岳と農鳥岳 ⑤荒川岳 ⑥兎岳
お馴染みの山々
①伊吹山 ②③大川入山 ④蛇峠山
2009 8 15 土曜探鳥会 羽根・長根の田んぼ
お盆の最中なので参加者があるだろうか?少々心配しながら萩小学校へ向かった。校庭の雑草が夏休み中だなと思わせる。一箇所だけ綺麗に刈ってあり迷路のように見える。パートナーは可愛らしい1年生。彼は、野鳥が大好きである。そして、よく知っている。あとはフィールドで実践すれば鬼に金棒というものだ。山陰川でカワセミの鳴き声を聞いた。民家を出ると田んぼ道。ツバメが飛び回っている。ヒナのために休みなく餌とる姿をみると本当に感心する。田んぼはだいぶ色付いてきた。水路をのぞくと小さな魚が一杯行き来している。オタマジャクシも増えたし、少しずつ生態系が回復しているように思う。羽根・長根の田んぼの入り口に山陰川の支流である室川(源は室林道)が流れていて、そこで、今日2羽目のカワセミを見た。その子は、観察記録に、青いうしろ姿と書いた。まだカタカナを習っていないので鳥の名前はすべてひらがなである。羽根・長根の田んぼではセッカが鳴きながら円を描いている。そして、ついに彼が鳥を見つけた。田んぼから顔をだしたキジである。つごう4・5羽の子どものキジだ。目には見えないが、田んぼの中は野鳥たちの生活圏があるのだ。2人で記念写真を撮り、帰りも鳥の話をして学校へと向かった。
1年生の鳥のことを凄く勉強している彼と探鳥会
①ヒマワリ畑 ②記録を取る彼 ③この室川でカワセミを見ました ④羽根の田んぼに棲むきじの子ども(4・5羽いました) ⑤記念写真 ⑥こま犬の前にて
2009 8 22 羽根・長根ラインセンサス
8月に入って暑さが戻り、稲穂も頭をおおきく垂れている羽根・長根の田んぼ道をセンサスした。セッカの囀りが頭上から聞こえる。50メートル四方くらいをなわばりに治めているオスが油断なく見回っているのだ。サギが見えた。そして驚いた。ここ数年姿を見ることがなかった、夏鳥のサギ、アマサギがいたのだ。それもたった1羽だけ。何故今の時期に?夏鳥の例にもれず南下中の個体だろうか?。原因はともあれ、アマサギの象徴である亜麻色の羽色を見たのはたいへん嬉しかった。音羽での個体数減少の理由は思いつかない。室林道でのセンサスを終えそのままやって来た。アマサギのことは少しだけ頭にあった。しかし、ほとんど見ることは無いだろうと思っていたので、驚きは半端ではなかった。コンパクトカメラしか持ってこなかったので、とりあえずはその姿を撮ったがやはり物足りない。久しぶりの姿だ。きちんと撮ってやりたいと思い、家の戻ると、フジのボディにニッコールの500ミリを装着し、昼ごはんもそこそこにして羽根に向かった。まだいるだろうか?顔を見るまでは安心できなかった。アマサギは同じ所に留まっていた。気持ち良さそうに梢の天辺にとまっていた。
久日ぶりにアマサギが飛来(南下中の個体か?)
①コンパクトカメラで撮影 ②-⑭アマサギ飛翔の連続撮影 ⑮室林道の山を見る ⑯-⑱小さな花々(カタバミ・ツユクサ・マルバルオウ)
①茶臼山への道、真夜中の太和金トンネル ②③④夜明け前、パープル色に染まる(聖岳) ⑤荘厳な日の出
2009 8 29 高嶺
雲の中に入っているかもしれない。茶臼山から向かう時はそう思った。阿知村からの高嶺の山頂は、遮るものが何も無いのを見てまずはホッとする。高嶺ではオオルリを見た。数羽で梢から梢へとじゃれあうように移動している。メスのようにも見えたが、撮ったのをみると、半成り(オスの若鳥で羽だけ青い)の個体もいたことが分かった。山頂でもオオルリがいたし、囀り個体までも確認できたことは収穫であった。遊歩道を少しだけ歩く。平谷の街が眼下に見える。ツリガネソウ、ミヤマオダマキ、ヤマハハコが可憐な花を咲かせている。次は何処に向かおうか。あららぎ高原か蛇峠山か。結局、アララギスキー場に行くことにした。4月の終わりに初めて行った時の印象がとても良かったから。ところが、ゲレンデには膝の高さまで夏草が生い茂る有様で、とても先には進めそうになかった。(残念)帰りは一寸した冒険を味わった。蛇峠山を西に見て阿南町に抜ける県道を通ったところ、これがなかなかの絶景で、深い谷にへばりつく昔ながらの狭い道であった。そんな所にも(失礼な言い方である)部落があり、学校を2つ見た。川の澄み様は半端ではない。宝石のアクアマリの色であった。いくら景勝地でも山奥の道は緊張する。正直に言って、新野の町に出たときは心の底からほっとした。
①阿智から見る高嶺の山容 ②入り口で見たオオルリ(半成り) ③山頂で見たオオルリ ④ツリガネソウとヤマハハコ ⑤山頂にある小屋と奥に蛇峠山
遊歩道を歩く ⑥ヤマハハコ ⑦ミヤマオダマキ ⑧ススキの穂
⑨ひるがの高原スキー場 一面の草で前進を阻まれた ⑨帰り道、深い谷の細い道を行く
2009 9 5 探鳥会 室林道
9月に入ったのに一番暑い探鳥会となった。子ども6名、大人3名と鳥を見るには程よい参加となった。校庭の前の大きな樹からはイカルの声がする。電線にセグロセキレイがいて大きな声で鳴きあっていた。セグロセキレイのこうした行動は、秋の始まりとともによく見られるようになる。そして、夏にいるのも珍しくなくなったハクセキレイが、澄んだ声で校庭に降り立ち餌を啄ばみ始めた。参加した子どもたちはみんな虫が大好きで、平気で虫をつかみ、そして名前を言い当てている。室の民家では特にモズの姿が目立った。1人の子が「秋の鳥の代表はなに?}と私に聞いてきた。私はすぐに「モズ」と答えた。事実そう思ったからだ。モズは留鳥なのでいつでも見られるが、やはり秋に一番似合う鳥だと思う。室林道への登りにはいると速度はさすがに鈍ってきた。それでも子どもたちはお喋りや虫などをつかんで楽しみながら歩いた。湧き水で顔を洗うと「気持ちいいー」の言葉を連発した。「前の室林道の探鳥会では17種類いたけど、今日は18種類見たいナー」と言う。前向きな言葉が素敵であった。大人たちに聞かせたいくらいだ。室林道は日が高くなっても涼しかった。ここで昼寝をしたらどんなに気持ちがいいだろう。探鳥会の先輩が萩の名水と名づけた湧き水に案内する。みんなで火照った手や顔を湧き水で洗った。帰り道にプレゼントがあった。2羽のノスリが寄り添うように室林道の上空を飛翔していたのだった。室林道からの下り道は楽ではあったが、反面、暑さは増してきた。
探鳥会光景
2009 9 6 室林道ラインセンサス
ツクツクボウシが懸命に鳴く。昨日の土曜探鳥会でノスリのペアらしき姿を見たので(サイズが似ていたので同性同士かもしれない)、今日も上空には要注意を意識した。最初に現われたのはエナガの群。見える範囲では成鳥ばかりであった。エナガがやってくると、静かであったところが急に活気付く。釣られてシジュウカラやヤマガラたちも鳴き出す。一瞬ノスリが見える。今日も見られるみたいだ。空が広く開けた室林道では唯一の場所で暫く待つ。1分も経たなかったであろう。2羽のノスリが山の端から舞い上がる。サイズもはっきり違うのでオス・メスのペアであろう。暫くその2羽を注視していたらもう1羽いることが確認された。3羽もいた。喜んでいると、あれあれ4羽になってしまった。2ペアーか?これで終了かと思っていたらいつの間にか5羽になっていた。豪華なタカのショーは1分も続かなかった。再びセンサスを開始する。オオルリの営巣ヶ所を10メートルほど過ぎたところで、30メートル先で鳥が動いているのが見えた。サクラの樹の主を双眼鏡で見ると、朝日に輝く濃いオレンジ色の姿、カワセミのような長い嘴、アカショウビンに違いなかった。(この鳥を見間違えるなんてあり得ないことだ)一度は見てみたかった。キョロロロロロロロと鳴く声は何度も聞いている。音羽でも聞く機会は何度もあった。しかし、姿は今度が始めてである。気配を感じたのかあっという間に飛び去ってしまった。これは興奮ものである。もう少しジッとしてくれていたらカメラに収められたのに残念だ。しかし、見られただけでも大満足。それと同時に自然観察は何が起こるのか予測がつかないことも勉強した。
①②室林道のエナガ ③-⑥室林道のノスリ(この日は5羽いた) ⑦-⑨我家近くで見たモズ ⑩黄色コスモス(よく見るようになった)
2009 9 13 寺ノ入林道ラインセンサス
昨日の雨が汚れを洗い流してくれた。寺ノ入林道の空もすっきり澄んで気持ちがよい。上空は強い風があり雲の流れも速い。アオゲラの力強い声がした。続いてヒヨドリたち。上空に下弦間近の月がかかっていて、雲に隠れたり現われたりしている。しばらく顔を上げていたら視界を高速で横切るものがいる。あのスピードで飛ぶのはあれしかいない。アマツバメである。昨日は雨雲の立ち込めた萩の空を10羽以上で餌を捕っていた。2日連続で見られるとは嬉しい限り。私の一番好きな鳥でもあるからだ。その魅力はツバメが遅く見えるほどの飛翔力。暫く美しい弧を眺めていたら、さらに上空を集団が通過しているではないか。姿から、イワツバメの群であることが分かる。東から西へと一直線に進んでゆく。どうしてもこれは南下個体と思いたくなる。地上ではヒガラの囀り個体が目立つ。美しいヒガラの声を聞き大満足である。野菊が私は大好きである。寺ノ入林道にも一杯咲いている。しかし、秋本番はもう少し先である。
雨上がりの寺ノ入林道 爽快であった
①-④ポッカリと浮かぶ雲、しかし、意外と流れは速い ⑤-⑩ノスリの飛翔 青空に映える
2009 9 19 羽根・長根の田んぼ
始めの挨拶でモズとノビタキを話した。秋になるとモズの声が一層高らかになること、ノビタキは渡り鳥で、今時分になると南に渡る姿を見ることができることなど。朝夕はめっきり涼しくなった。直感ではあるがそろそろノビタキが見られる気がしたのである。モズは萩小を出て間もなく聞くことができた。梢に、竹やぶに、電線に、あちこちで力強いモズの姿と声を確認することができた。刈り取りの終えた田んぼでは、セグロセキレイ、ハクセキレイが採餌していた。参加メンバーの子どもたちは昆虫などが大好きで、バッタやトカゲも平気で手に取る。虫たちには要注意人物なのである。山陰川の橋を渡るといよいよ羽根・長根の田んぼに入る。あぜ道が転々と朱色に染まっているのはヒガンバナ。彼岸も間近、名前どうりの花である。幼い頃に、ヒガンバナは墓場に咲く死人の花と聞かされ、花が咲くと片っ端からちょん切った記憶がある。多くは赤花であるが白花も見られる。校長さんが運動会で紅白のヒガンバナを飾ったことを聞き、粋なことをするもんだと感心した。私の目はヒガンバナと共にノビタキの姿も追っていた。スズメ大の茶色と黄土色がいたらそれがノビタキだ。緑色の畦草ではよく目立つので肉眼でも見つけることが出きる。いや、むしろ肉眼の方が視野が広い分有利である。ノビタキやモズを比べても、鳥の種類で止まったり、飛んだり、羽ばたく姿に特徴がある。ノビタキはツグミ科の鳥らしく頻繁に羽ばたきの動作をするのですぐに分かるのだ。予想通りというか、やれやれというか、幸運にも2羽の姿を確認した。早速フィールドスコープで捉え子どもたちに見てもらう。さらにもう1羽。この個体は農道におりて餌をあさっていた。終点の長根川で子どもたちは靴を脱いで川の中に入ってしまった。最初から入るつもりでいたらしい。気持ち良さそうで羨ましい限りだ。青空にはすじ雲がたなびきすっかり秋の雰囲気を漂わせていた。地上は刈り取りの終えた田んぼとヒガンバナの朱色。ムクドリが群となって電線にとまっていた。
探鳥会光景
 |
 |
①室林道も秋の空 ②室林道のヒガンバナ
2009 9 20 我家周辺
今年、我家の前の田んぼは、ヒマワリとコスモスの花で見事であった。ヒマワリには種がある。種は野鳥たちの好物。熟した種を頂こうとカワラヒワやスズメたちがやってくる。カワラヒワの写真も欲しいなと思っていたので車を停めたところ足元にいたのは、あのノビタキである。そのノビタキはヒマワリ畑にいて右往左往していた。冬にジョウビタキがハゼの実を食べているのを見ているので同じ科のノビタキが種子を食べられないとは思わないが、ヒマワリ畑には似合わないと思った。
①②ヒマワリ畑で採餌するカワラヒワ ③④⑤ヒマワリ畑にいたノビタキ ⑥コスモス
2009 9 26 健康ウォーキングコースラインセンサス
日の出前、爽やかな朝のうちに歩いておこうと、新調したハイキングシューズを履いてコースを歩いた。これから野山などを共にする靴の具合を見たい気持ちもあったからだ。結果は上々。甲高な足にもピッタリあってこれならいくらでも歩けそうだ。スタートしてすぐにカワセミを見た。早朝に賑やかに鳴いている声を聞いていたので、きっとこの個体であろう。復路で再びカワセミを見たが、今度はつがいでいた。仲良く並んで同じような動作をしているのが微笑ましい。何かを呑み込むような動きをしたり、頭を水平にしたりしている。田んぼではキセキレイやセグロセキレイが目に付いた。特にキセキレイが多かった。神社の大きなクスノキには色々な鳥がいる。中でもイカルの群は賑やかだ。囀りをしている個体もいたが多くは地鳴きで、聞きなれないとイカルがいるとは思わないだろう。モズも勿論いた。互いに鳴きあって縄張りを守っているのが、戦国時代の城の構えを思い起こさせる。羽根・長根の田んぼには南下中のノビタキが羽を休めていて個体数も増えた。ヒガンバナやツユクサが咲き、畦を歩くと露に濡れるようになったのは、空の雲の形とともに秋の深まりを実感させてくれる。新品の靴なので今日のところは汚さないように努めた。再びカワセミにもどる。2羽はつがいであった。我家から数十メートルしか離れていない山陰川の川底に仲良く並んでいた。手持ちのカメラは風景を撮るためのコンパクトデジカメで野鳥を撮るのには適さない。しかし、家に取りにいっている間にいなくならないとも限らないと思いこのカメラで撮ることに決めた。まずは画像サイズを1メガ(常にはこのサイズ)を最大の5メガに切り替えた。そして、望遠にズームし、できるだけ近くから撮ることにした。これがなかなか難しく、カワセミはすぐに気が付いて逃げてしまうものなのだ。ところが今日は飛び跳ねても余り遠くには行かないなど、近くに寄っても気が付かない様子なのだ。これもオスとメスが互いに相手のことに注意がいっているからではないだろうか。記録ように撮ったので今度はオームページのお客様のためにカメラを取りに戻った。幸いにして100メートルほど上流の土手の樹の枝の中から声が聞こえた。そして2羽でくつろぐ姿を撮ることができたのだ。
健康ウオーキングコース
①日の出前の観音山 ②リラ ③ヒガンバナ ④カキと秋の空
カワセミのつがい
①②仲良く並ぶ(コンパクトカメラ) ③④⑤オス成鳥 ⑥⑦⑧メス成鳥
2009 10 3 宮路山
朝は厚い雨雲に覆われていて霧雨が車の天井を濡らしていた。しかし、雲の流れる方向は上りなので回復に向かうはず、天気予報を信じて迷わず探鳥会を決行した。赤坂駅が集合場所で先生も来ていた。今日の参加は子ども5人とおとな4人。音羽川に沿って進んだときに、カメラを車に忘れてしまったことに気がつき慌てて取りに行く。やれやれ先が思いやられる。赤坂の杉森八幡社の境内には、18日に行なわれる歌舞伎の準備が始まっていて、観客の席に竹で屋根が作られようとしていた。(小屋がけと言うそうだ)大楠の根元に子供たちが上って暫し遊ぶ。宮路山登山道に入る頃には雲は全く見られない素晴らしい快晴となった。ツクツクボウシがまだ鳴いている。時折、ヤマガラやヒヨドリ、メジロといった宮路山に多くいる鳥が鳴いたり姿を見せてくれるものの、全体的には静かな山のたたずまいである。子どもたちは鳥よりもトカゲやバッタに目が向いていて、手づかみしている。頭上からはアケビの実がぶら下がり、何とか取れないかと大人たちは汗をかきかき奮闘する。紫色に熟れた実は甘く緑色の実はまずいことを実体験する。山頂へ気持ちのよい登り道をゆっくり進むと、目の前には東三河の平野と三河湾のパノラマが広がる。子どもたちは隠れ小屋の樹にすぐに向かった。その前に、昼が近い、弁当を食べるぞ。思い思いに陣取って弁当を広げる。この時ばかりは大人も童心に帰る。おかずを分け合って食べると何倍も楽しめるわけだ。私はしばしまどろみの時間を楽しんだ。(牧神の午後への前奏が浮かんだ)目を覚まし景色を見ていたら、東の方向からゆったりとした羽の動きの鳥がやってきた。トビならば同じ位置で輪を描くことが多い。この鳥は徐々に迫ってきたのでトビではないなと思った。背中の色は黒っぽい、腹が見えたらトビかどうか分かる。輪を描いた瞬間タカ特有の縞模様がはっきり見えた。トビと同等の大きさといえばクマタカかハチクマ。前者であることを願ったがハチクマの可能性が高いと思った。ハチクマは越冬地に向かって今まさに南下中なのだ。クマタカでなくとも十分である。みんなに声をかけ見てもらった。頂上に向かう道中では上空には1羽の鳥いなかったが、それがどうだ、自然観察はなにが起こるかわからないことをあらためて思い知った。帰りは下り道ばかり。心地良い疲れを感じながら林の小路を赤坂の街へと急いだ。
探鳥会光景
①変わった植物 ②大楠のでかいこと ③最初の休憩 ④宮路山を登る ⑤⑥下りになった ⑦⑧⑨駐車場で ⑩⑪⑫⑬山頂へ向かう ⑭陽気に誘われヘビも日向ぼっこ ⑮⑯⑰山頂間近 ⑱⑲弁当を開く ⑳21山頂からの眺め 22碑の前で 23宮路山から下り音羽川で少し遊ぶ
2009 10 9 茶臼山ラインセンサス
台風一過の青空が奥三河の山々の上に広がっていた。おにぎり2個とお茶を買って一路茶臼山へ。何がしかの南下個体が観察できたらいいなと思った。一応ねらいはあった。エゾビタキとノビタキだ。前者には会えなかったが、思いもよらない鳥と出会うことができた。ノゴマである。喉の綺麗なオスではなくて地味なメスであったがそんなことはどうでもいいことだ。最初、声がした時は、ジョウビタキかと思った。姿を見てウグイスのようにも見えた。白っぽい眉斑が目についたのである。しかし、その形は小型ツグミのものであった。ルリビタキやジョウビタキのメスは眉斑はない。もしかしてノゴマ?。残念ながら断定はできなかった。撮った姿をよく見て決めようと思った。その結果が、やはりノゴマに違いないという結論に至ったのである。過去に1度だけ旧額田町でオスのノゴマを見たことがある。たった1個体しか見たことのない鳥なのだ。センサスの間で聞かれたのはウグイスとシジュウカラ、そして、この季節になっても囀りを続けるソウシチョウ。シジュウカラが地元室林道では少ないのに対してここ茶臼山では、ライバルのヤマガラを個体数で圧倒している感じを受けた。カケスもよく見られたし、ヒヨドリの群れ(30羽ほど)が塊りになって飛び去っていくのを見て伊良湖岬のヒヨドリの渡りを連想した。コースの最後は牧場が広がる。ここでノビタキの登場。平地であろうが高原であろうがひたすら南下するノビタキを偉いと思う。12時きっかりでセンサスを終え帰途に着く。途中、平尾でノビタキを、地元音羽でオシドリを確認した。ノビタキが見られる頃にオシドリもやって来る、そんな方程式が今年もあてはまったようだ。
茶臼山で見た野鳥
①-⑧ノビタキ南下個体(⑥-⑧は豊川市平尾町で撮影) ⑨-⑪ノゴマ(過去1羽しかお目にかかっていない)メスの南下個体 ⑫⑬ハシブトガラス ⑭モズのメス
2009 10 10 室林道ラインセンサス..
台風で秋が深まった感じがする。涼しいほどの室林道を気持ちよく歩いた。鳥の影も濃くなったようだ。ウグイス、ヤマガラ、カケスなど。カケスなどは真夏に比べ明らかに個体数が増えていることがわかる。南下個体もいた。前回のセンサスで確認したエゾビタキである。サクラの枝で羽を休めている。オオルリと同じヒタキ亜科の鳥らしく足は短い。オオルリもいた。全く声を発しなくなったのでいることに気がつかない鳥のひとつだ。この個体はメスの体に翼の部分だけ青くなったオスの若鳥である。ヤブサメもいる。ヤブサメの地鳴きはいたって地味である。採餌のために小さな体を存分に使って林床を移動していた。鳥ばかりではない。アサギマダラも南下していたし、ツクツクボウシもまだまだ鳴いている。
①-③エゾビタキ南下中の個体 ④オオルリ若鳥(半成り) ⑤⑥アサギマダラ ⑥の個体は羽が傷んでいる
2009 10 11 我家周辺の野鳥
屋根瓦がはがれた住宅もみられ台風の爪あとが生々しい。しかし、台風は秋の天気をぐっと引き寄せてもくれた。真っ白な卷雲は見ていて本当に気持ちがいい。山陰川の側をぐるりと回るコースでラインセンサスを行なう。まず今日の主役はなっといってもモズだろう。秋の高鳴きの光景をいたるところで見つけることができた。ある個体は電線で、別の個体は梢、縄張りの中に入った個体を追い出すものをいる。田んぼではスズメの群が落穂ひろいを、その周辺ではノビタキが2羽、キセキレイとセグロセキレイも川の中で採餌している。再び川の側を歩いていたら、川下から水面を一直線に飛び去るもの、カワセミのエメラルドブルーの光が眩しいほどであった。トンボが飛び交い、アサギマダラがひらひら宙に舞う。
我家周辺の風景
①家から50メートルほどに山陰川 ②ツユクサと空が青を競う ③竹林も風情がある ④クモも風景の一部 ⑤セイタカアワダチソウも風景に溶け込む ⑥もうサザンカが咲き出した ⑦モズが今日の主役 ⑧この場所をカワセミが飛び去った
2009 10 17 萩小から下加茂神社へ
雨がパラパラ降り始めたのでしばらくは萩小の校舎で待機する。子ども4人・大人1人。暫くして強い雨脚。待っていてよかったー。明るくなり萩っ子の森で観察(というよりアスレチック)をする。アマガエルが多い。(このメンバーは生き物大好き)すっかり止んだのでいざ出発する。ヒヨドリやイカルが小学校の近くで見られ、モズが高鳴きをしていた。山陰川のキセキレイはレモン色で子どもたちも感動。下加茂神社のクスノキも台風の被害を受けていた。折れた枝先が痛々しい。境内で暫く遊ぶことにした。ぽこぺんをやる。羽根・長根の田んぼに行くことは止めにし山陰川で遊ぶ。子どもは遊びの天才とはよく言ったものだ。帰りにこの秋の初確認鳥にであった。ジョウビタキが庭先で採餌していたのだ。オスの綺麗なジョウビタキである。さらに賑やかな声が聞こえる。つがいらしいシジュウカラがツバキの樹に止まった。
探鳥会のコース
①萩小で雨宿り ②-⑤萩っ子の森 ⑥アマガエルと彼 ⑦萩小学校 ⑧山陰川 ⑨キセキレイ(子どもたちが撮影) ⑩元気な子どもたち ⑪川で遊ぶ ⑫記念写真 ⑬山陰川
①好きな野菊の花 ②林の中を小鳥が巡る
2009 10 24 寺ノ入林道ラインセンサス
ヤマザクラがいい色に染まり、シロモジが黄色く色付いていた。標高600メートルの寺ノ入林道はこれからが紅葉の本番といった感じである。ノギクやアザミが林道を飾る。リンドウを一輪見つけたときは嬉しかった。キキョウはもう少し先だ。今日は隣の町にあるライフル射撃場からの音もないので野鳥の鳴き声と沢の音だけが聞こえる。いや、もうひとつ、ニホンジカの遠鳴きもあった。実は、寺ノ入林道に来る道中で頭に角のある立派なオスジカを見ていたのだ。林道を賑わしていたのはカケス。だみ声でお世辞にも綺麗な声では絶対ないが私は好きである。寒い山から聞こえるカケスの声には精神性を感じる。小さな声で林を巡るのは混群鳥たちである。主な配役はエナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、そして標高のある寺ノ入林道らしいヒガラも。ヒガラは囀り個体もいた。この時期に囀りとはどんな理由なのだろうか。カケスと並んで賑やかなのがヒヨドリだ。里の鳥と思われているヒヨドリ、元はといえば山の鳥なのだ。徐々に里に広がっていったのである。だから山にいても活き活きとしているのは至極当然なこと。
色付き始めた寺ノ入林道
2009 10 25 羽根・長根ラインセンサス
ノビタキの南下個体2羽を確認する。ついでにセッカも。セッカについては越冬する可能性もありそうだ。田んぼではヒバリたちが飛び回っていた。なかには囀る個体もいるようだ。畦にはイヌタデの赤い粒々が一杯。ススキの穂も風に揺れている。やがて北西の季節風が羽根・長根の田んぼを支配するようになり、野鳥たちは厳しい冬に備えなければならない。天敵もすでに到着していた。彼に睨まれたら生きた心地がしないだろう。チョウゲンボウの早い羽ばたきはいつ見てもワクワクする。
①-③羽根・長根の田んぼ風景 ④⑤ノビタキ ⑥セグロセキレイ ⑦⑧セッカ
2009 10 28 萩小 秋の探鳥会 3年生 観音山コース
朝起きて窓を開けると気持ちの良い風が入ってきた。隣の畑ではセグロセキレイとハクセキレイが仲良く餌を探している。少し離れた電線にはモズが止まっていて高鳴きだ。我家も縄張りに入っているオスのジョウビタキ、隣の庭でヒッヒッヒッと朝の巡回を開始している。きっとこんな光景が子どもたちの前にも繰りひろげられることだろう。隣の上加茂神社ではオオタカもいた。幸先がよさそうだ。校庭に集合した3年生以上の子どもたち、インフルエンザの影響で少し淋しい感じだ。ここは元気よくやるしかないか。3年生と観音山のコースを行く。今年が探鳥会のスタートとなった子どもたちに思い出に残るものを、と願いつつ校庭を後にする。プール脇の木立でエナガの群を発見。エナガの群を初めて見たときの印象は、17年経った今でもはっきり覚えている。つむじ風のようにエナガたちの声が迫ってきた、とたんに辺りは鳥が縦横無人に飛びかい出した。それはそれは可愛らしいエナガであった。私はそのときの情景を、おしゃべりの女の子たちの群に入ったようだと思った。ものの1分もたたないうちに群はどこともなく去ってしまった。あの騒々しさはなんだたのだろう。子供たちが個体数をカウントする。枝で動き回っているときは無理、飛立ったときがチャンス。個体数は13。きっとこの数はクラスの子だけのものになるのかも。倉の民家を抜けるときにもいろいろな鳥を見た。モズ・トビ・セグロセキレイ・ハクセキレイ・スズメ・日頃通学でもおなじみの鳥たちだ。そして我家でも見かけたジョウビタキ。冬鳥として海を渡ってきた姿は子どもたちにはどう映るのだろうか。善住禅寺ではこれも魅力的な鳥がお出ましだ。同定に少し時間を要したがチョウゲンボウである。さらに上空にはノスリのペア。隣ではモズが高鳴き。目が回ってしまう。高台を下りると山陰川が見える。ここはなんといってもカワセミが主役だ。子どもたちには「川の上から目をはなさないように!」と告げ、一列になって進む。川の見えるのは200メートルくらいしかない。この間にカワセミが見られるとは正直思わなかった。しかしいたのだ!。最初は川下に向かい一直線。全員がはっきりと見たようだ。さらに、Uターンして川上へ飛んでゆく。もう大サービス。観音山へは田んぼ道を行く。山が迫り鳥たちが飛んで行く。のどかな風景の中に子どもたちの元気な声が響く。身も心も気持ちよい。近道するため帰りはさらに自然な道を歩いた。子どもたちには日頃あまり通ったこのない道だろうな。
探鳥会光景と見つけた野鳥たち(オオタカをのぞいて別の日に撮ったものです)
3年生の子どもたちと先生 萩小から観音山へ
こんな鳥がいました
①アオサギ ②エナガ ③ハシボソガラス ④ホオジロ ⑤ジョウビタキ ⑥キジバト ⑦モズ ⑧ノスリ ⑨ カワセミ ⑩探鳥会の朝見たオオタカ(幼鳥)
2009 10 31 茶臼山ラインセンサス
紅葉狩りのマイカーが朝早くから茶臼山に来ていた。真っ青の空にほどよい風が吹いていて、歩いて行なうラインセンサスにはもってこいの日である。山頂付近は落葉も始まっているが、所々に植えられているモミジやドウダンツツジは真っ赤だ。もっともこれらは後から植えられたものである。ホオジロがカラマツの天辺で囀っている。室林道など平地でもそうであるが今ホオジロの囀りが聞かれる。この季節で聞かれた囀りはホオジロとソウシチョウそしてイカルである。今日のセンサスでもホオジロとソウシチョウは賑やかに歌っていた。特にソウシチョウは全ての野鳥の中でも一番繁栄しているのではと思うほど。冬鳥も見られた。ジョウビタキにルリビタキはもちろん、大好きなカヤクグリも鳴いていた。チリリ・チリリ・チリリ地鳴きなのに美しい声である。ソウシチョウの囀りと地鳴きは、ウグイスなどの囀りが無くなった今、山に明るさをもたらしてくれていると思うが、外来種であるということを割り引いても少しうるさいな!が本音である。冬鳥の茶臼山はアトリ科の鳥たちが主役になる。ベニマシコや運がよければオオマシコ・ハギマシコも飛来する。今日はそこまでは。イカルとカワラヒワが塊りを作って飛んでいる。群を見るとついついハギマシコを期待してしまう。360度のパノラマは天気の割には見通しが利かなかった。それでも奥三河の山々や長野最南部の秀峰が手に取るように見られた。センサスする道路は車の通りが多かった。重いカメラを担いでいると物珍しそうに見てゆく。てやんでい!こっちとらもう20年近くからここを歩いているだぞー!。
2009 10 31 茶臼山ラインセンサス
紅葉狩りのマイカーが朝早くから茶臼山に来ていた。真っ青の空にほどよい風が吹いていて、歩いて行なうラインセンサスにはもってこいの日である。山頂付近は落葉も始まっているが、所々に植えられているモミジやドウダンツツジは真っ赤だ。もっともこれらは後から植えられたものである。ホオジロがカラマツの天辺で囀っている。室林道など平地でもそうであるが今ホオジロの囀りが聞かれる。この季節で聞かれた囀りはホオジロとソウシチョウそしてイカルである。今日のセンサスでもホオジロとソウシチョウは賑やかに歌っていた。特にソウシチョウは全ての野鳥の中でも一番繁栄しているのではと思うほど。冬鳥も見られた。ジョウビタキにルリビタキはもちろん、大好きなカヤクグリも鳴いていた。チリリ・チリリ・チリリ地鳴きなのに美しい声である。ソウシチョウの囀りと地鳴きは、ウグイスなどの囀りが無くなった今、山に明るさをもたらしてくれていると思うが、外来種であるということを割り引いても少しうるさいな!が本音である。冬鳥の茶臼山はアトリ科の鳥たちが主役になる。ベニマシコや運がよければオオマシコ・ハギマシコも飛来する。今日はそこまでは。イカルとカワラヒワが塊りを作って飛んでいる。群を見るとついついハギマシコを期待してしまう。360度のパノラマは天気の割には見通しが利かなかった。それでも奥三河の山々や長野最南部の秀峰が手に取るように見られた。センサスする道路は車の通りが多かった。重いカメラを担いでいると物珍しそうに見てゆく。てやんでい!こっちとらもう20年近くからここを歩いているだぞー!。
①②豊根ビジターセンターにて ③-⑨茶臼山センサスコースの紅葉 ⑧シロモジの実 ⑩-⑭奥三河の山々大パノラマ ⑮大入川山 ⑯ここまで来るとセンサスも終わり ⑰-⑲ホオジロの囀り個体 20-22ルリビタキ 23ソウシチョウ
①駒場池 ②やって来たマガモの群 ③-⑥マガモの飛行 ⑦⑧カルガモ ⑨オシドリ ⑩平尾の里山風景 ⑪ホオジロのオス ⑫⑬ホオジロのメス ⑭⑮ノスリ
2009 11 8 観音山
室林道から観音山にコースを変更した。理由は、開けた場所の方が鳥を見やすいと思ったからだ。萩小探鳥会でのカワセミとの出会いもまだ記憶に新しい。子どもたち5人と暖かな光の溢れる萩の里をのんびり歩いた。もっとも彼らの興味はめまぐるしく変わるので決してコースどおりに歩くことはない。当然ながら危なそうな所は厳しく口出さなくてはならない。萩小探鳥会では倉の山陰川でカワセミを見た。同じか所を同じように一列に歩いた。今回はかなり進んでからカワセミを見つけた。川下に一直線。子どもたちは戻るのを承知でカワセミを見つけたいと言い出した。これは良い状況だ。思い入れがなければわざわざ戻るなんて思わないと思うからだ。おまけに、常にさわがしい子が「シー・静かに」何て言っている。熱意が通じたのか、彼は土手から伸びた枝にとまって川面を見ていた。スコープで見るその綺麗な姿。しっかり記憶に残るだろう。観音山が近づいて来た。田んぼや川ではセキレイたちが賑やかに鳴いている。セグロセキレイ、ハクセキレイ、キセキレイなど。時折ビンズイの声もする。キセキレイの個体数が多かったように思える。気温が下がって一斉に山から下りてきたのでは。山の緑の中にポツンと白いものが見える。スコープに映し出されたのはやはり萩小探鳥会で見たことのあるチョウゲンボウであった。胸の縞が縦にあるので幼鳥であることも一緒。きっと同じ個体だと思う。捕った獲物を梢で食べていたのだ。これまた凄いシーンを見たものだ。結果的にコースを変えたことは大変良かった。彼らの興味は多岐にわたっている。決して鳥だけを見たいのではないが、一瞬でも野鳥に打ちこんでくれたら嬉しい。
探鳥会コースの風景
①腕白盛り ②カキが豊作だ ③今頃アサガオ? ④畑も青々 ⑤キンカン ⑤スズメとモズ ⑥カーブミラー ⑧観音山がそびえる ⑨カワセミ(子どもが手持ち撮影) ⑩セグロセキレイ ⑪キセキレイ ⑫記念撮影 ⑬トビ ⑭チョウゲンボウ ⑮-22子どもたち
2009 11 14 室林道ラインセンサス
朝方が最も雨脚が強かった。窓を開けると細かな雨しぶきが舞い込んできたほど。それも9時過ぎには止み、それとともに室林道に向かって車を走らせた。我家から室林道までは直線距離にして2キロ程、10分もあれば着いてしまう。これほど近いところで豊富な野鳥が観察できるなんて私はしあわせ者だ。室の山を旋回している小鳥の群を発見。その数およそ50羽ほど。飛び方や微かに聞こえる鳴き声からイカルであることが分かる。冬にして美しい声で囀る変わった鳥、決して珍しい鳥ではないのだが。晴れ間が広がるにつれて野鳥たちの動きが活発になる。エナガが動き出すとカラ類たちが後を追う。ヒガラがいないかと注目したがどうもいないようだ。本格的な冬鳥の訪れはもう少し先か。センサスの終わりに一声、カケスが鳴いた。
雨上がりの室林道
2009 11 14 我家周辺の野鳥
夕日で秋草が輝いた。一番はススキ。スズメの群れがススキに止まっている。近くを通り過ぎたら一斉に飛立ちイチジクの樹にとまる。それが黄金色に染まり素晴らしい景色であった。スズメをバカにしてはいけない。川沿いの道を歩いたこともあってセキレイが多かった。キセキレイ、セグロセキレイは勿論、ビンズイやタヒバリの鳴き声も聞こえる。
我家付近を歩いた
①-④散歩コース ⑤-⑦スズメ ⑧ホオジロ
2009 11 15 乙女川
乙女川
乙女川と言うとやさしい流れと思われるかもしれないが、岩盤がむき出しになった川底には大きな岩の塊が水の流れを変え渦をまくような、どちらかというと男性的な川である。アユなども遡上する清流なのだ。鳥ではなんといってもカワガラスが棲息していることだろう。流れが直角に変わる箇所に堰があって滝の裏側に造られた巣に突進するカワガラスを見たこともある。数年ぶりに今年カワガラスを確認できたのは嬉しい出来事であった。オオルリなどの夏鳥が去った今、静けさをとりもどした乙女川ではあるが、ヒョドリやウグイスのおなじみの鳴き声を聞きながら歩くのもまたいいのもだ。川沿いの林も先の台風の爪あとがあちこちであった。キラキラ輝く川面を目を細めて眺めていると、こうして川を見ることが減ってきたことを思わずにいられなかった。川は命の源。それほど大切で身近である川を今の人たちは無関心になってしまった。名勝地に行けば愛でることもしよう。しかし、生活に密着した我が川を忘れてしまったのだ。
雨山ダム
乙女川の上流に雨山ダムはある。高さ12.5m 幅160m。大きなダムではないが近寄ってみると結構迫力がある。ダム湖の名前は三和湖。周りの山々には多くの野鳥がいる。駐車場にキセキレイがいた。周りが静かなだけにキセキレイの澄んだ声がよくとおる。中学のとき萩からこの近くを通り本宮山に登った。谷から尾根までの坂を必死に登ると本宮山が顔をのぞかせていた。あの道はまだあるかしらん。たしか道の片側にはイノシシなどを食い止める石垣があったように記憶している。
大代
18年前、野鳥観察を始めたころは家から近い野山を主なフィールドにしていた。大代もそのひとつで、秋深まった頃にはにミソサザイやヒガラの姿を求めて歩いた。1日で5羽も6羽も見つけることも珍しくなかった。あまりに近すぎるため、その後はメインのフィールドになれなかった。少し遠くに行きたいと思うのは止む得ないことだ。少し寄り道すればこれほどご無沙汰することもなかったのにと思う。萩ではヒガラを毎年みることはなかった。山寄り位置する大代までは来るのに萩に下りてこない。そんな言葉を師匠の山口さんから何度も聞いたことがあった。県道から山に車で入ってみた。ホオジロが数羽飛立った。たしかここにはホオジロやアオジがいたっけ。この突き当たりの場所はミソサザイが必ずいたな。見覚えのある地形。そこではミソサザイのかわりにウグイスが鳴いていた。
①-⑤乙女川 ④の堰 滝の裏側にカワガラスの巣があった ⑥⑦雨山ダム
2009 11 21 茶臼山ラインセンサス
茶臼山に着いた時には既に正午を少しまわっていた。風も強く体感温度は相当低い。ウインドブレーカーと手袋は絶対必要。スキー場のゲレンデには数台のスノーマシンが並んでいる。たしか新聞で試運転をしている記事が載っていたがいよいよ冬本番だ。リフトの近くでコガラを確認する。コガラは頑固に山を下りようとはしない。カラ類のなかでは地味な鳥ではあるが魅力がある。そして茶臼山定番の冬鳥であるベニマシコもいた。フィフィと柔らかな声で鳴く。東を見ると雪化粧の赤石・荒川・聖が聳えている。寒いはずである。2・3日前に降った雨、山では雪を散らしたのであった。北面は日陰になっていて芯から冷える。ベニマシコやカヤクグリの出現を期待したがなにもなかった。恵那山・大川入など長野県南部の山々や紅葉の風景を眺めていたら、視野の端に鳥の群が飛び込んできた。しかし、遠すぎて種類は分からない。少し大きな体からアトリ科のイカルかシメかなと思っていた。さらに歩いてアルプスの見渡せる場所に着いた。ここで山の写真を撮る。聖が雲の上に聳えていた。引き返そうとしたら再びあの群にであった。今度は鳴き声が聞こえる。その声はツグミのものであった。そういえば過去にもツグミの大群を見たことがあったけ。忘れていた。今晩はさらに山奥の山荘に泊めていただくことになっている。そろそろセンサスを終えて向かわなくては。
①聖岳 21日 ②聖岳 22日 ③④南アルプス南部(左より荒川岳・赤石岳・聖岳の3千メートル峰) ⑤ゲレンデに勢揃いの製氷機 ⑥センサスコースも枯野姿 ⑦奥三河の山々(碁盤石山・天狗の棚・丸山) ⑧根羽の山々
①高嶺(茶臼山の北隣の堂々とした山) ②平谷川 ③④⑤裏山(三階峰)にて ⑥裏山からの素晴らしい眺め ⑦三階峰山頂の大岩 ⑧山頂をバックに
2009 11 29 室林道ラインセンサス
寒い朝となった。豊橋で用事を済ませそのまま室林道へと向かう。曇空で暗い林を予想し、50×7の明るい双眼鏡を持参した。1.5㎏と重いレンズなので腰からベルトで引っ張り首への負担を減らすことは重要だ。反面、その重さが手振れを抑制してくれる。明るさ50は虹彩が最も広がった状態に一致し、これ以上明るくしても虹彩で遮られるので意味を持たない。星空の観望にも勿論有効であるし、薄暗い林床の鳥を観察するのにはこれ以上の道具はない。サクラの枝に群れるメジロたち。目の周りの白い輪がくっきりと見える。50ミリの解像力が野鳥の観察にも威力を発揮する。しかし、ノートに記録されるのは声だけの個体が7割以上を占める。ミソサザイの地鳴きをこの秋初めて室林道で聞いた。また、繁殖期に高山で聞いたルリビタキの囀りが室林道に響いた。ルリビタキは越冬地として平地に下りてくるわけであるが、来て間もない頃にオスだけではあるが囀りをすることが珍しくない。地鳴きが聞こえたのでルリビタキ地鳴と記録した。するとまもなく囀りを始めたのであった。ルリビタキが室林道で囀る?。何度も聞いてはいるが毎回不思議な感じを受ける。室林道がやけに静かに感じた。野鳥観察もいよいよ冬のステージになったなと。その静かな原因のひとつはヒヨドリの鳴き声が減ったからに違いない。今年の里の風景はカキのオレンジ色が一杯溢れているようだ。カラスやメジロとともに果物に目のないヒヨドリ。山から下りてきてご馳走をついばんでいる姿が其処ここで見られるようになった。その分、室林道は静寂さを増したのである。
秋深まる萩の里山と野鳥たち
①②カキと月 ③夕日に染まる観音山 ④倉 田んぼ風景 ⑤再びカキ ⑥ノギクも散りかけた ⑦これから見ごろのサザンカ ⑧⑨セグロセキレイ ⑩ハクセキレイ
⑪⑫キセキレイ
2009 12 6 室林道ラインセンサス
どこも同じだろうが今年の紅葉は見事である。室林道も例外ではない。黄色や橙色の落葉樹と常緑針葉樹や照葉樹の緑色が織りなす景色が室林道を飾る。それに、真っ青な空の色が加わる。白い雲も忘れてはいけない。季節風が吹き始めるともうひとつ必ず起こる現象が。バロック音楽の通奏低音ならぬ通奏重低音の響きである。弦は山から山へと架けられている鉄塔の24本の高圧線、それを季節風が奏でる。滝の音と言ったら似ているだろう。藪からクロジの地鳴き、負けじとウグイスもササの中から鳴く。ミソサザイも定着しているようだ。ウグイスに似ているようで全く違うとも言える。先週、ルリビタキの囀りを聞いた。今日は姿を確認。その名のとおり青いオスの成鳥であった。
紅葉織りなす室林道
どれほどこの道を歩いただろうか。(今日で748回目 17年かかった)同じ景色は2つとない。1回1回を大切にしたいと思う。
2009 12 6 羽根・長根と新堤池
室林道から羽根・長根に下りてきた。農道をゆっくり歩いてみる。草花もモミジ色に変わってなかなか風情がある。しかし、新鮮な緑色の場所もあってそれはそれで綺麗である。セグロセキレイやハクセキレイが鳴きながら飛び回っている。彼らは田んぼで採餌をする鳥にしては色が派手、一方、同じセキレイ科のタヒバリは、鳴かずにジッとしていたら存在に気付かれることはないだろう。彼らに近づくと一斉に鳴いて飛び回る。ぴぴぴと澄んだ地鳴きである。本家のヒバリも田んぼで採餌しているが、こちらも急に飛立つ癖はタヒバリと同じである。畦で咲いているのはタンポポとイヌタデ。黄色と濃い桃色はこの時期には貴重な色だ。周りの山々には黄色やかば色の林が、常緑林と混ざり合って織り錦である。続いて水鳥を見にゆく。羽根・長根の田んぼのすぐ近くにある新堤池、そこには秋になるとマガモが大陸から飛来して来る。それほで遠くはないが、オシドリが深い山奥から里にやってきて冬を越している。音羽の中でも自然な姿のオシドリが見られる貴重な場所である。ササを分けて池に近づいてみると、水鳥たちの声が聞こえる。マガモのオスとメスが湖面に浮かんでいた。オシドリたちは池の周りに生える木々に隠れてよく見えない。双眼鏡で探すと枝の上に止まっているものもいる。装飾過剰のオスと灰色の地味なメスが樹の陰で行ったり来たり。しかし、なかなか池の中には来ない。勇気ある個体の出現を待つしかないのである。
①②羽根・長根ハクセキレイ ③④⑤羽根・長根の風景 ⑥新堤池 マガモ ⑦-⑫オシドリ
2009 12 19 土曜探鳥会 羽根・長根の田んぼ
朝起きて驚いた。畑や屋根が真っ白ではないか。さらに心配させたのは、白いものが止むことなく空から落ち続けていること。探鳥会大丈夫だろうか、牧野さんに電話しなくていいだろうか。もうそろそろ家を出発されている頃だ。道路には積もっていないようだしまあいいか。やっちゃえ。そんなこんなで萩小に来てみると、校庭で雪だるまを作っている二人の姉弟を見た。今時珍しい元気のいい子たちだ。牧野さんも遅れず着いた。どうですかと聞いたら、家のほうは全く降っていないとのこと。それでも雪が降る中を歩き続けることには抵抗を感じた。しかし、それでもやって来た子どもたちのことを考えるとやろうと思った。あとは回復してくれることを祈るだけだ。下加茂神社を過ぎた頃から雲に切れ間が見えてきた。南の方は青空ものぞいている。お日様の力は凄い。メンバーの気持ちもずっと明るくなってきた。そこで見たのがビンズイ。子どもたちはあまりなじみのない鳥の名前である。電線に止まってポーズをとってくれた。羽根の田んぼに入る所でスズメが一杯とまっている木を見つけた。そのスズメがみんな丸くふくらんでいる。袋雀である。羽根・長根の田んぼから室林道方面をみるといつもは濃い緑の山が、砂糖をふりかけたようになっていた。今日は2人の新しい子どもたちが参加してくれた。朝校庭で雪だるまを作っていた姉弟だ。子どもたち6人と大人3人が向かった先は新堤池。再びオシドリに会うため。ところが今日に限ってオシドリたちは木陰に隠れて姿を現さなかった。そのわけは木立の一角にとまる小型のタカにあった。その姿は威厳に満ちていて金の虹彩が辺りににらみを利かせていた。ライオンとシマウマと同じ関係を今見ているのだ。萩小からここ新堤池まで一気に歩いてきた。しばらくはおやつをいただいて休むとしよう。いつもの石垣のある暖かい場所で。
雪だるまづくりから始まった土曜探鳥会
①②校庭は一面の雪 ③④川原の通学路を進む ⑤最初のスズメの群 ⑥-⑯羽根・長根の田んぼでは暖かい日差しが ⑰再びスズメの群れ(手持ち撮影)
2009 12 19 家周辺の野鳥
萩小からもどってみたら皆は食事に出かけたあとであった。パンで昼食を済ませ暖かな午後をもう少し楽しむことにした。時折雲が太陽を隠すことがあったが、それ以外のときは気持ちが晴々とするそんな午後であった。アオジのオスを久しぶりに見た。その近くからも幾羽かの地鳴きがしたのでこの辺りは、アオジにとって棲みやすい場所なのだろう。ホオジロも沢山見かけた。この鳥もありふれてはいるが味のある姿をしている。サクラの樹の又にタカの姿。思わず息を呑む。ところがこのタカ微動だにしないのである。正面に回ってみるとそれは作り物ではないか。はっとして損をしたと同時に悪戯とは言えないまでも、あまり褒められた趣味ではないなと思った。
師走の我が家周辺の鳥たち
①スズメ ②-⑧アオジ(オス) ⑨⑩ハシボソガラス ⑪⑫ジョウビタキ(メス) ⑬ヤブツバキが咲いていた ⑭⑮初冬の風景 ⑯こんなところにタカの置物