2024 12 30 室林道ラインセンサス
今日が室林道ラインセンサスの今年の最後になると思う。10日間で2度目となった理由は、1回目が、車で移動したのが残念であったからだ。やはり、歩かないと。ただ、その時は腰を痛めて歩けなかった。今は大丈夫だ。林道の入口でカケスが鳴いた。幸先良い。久しぶりのカケスだ。エナガの群れが来た。しかし、姿が分からない。こういったときは個体数は1とする。実際は10個体以上いるはずだ。ミソサザイは2個体確認する。4個体確認できた日もあるので、今年の冬は盛況と言ってよいのでは。ヤマガラ、シジュウカラも順当に確認できた。しかし、ヒガラは駄目だ。どうしても見てみたい。正月飾りに良さそうなセンリョウも艶のある実を付けている。似た者のマンリョウは見向きもされない。細かな所を見ていると、岩に模様を作る地衣類(だと思いが)の模様が気になってしまった。天井のシミやなどと同じ種類の面白さ。何とか絵になるのをと頑張ったが駄目であった。
室林道には色んな表情がある。植物も奥が深く何も分からない。
2024 12 29 ふるさと公園
公園の仕事は朝の6時に始まる。門扉の開閉を、シルバー人材センターの一員としてやっているのだ。もう13年になろうとしている。冬は寒く辛いが、星を見ながら仕事ができることが辛さを耐える力になっていると思う。今日、ほんの一時であったが、なかなかお目に掛かれない、水星(Mercurius)を見た。場所は、ふるさと公園に入ったばかりの所である。明るい1等星くらいであった。またたきが少ない、色は金色、その辺りは明るい恒星は無いはず、などから惑星であろうとにらんだのだった。30日にWEBで調べた所、12月25日、水星西方最大離角とあった。東の空と言う意味になる。間違いない。スマホで撮ったのには新月手前の月が写っていた。その月の少し東にあるはずであったが、日の出も迫っており、残念ながら写ってはいなかった。
2024 12 27 室林道ラインセンサス
腰を再び痛めてしまった。年末のこの時期にやってしまうとは、全くもってだらしがないとしか言いようがない。今年の最後のラインセンサスである室林道下旬が残っているのだから。2日間は横になっていた。大変なのは起きる時、いつもながら情けなく思う。3日目の今日、できるだけ起きていようと思う。運手はできるのか試してみた。何とかできそうなので室林道へ出かけることにした。車からのセンサスはどうしても雑になる。エンジン音もあるが速度も速い。センサス結果は参考程度と考えた方がよい。ヒヨドリの声から始まった。何時もの室側ではなく長根側から入るので、2倍の距離をセンサスすることになる。室側に設置されている車止めを移動させることは今の自分には無理。室側入り口を折り返して長根側から出るわけだ。クロジらしい姿を見た。色と周りの環境からクロジと判断した。アカゲラもいた。こちらは鳴き声と色から判断。何時も折り返し点にはセンダンがあって実が生っている。小さな鳥が何羽もいたがそれはメジロである。あとは、ヤマガラ、ソウシチョウ、ハシブトガラスであった。最後の最後にこのような結果になってしまい残念ではある。しかし、仕方がない。何が起きるか分からない。
軽トラックでセンサス。写真もあまり撮れない。
2024 12 24 ふるさと公園ラインセンサス
太陽が上がったばかりのふるさと公園をセンサスした。遠く本宮山に朝焼けの雲がかかっている。私の地元から見える山々も朝日を浴びてきれいだ。園内では散歩の人たちでこれから賑わいが始まる。あちこちで野鳥の声がするが、最も多いのはヒヨドリで、次いで、メジロといったところか。ヒヨドリは2羽で飛ぶのがよく見られる。本当のつがいなのか?キジバトやシロハラは居ればすぐにほど鳴き声が大きい。やはりサイズが影響しているのか。反対に、メジロは、たぶん量ではヒヨドリに勝っていそうであるが、何分声が小さいので数を少なく見積もってしまうだろう。日が通過して見える林の景色が特に好きだ。写真を撮るのにも順光よりも逆光を選んで撮る。そんな写真を今朝はたくさん撮った。
赤い太陽が登る中、野鳥たちも気持ちよさそう。そういえば、今年の正月も朝焼けで始った。(1月4日分をご覧ください。)
⑰-⑲レース鳩の訓練 ㊲-㊵キジバト ㊶-㊸メジロ
2024 12 22 寺の入林道ラインセンサス
茶臼山に引き続き、2024年最後のセンサスをしに三河湖に出かけた。こちらの標高は茶臼山のほぼ半分なので雪の可能性はまずない。それでも寒いことには変わりはなかった。冬季においては、アトリ、マヒワといったアトリ科の鳥が一番の楽しみな場所である。今日はそういった鳥ではなく、意外な鳥の声に少々驚いている。その鳥はウグイス。夏季の寺の入林道での不思議が、ウグイスがとても希少種であること。だから、今ここでウグイスが鳴くか、そんな気分で声を確認した。ミソサザイもいたがその声とは違う。シロハラでもない。ウグイスでしかあり得ない。アトリよりも嬉しい鳥の出現。山を下がらないのか?話は変わって、茶臼山でもここ寺の入林道でもやたらにニホンジカの声を聴いた。彼らの繁殖期は少しばかり早い。
ニホンジカ(3回鳴いている)

寒々とした景色
2024 12 21 茶臼山ラインセンサス
前日にスタッドレスタイヤに替えたばかり。いいタイミングで茶臼山に出かけることができた。ディーラーの人の話では、タイヤ交換の依頼が多くて、今からだと今年中の交換は難しいとのことであった。国道から茶臼山への道に折れるとチェーンの要不要の看板がある。この日は必要であった。ここまでの国道は全く積雪は無かったのであるが。スキー場は問題なく滑走可能であるようだ。防寒と滑り止めを万全にして早速歩き始める。農作業で使用するスパイク付きの長靴が大活躍だ。国民休暇村の付近で鳥を見た。この日は双眼鏡が無い(忘れた)ので、最近新調したメガネを付け補強した。多少良く見える。数羽のヤマガラのようだ。雪景色の中で見ると大変目立つ色だと思う。実際、寒色系のシジュウカラ・ヒガラは雪景色の中では保護色的に見えるようだ。ほぼ同じ場所で群れていたのがツグミ。まだ私の地元では見ていない。そのツグミの前に現れたのがミソサザイ。冬季には、越冬のため、平地に下りてくるイメージのミソサザイを標高1300メートル山中で聴くのは意外に思える。このままここに居座るのか、さらに山を下りるのか、観察する楽しみが増えるというもの。学校が冬休みの入れば、親子の歓声が響き渡ることだろう。
雪の中を歩く。何時も思うが、景色をひとり占め。
①-⑧コガラ ⑨ツグミ ㉔ニホンジカを見る(鳴き声はいっぱい聴いた) ㉓加賀白山が見えた!
2024 12 16 室林道ラインセンサス
今日の室林道センサスを思い返しながらこの日記を書いている。ミソサザイのたった一声に動揺を覚え、急いで録音旬準備をするもそれっきり。それを4回繰り返した。1回だけ録音に成功する!混群が現れたら大忙しだ。そのなかにある鳥を懸命に探している自分がいる。その鳥の名はヒガラ。越冬に飛来する鳥たちの中でも、1番か2番に待ち焦がれる鳥である。普通に居そうで見つからない。それも、私が地鳴きを完全にマスターしていないことが大きいと考える。マスターしていたら直ぐに分かるはずなのだ。メジロとの区別が今一つ分かっていないのだ。メジロは分かる。しかし、ヒガラは分からない。なんとも残念である。冬季の室林道の一番の楽しみは混軍との遭遇だ。たった今まで静かな山であった。時折、ヒヨドリやカケスが張り裂けるような声を上げているが、深々とする空気にのまれて鳥たちも沈黙するばかりだ。そこに一連のエナガがやって来て踊りだす。成鳥に若鳥たちも混じり合ってどんどん数を増す。そこに数羽のヤマガラが合流して餌を取り合う。暖かな色を見るとホッとする。今度は寒い色のシジュウカラのお出ましだ。カラ類のリーダーらしく押しの効いた声で鳴いて、地上近くにも下りたりする。メジロは群れに入るのかどうか分からない。メジロはメジロで仲間を作りどこかに行ってしまう。混群のしんがりはコゲラと決っているよう思える。ギ―と少し的外れな声で追従する様が可愛らしくも滑稽でもある。冬季で会いたい鳥の1番2番の鳥のもう一つはカヤクグリだ。昔は毎年やって来た。今はまず見られない幻の鳥のなっている。
クヌギやヤマザクラが綺麗に紅葉している。紅葉のような派手な感じはないが気に入っている。
2024 12 8 室林道ラインセンサス
歳末赤い羽根募金が始まる前に2時間のラインセンサスを終える、そのために、朝7時に室林道へやって来た。今日の日の出は6時46分。山に囲まれたここの日の出は7時過ぎになる。センサスの半ばころに林の中から日の光を見たからそんなところだろう。最初の声はヒヨドリとウグイス。ヒヨドリはどんな時でも失望させない頼りがいのある鳥の筆頭だ。ウグイスの地鳴きは要注意。シロハラと違うか、まず疑ってかかり、その後ウグイスC(地鳴き)1とノートに書く。メジロC1、ヒヨドリC1、ハシブトガラスC1・・・・。姿 V(ビジュアル)の記号はなかなか出てこない。実際に見られたのは、キジバトV2、不明Vだけである。不明なのはカラ類と思うが、ヤマガラかシジュウカラかもしかしてヒガラか。大きさからヒガラとも思ってはいるが確信できなかった。ミソサザイが鳴いた。こちらには自信がある。ウグイスともシロハラとも違っている。冬の室林道の名物鳥と言いたい。メジロももちろんいた。センサスを折り返す頃になると日も上がり明るくなる。冬の山、それも早朝、寒くはあるが身が引き締まる感じが好きである。
夜明け 暗闇と光が交錯する室林道 光があるとホッとする
⑨-⑪羽が散乱していた、捕食されたのであろう
2024 12 4 萩小秋の探鳥会1年生。長根方面
快晴の探鳥会日和だ。少し風が強いのが気がかりである。その心配は半分当った。学校を出て、神社の脇を通り、山陰川の2つ目の橋を渡るまでは、鳥の姿らしい姿を見ることができなかった。かろうじて、ヒヨドリの声と、木々の間を飛ぶヒヨドリが見られただけである。川の様子を見ると、橋の下流でカルガモが群れている。橋の上からだと手前の草木が邪魔になる。県道沿いではあるが一応コミュニティバスのバス停なのでそこに移動。ここからならよく見える。児童たちも双眼鏡にチャレンジする。羽根の田んぼ地帯へと入る。すると2羽目の見所があった。真正面の電柱の先にノスリがいたのだ。凛々しい姿を子どもたちにスコープで見せる。それからは田んぼの中にいるハクセキレイやセグロセキレイ、空を群れるカワラヒワ、やはり電線にとまるモズなどを見つけた。この日は未だカワセミを見ていない。そこで、予定通りに向山大池へと向かうことにする。過去に何度もカワセミが見られたからだ。しかし今日は空振りに終わった。そろそろ学校に戻る時間。カワセミはあと2回チャンスがあるからと言って戻る。来るときカルガモのいた場所で奇跡が起きた。カワセミがいたのだ。コンクリート棒にとまっていた。さらに手前の石の上にとまったのち下流へ向かって行った。タイミングがドンピシャ。さらに追い打ちをかけるようにして、本日2個体目のノスリも見られた。(写真)帰り道は1年生らしく楽しく帰った。歌声も出た。満足した声のように聴こえた。
見ごたえのある大きな鳥が人気であった。
①カルガモ ②-④ノスリ(②③と④は別の個体)
2024 12 1 子ども探鳥会 観音山方面
大人3人、子ども2人のミニ探鳥会。前日の天気予報をは曇り空でパッとしないものであった。それがこんなに晴れ渡るとは。天気を予報するのは難しいものだ。無論、合っているいる確率の方が高いことは承知しているが。良い方に変わったのだからよい。今回のスタートは寺そばの隣を通るコースとした。ジャルダン・リラの道は、山に近く日が当たらないので、寒いと判断したからだ。寺そばの駐車場でジョウビタキのオスをみた。子どもたちがスコープで見せてくれた。ジョウビタキにはコースの至る所で出会った。お母さんと娘さんと話をした。ジョウビタキを見たそうだ。図鑑で示すと、「そうそう」とかWしてくれる。止まっている車のサイドミラーに、点々と鳥の糞が付いているのを見た。「これ、ジョウビタキがとまっていなかったですか」と尋ねると、「いました、いました」と言われた。ミラーに写っている自分を威嚇する姿も見たと言われる。善住禅寺の前を通り、背戸路を抜けて、亀忠和菓子所を抜け、山陰川に出る。最近、2年3年がお菓子の作る体験をしたばかり。さぞかし美味しいかったに違いない。そこで先生が、川上に向かうカワセミを見る。それではと、川を上流に向かって進む。ここで向きを変えようとした途端、きらりと輝く姿を見つけた。カワセミだ。ダイビングをしている。それも2度3度と。スコープで観察。メスかな?(写真を拡大してみたら、若鳥らしく見える。腹部のオレンジが鮮やかではない。)川から山へと進む。付近の人しか利用しない、隠れた小路を歩いて行く。メジロやヒヨドリの声が多い。きれいにしてある家を抜け、竹林の路を進む。その先で休息を取った。ポカポカ陽気で、防寒の恰好では暑いくらいだ。もぐもぐタイムはいつも楽しい。あとはのんびり学校に戻るだけ。全く雲が無く、抜ける青が凄い。
青空と色づいた山を眺めながらの探鳥会最高!
①-⑤ハクセキレイ ⑥⑦ジョウビタキ ⑧-⑩カワセミ(何度もダイブしていたが、若鳥なので漁が下手なのでは?)
2024 11 26 萩小秋の探鳥会6年生 室林道
一週間前からこの日の天気が心配だった。探鳥会の時間帯(午前中)だけは降って欲しくないと祈る。終わったあとならいくらでも降ってくれ。そして、実際にそのようになった。いま日記を書いている夜、ものすごい雨音がしている。冬の雨とは思えない。朝、所々に青空が見える天気にほっとした。登校の見守りを終えた後いったん家に戻り、可燃ごみをゴミ集積所に出して、すぐさま学校へと向かう。講師の先生方とは春の探鳥会以来だ。6年生は室林道。今年は歩いての探鳥会。例年は自転車。林道本体までは届かないが、道中にも様々な鳥がいるのを観察できる。それはそれでよいと思った。民家ではジョウビタキを見た。フィールドスコープで観察。スコープの操作は全て児童たちに任せる。室地区の空を群れでいるのはイカル。ヒヨドリよりは小型で、同じ波動状の飛び方を説明する。民家を抜けると上り坂になる。自転車でここを登るのはかなりきつい。樹上から鳥の声と姿が。混群だ。シジュウカラ、エナガ、コゲラなどを確認する。そして最後のクライマックス。100メートルほど先でニホンザルがいた。それもかなりの数である。リーダーらしいのがこちらの様子を見ている。問題なしと判断したのか、大人、子供、赤ん坊大小さまざまな個体が道を横切って姿を消した。若者らしいのや、ほんの子供、次のリーダ候補、母親の背中に乗った赤ん坊。子どもがコンクリートの壁に挑戦。飛びついては転げ落ちる。なんとも微笑ましくかわいい姿。頑張れ!と言いたくなる。ちょうどいい時間になった。今日の探鳥会はここまでだ。6年生はミニクラスだ。だからみんな仲良しである。そのことは探鳥会を通した短い時間でも分かる。最後の探鳥会を楽しんでくれたなら良い。
室林道への道をセンサスした。
①ジョウビタキ ⑨⑩⑭-⑯ニホンザル サルのポーズで記念写真
2024 11 24 室林道ラインセンサス
この日は、いろいろハプニングが多かった。悪い意味ではない。むしろ、良いことであるが。キツネがひっそりとたたずんでいた。キツネであることは直ぐに分かった。まずはあいさつ代わりの写真撮影。太い尾っぽと痩せた体。しかし、イメージにあるキツネよりも、のんびりとしているかのような様子が、微笑ましくも、可愛らしくも感じた。やがて、仮に彼としておこう、彼は、とぼとぼと歩き出した。それは、これからセンサスで進む方向であった。センサスで彼の後を付けて行こうか、もう少し先にまで行かせてやろうか、今回は後者をとった。曲がり角で再び止まったのを記念撮影。鳥の方では、ルリビタキの声が多く聴かれた。その中の2羽はハッキリと姿を確認できた。前日の寺の入林道でも鳴いていた。さらに、これもお気に入りの鳥のミソサザイ。地鳴きが聴かれた。ああ、やって来たねと言いたい気持ち。最後は、アオバトの声である。摩訶不思議な声の持ち主である。
⑥⑦キツネが出現! ③④ルリビタキ
2024 11 23 寺ノ入林道ラインセンサス
思った通り冷えていた。防寒が不足だった。歩いて体を温めるしかない。夏、ゼイゼイ言いながら歩く道をスイスイ進む。臨床を歩く小鳥を見た。暗い色から、クロジではないかと思う。双眼鏡で探したが駄目であった。多分そうだ。ヒガラの声(だと思う)を確認。自分にとってヒガラの地鳴きは難しい部類に入る。声だけでは確信持てない。姿を見たい。室林道でもヒガラの声を聴く。しかし、姿を見ないと安心できない。そんな季節が再び巡って来た。今日1番の驚きは、ウグイスの地鳴きを聴いたこと。あれほど少ないウグイスが、今の季節に確認できたのだ。何故?
明日はラリージャパン。通行止めの真ん中に寺ノ入林道はあります。
②の直線がラリーコース 右折すると寺ノ入林道
2024 11 23 駒場池
ふるさと公園から三河湖へと向かう途中に駒場池がある。せっかくなので立ち寄ってみる。池沿いの車道は頻繁に利用していて、車から眺める限りでは、ほとんど鳥はいない。車から降りて見るためには、車道とは反対側の未整備の方を通らなければならない。結構荒れ放題なのであまり通りたくはないのであるが(車が傷つく)、仕方がない、寄ってみた。キンクロハジロが10羽程度、マガモがほんの少し、と言った所か。昔の賑わいはどこに行ってしまった?。カモよりも陸上の鳥の方が面白そうだ。今度は歩いてみよう。
キンクロハジロとマガモがいたが、個体数はとても少ない。
2024 11 23 ふるさと公園ラインセンサス
門扉開閉の仕事を終えて直ぐに、再び駐車場へと向かい、そのまま公園の中をセンサスをした。仕事中は薄暗かったけれども、今は気持ちの良い朝日が当たっている。ヒヨドリの声が凄い。ここはヒヨドリ天国だ。2羽で行動している個体が多いがペアなのだろうか。それともただの知り合い?。ジョウビタキもかなり多そうだ。明るい場所が好きなジョウビタキだから、人の手の入った公園が気に入っているのかも知れない。シロハラの声を聴く。エナガの群れを見る。鳥の世界は既に冬季だ。
2024 11 17 御津海岸探鳥会
天気の女神は私たちに微笑んでくれた。そうとしか思えない。バスは23号線バイパスを通り、埋立地の工場の中を抜けて豊川右岸堤防に到着。目の前の海はべた凪。そこには無数の鳥たちが羽を休めていた。殆どが海ガモで、遠くの者は種までは分からない。近くにいるのは、キンクロハジロ、ホシハジロであった。きっと、スズガモもいるに違いない。なにより驚いたのは、これほどの近さで大きな群れを見られたことだ。例年、遠くに黒いすじくらいにしか見られない。首の長いのはカンムリカイツブリ。黒く帯の様になって移動中なのはカワウのようだ。数は見当つかない。子どもがスナメリを見つけた。私も、息を吐き出す水煙を見ることができた。イルカではなさそうだ。たまたまきて見られるとは、こんなことは滅多に無い。いつもは寒くて風が強くてと、長くいたいとは思わない場所なのであるが、今日はポカポカ陽気。風が無いと汗ばむ陽気なのだから恐ろしい。それでも次の工程がある。豊川河口を後にして日本列島へと向かう。こちらには、馴染みの深い音羽川の河口部がある。やはり河口部には魚が多いのであろう。先と同じような光景が広がる。海鳥の群れが浮かんでいた。種は同じである。私は、以前、ここでスナメリを見た。橋の上からの景色が気持ちよかった。飛び交う鳥たち。カモの仲間、トビやミサゴ、セキレイも鳴いていた。ここで探鳥仲間が増える。御津の人たちだ。何度かご一緒した方もいれば、初めて参加の人もいる。初めてでこのような条件で観察できるのは幸運の持ちだ。浅瀬では淡水ガモが見られた。多くは、防波堤に上がって日向ぼっこ。馴染みの、カルガモ、マガモ、オナガガモたちである。オカヨシガモの姿もあった。その中で一番嬉しかったのは、萩では絶滅したコガモを見たことである。ほんとに見なくなったコガモ。黄色い足がチャーミングに写った。お昼で御津の人たちとは別れた。思い思いにお弁当を広げる。一番の楽しみ。その後は、帰るまでずっと遊んだ。私は私で、先生と子どもたちの様子を見ながら微睡んでいた。最初の橋の上で、これまた珍しい人たちに会った。着ぐるみ姿を撮影しているのだ。キャラクターの名前は忘れてしまったが、オオカミっぽい姿であった。
快晴・微風・べた凪と絶好の探鳥会日和となった。野鳥たちにも沢山会えた。
②-⑤⑥豊川河口にいた海ガモ。 ⑯トビ ⑰カンムリカイツブリ ㉘㉘コサギ ㉛イソシギ ㉞カワウ
2024 11 11 室林道ラインセンサス
スタートでは降られるかもしれない怪しい天気であった。杖代わりのビニル傘を持ってのセンサスとなる。濡れている道の下り坂は滑りやすく、勢いよく歩くと尻もちを付く危険があるので、慎重に歩を進ませる必要がある。摩擦の大きい箇所を選ぶとよい。時間帯も良かったのか、色々な鳥が鳴いていた。先ずは、初確認であるが、シロハラが鳴いていた。一見するとウグイスのようにも聴こえる。(未だに間違えてる)もう一つの声があればなと思った。(ジュクジュクの声、シジュウカラとは全く違う)本家のウグイスも鳴いている。似てはいると思う。メジロ、ヒヨドリ、カケスも多い。時折、コゲラ、ヤマガラ、エナガも確認できるが、前者程目立たない。その中でも、さえずりはとても目立つので、ソウシチョウのさえずりが異次元に美しい。最盛期のさえずりとは比べることはできないが。葉っぱを見ていると面白い。黄葉と穴だらけの葉、鮮やかな緑の葉など。落ち枝にビッシリとキノコが生えていた。枯れ枝にキノコが生えて、それが落ちたものであろう。ようやくセンリョウの赤い実が目立ってきた。正月の花木である。もう2か月無い。
落ち着いた感じの景色に変化した
2024 11 3 茶臼山ラインセンサス
茶臼山を1周回すると7キロ、3時間くらいかかる。先月までは喘ぎ喘ぎ歩いていた。頻繁に足を止めていた。ところが、今日はすいすいと歩いてしまった。カメラの調子が今一つで、それに時間が掛かってしまったのは残念であった。紅葉の盛りと言う訳でもないのに駐車場は満車状態だし、バイクのけたたましい音が途切れることは無かった。それは許せるとして、風が強いのには困ってしまった。野鳥があまり姿を見せないのだ。特に茶臼山と萩太郎山の鞍部は強かった。少し下がった頃から風がおさまりだしたので、さあこれからと気合を入れる。それが禍したのか、ツルっとしたかと思ったら、みっともない格好で尻もちをついていた。カラ類を結構見た。コガラ、ヒガラといった高山の鳥もよいが、馴染みの、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ達にも会えれたら嬉しくなる。頑張っているなと言ってやりたい。ススキが真っ盛りの野原では、ホオジロが、両側に白いすじの尾羽をなびかせて飛び去っていった。さえずっていたらもっとよかったのに。ハシブトガラスが賑やかだ。追いかけっこもしている。地元でも、冬に入る前にひとしきり同じ行動を見る。カラスのみならず、トビも、大変な数が集まっているのをよく見る。何かのパフォーマンスに違いない。本格的な冬になるとアトリ科の鳥たちがやって来る。今は谷間にあたるのかなと思う。登りも普通に歩いて行ける。体力が付いたのか?最後の登りから見る景色が良い。牧場の緑が、少し赤くなった雑木林と良いコントラストとなっている。こんなところに家があったら最高だな。その牧場にいたのがニホンジカである。夏に見た赤っぽいのとはすっかり変わって、よく見るようなこげ茶色をしている。駐車場は一杯であった。停める場所が無くてそのまま出る車もあれば、枠外に停めるのもいる。そういえば、朝、登って来た時、大きなクラクションを鳴らして、無理やり抜いていった軽がいた。かなりのスピードであった。いい年のおじいさんだった。
紅葉が始まっていた
2024 10 27 ふるさと公園ラインセンサス
なにやら大勢の交通整理がいる。停める場所が決められていてそちらに誘導された。園内にはくまなくテントが張り巡らされ、何か大きなイベントがあるのは間違いない。それはすぐに分かった。大門に横断旗が出ていたのだ。ふるさと満喫まつり2024と書かれていた。祭りそのものはこれからで、開門と共に準備に入ったばかりのようである。それにしても気持ちのよい朝だ。たとえ野鳥がいなくても散歩だけで十分満足できる。結論から行くと、ヒヨドリとメジロばかりである。その中にわずかばかりの鳥、ホオジロ、モズなどがいた。冬鳥のジョウビタキもいる。さえずりをしていたのは、シジュウカラとホオジロの2種で、とても綺麗とはいえないが、今の時期にさえずってくれているだけでもありがいたいと思う。ホオジロは、繁殖期のピークのさえずりが終わり、夏を越して少し寒くなるタイミングで、もう一つのぴーくを迎えることは、以前から気付いていたことだ。姿ばかりではなく、鳴き声も野鳥を理解する上でとても重要であることを、師匠から教わった。それは、今度は自分か教える対象となる子どもたちと接するときにも常に意識しているつもりだ。師匠の事を書いた新聞記事を見たことがある。「彼は鳥の気持ちを理解している。」
爽やかな朝のバードウオッチングです。 ③芝生に何か掘り起こした痕が目に入る。イノシシか?
2024 10 26 寺の入林道ラインセンサス
ここに来るまでに2ヵ所の通行止め予告を見た。11月24日(日)ラリージャパン・・・とある。また、あのWRCラリーカーが疾走するわけだ。ユーチューブでも「リエゾン」と呼ばれる一般公道を、一般車両と一緒に走っている姿を見る。その景色には見覚えがあり、今まさに寺の入林道へ向かう道がそうなのだ。神社の幟立てに開催を示す旗が立ったこともあるが、今年は未だ出ていない。神様と一緒にしてしまう所が日本人らしいが、苦情でも出たのかな。それはよしとして、休日とあってバイク(自動・人力)が多かった。作手まで来るのにも500メートル登る必要があるので、人力のバイクの人たちにはお疲れさまと言いたい。その点、自動の人は楽なものだ。自分も自動の仲間に入るので偉そうには言えない。コース全般を通して静かであった。大きな声を上げる鳥がいなかったとも言える。それこそ耳に神経を集中させないとセンサスが叶わない状態なのだ。シジュウカラが鳴いた。コゲラとアカゲラも鳴く。そうしてる間にメジロが何羽か枝先を移動。聴き取り難かったがヒガラもいそうだ。混群の様相を見せ始めた。結局、全コースで鳥の姿らしいものを見たのはここ1個所だけであった。持参したカメラの露出がおかしかった。全て露出不足で、何も写っていない。代わりに以前に撮ったのを載せておく。
各種通行止め 伐採作業とラリー
2024 10 23 室林道ラインセンサス
あいにくの雨ではあるが、傘を差してやればよい、そう思って室林道へと車を走らせた。大した雨ではないので、ノート取りとか、カメラへの雨粒、などの心配は不要。通常通りのサインセンサスができた。一番多かったのは、意外と思われるかもしれないが、秋の南下行動でやってきたカケスである。なんせ声が大きい、鳴けば必ず耳に入るから個体数も伸びるのだろう。その他の小鳥ではそうはいかない。ジョウビタキなどの冬鳥はまだ確認できない。濡れた葉っぱがみずみずしい。そうして眺めると、雨のセンサスもまんざらでもない気がする。
ポツポツと雨粒がビニル傘で鳴る程度のものであった 霧に霞む景色も良い
⑨雨粒を撮ってみた ⑩サワガニがいた ⑪ソメイヨシノが痛々しい 凄い色だ ⑬ソメイヨシノが咲いている
2024 10 21 愛鳥クラブ羽根長根
今日は萩小クラブ「探検・愛鳥クラブ」に参加した。5・6時限を使っての、4年生以上が参加するクラブ活動である。上天気のもと、5名の児童たちと、担任の先生、私を含めた合計8名で、萩小学校を後にした。秋の青い空が広がる。心地いいいそよ風が日差しの強さを和らげてくれる。信号機を渡り山陰川へと出る。カワセミのポイントだ。今日は何と、往路と復路の2度、カワセミを見ることができた。滅多に無いサプライズに児童たちは大喜び。カワセミ相はこれだけでは終わらない。2つ目の山陰川に架かるオオイ橋でも、上流に向かって飛び去るカワセミがいた。多分、橋の下を潜って行ったに違いない。今日はこれだけでは終わらない。最終目的地の向山大池で、縁からダイブして漁をするカワセミを見たのだった。もうどれだけ偶然が重なればこのような事が起こるのだろう。信じられないよりも呆れてしまう。まだまだある。ノビタキのなっか姿を見た。ひたすら南下し、海岸線から先は休みなく飛び続ける。そんな大それたことを、鈴間と見まごうほどの小さなノビタキが成し遂げているなんて。児童に話す口調もついきつくなってしまうのは仕方ないか。初確認の種もいた。山の端から激しい羽ばたきで姿を見せたのはハイタカである。いよいよやって来たか、と思った。朝夕の冷え込みが本格的になってきた。北海道からは雪の便り。野鳥の世界も入れ替わりが着実に始まっていた。6時限終了時間に間に合うのが、今や自分にとっての1番の関心になってきた。無駄口控えてひたすら歩いた。
カワセミ・ノビタキ・ノスリ・ハイタカなど魅力的な野鳥に出合えた
①②カワセミ ③ノビタキ ④シマヘビ
2024 10 20 室林道・羽根長根
起きたときは雲一つ無い程の天気なのに、探鳥会が始まった時刻には厚い雲が空一面を覆っていた。参加者は5名。定員一杯ではあるが、2人は低学年。車1台で2ヶ所を回った。最初に校庭のことをお話ししたい。セグロセキレイのアルビノに再開したのだ。頭と顔が真っ白なのは変わらない。しかし、同一個体なののはずではあるが背中の所が相当黒っぽく見えた。後から考えてみると、最初に見たのは11月から今年の春先までであったので、冬羽を見ていた。今は10月で、夏羽を見ていることになる。冬羽、夏羽の違いが表れているのであろう。車で最初に寄ったのは羽根長根の田んぼだ。先々回の子ども探鳥会(9月29日)で見たノビタキを、未だ南下個体がいるのか、確認したいと思ったからである。スズメやモズはすぐに見つかった。しかし、ノビタキは、ぱっと見渡す(双眼鏡を使って)限りではいないようだ。半分諦めていた時、割と手前の畦で、バタバタと羽をバタつかしているのを見つけた。ノビタキ特有の動きだったから、直ぐに気付くことができた。皆も直ぐに分かった。未だ南下行動は続けられているのだ。向山大池でカワセミを探した。これも、前の探鳥会で見たカワセミの印象が強かったからだ。特定外来種の魚を釣ることに勤しむ人たちが糸を垂らしている。これだけ大勢の前に姿を現す勇気も無いであろう。次いで向かったのは、オシドリが飛来する新堤池。やぶ蚊防止のスプレーを入念に。坂道の途中からオシドリの姿を見た。池に到着すると、湖面のオシドリは気配を感じたのか、次々と羽音を立てて飛び上がった。そして、池を旋回し飛び去ったのだった。我々が去れば、どこからともなく戻って来るだろう。最後に室林道へと向かう。春の探鳥会では様々なさえずりが聴かれたコースである。ウグイス、キビタキ、センダイムシクイ、サンコウチョウ等であったと思う。今日はとても静かだ。本当に鳥がいなくなったかと思う程。大丈夫、鳥は沢山いるのです。少ない中でも確認できたのは、ウグイス、ヤマガラ、カケスなど。車に使う大きなシートを広げておやつタイムを始める。弁当もそうであるが、自然の中で食べるのは、おいしいだけでなく、ホッとする時間を持てるので、現代人はぜひ持つべきだ。ついでに言えば、バードウオッチングはとても癒し効果があるらしい。生活に疲れたら、バードウオッチングでリフレッシュをお勧めする。
1家族と先生&野鳥ガイド5人の探鳥会
①②ノビタキ南下の姿 ③-⑤セグロセキレイ(萩小校庭)アルビノ 背中部分は普通の鳥と同じ色になっていた。(部分白化と言えそう)
2024 10 19 茶臼山ラインセンサス
天気予報通りならば、ラインセンサスの後半は、傘を差さなくてはならない状況であった。そして、現実はその通りとなる。天気予報の精度の高さには目を見張るものがある。気象学の発展と共に、予報の精度に寄与しているのは、IT技術の進展なのだと思う。スパコンはとんでもなく能力が高いのである。そんなわけで、センサスのお供にしたビニール傘(杖にもなった)は最後に有難いものとなった。特徴的だったのは、カケスとハシブトガラスの声が至る所から聴こえたことだ。そして、共に同じ科らしく、似たような羽ばたきで森から森へと舞っていく姿を見た。2つ目は混群である。特に、コース終盤の地点、小鳥の森小屋では、エナガ、ヒガラ、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラたちが、蜂の巣を突いた時の状態であった。エナガなどは追いかけ行動をしていた。紅葉は始まったばかりであった。これから日を追って見事になるだろう。雨でも大丈夫なように、前日に入って来た雨靴を履いて歩いた。サイズや軽さも申し分ない。スマートなのがこれまた良いと自画自賛である。
紅葉が始ったようです。私には感じられないのですが、何ん箇所かパワースポットが有ります。古木も多く、2本の樹がくっ付いてしまったのも有ります。
㉞-㊶は仲の良い樹。もう絶対に引き離せません。ライオンズクラブの石碑も何か意味深。
野鳥も多くいました。①はエナガ(幼鳥のように見える)
2024 10 13 室林道ラインセンサス
上等の秋晴れ(秋をいつまで楽しめるのか?)、野鳥観察で至福の時間を過ごした。私はこれで十分。セミ時雨が止んで久しい。黄葉には程遠いものの、それでも秋はゆっくりとやって来ている。ジョロウグモの作品を眺めながら、これはと言うものはカメラに収めた。網にポッカリと大穴、これがまた面白くていい。センターに鎮座しているクモの体も見る価値がある。姐さんの着物の模様。虹色が出るような角度を狙って撮ってはいるが、ドンピシャのものは撮れた例がない。それでも最後に撮った赤色のはまあまあかな。カケスがあちこちで鳴いている。いずれも南下個体。春以来の再開となる。ウグイスの地鳴きも聴かれた。それ以上に、ソウシチョウは元気だ。さえずりをいつまでやるのやら。ようやく見たのがアサギマダラ。今年はこのまま見られないかと心配であった。アゲハチョウやシロチョウ科のチョウたちとは飛び方が違っている。ゆっくりと羽ばたき、ふわふわとしているようだ。体に毒を持ち、野鳥から捕食される心配がないからなのであろうか。もう一つ、ちょっと変な声が聴こえてきた。大きなものが動く。頭と腕が分かる。ニホンザルが発した声だったのだ。
⑤-⑧、⑩-⑭、⑯⑰ 秋に多いもののひとつにクモの巣がある 形・色ともに見ごたえがあると思うのであるが
③アサギマダラ 今年見たのは2度目、1度目は、7月に萩小学校。
⑨ニホンザル
2024 10 11 宮路山
子どもたちに加えて、先生と父兄も参加した。総勢で16名となる。探鳥会の人数としては上限かも。ひまわり農協に駐車させているので、今日は平日であることを忘れてはいけない。既に終えた、運動会の振替休業日なのだ。来店者の邪魔にならないよう気を付ける。音羽川添いに進むと、明後日が大祭の杉森八幡社にでる。大祭が終わった翌週に行われる歌舞伎芝居の準備が進んでいた。回り舞台を見下ろすように配置された観客席の小屋を造っているのだ。これを小屋掛けという。丸太で柱を立て床をふき、屋根には青竹で作られた骨組みができる。その上にブルーシートが掛けられたら完成。雨や夜露を凌げるわけだ。すぐに宮路山登山道へと向かう。急な階段道を息を切らせて登って行く。そこの広場にあるのが忠魂碑。地元萩にもある。子どもたちは意外にも知らなかった。音羽川で見たのがカワセミでなくイソヒヨドリである。この鳥は、近年増えつつあると思う。どのような環境にも適応していけそうな鳥であろうと思っている。森の中では鳥を見る機会が少ない。もっぱら鳴き声である。特別変わった鳥はいない。ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラ、ハシブトガラスがいた。山頂は標高362メートル。独立峰なので景色は最高だ。特に南に広がる三河平野と三河湾は一見に値する。もう何回この景色を眺めたことだろう。弁当を広げてにっこりする顔を見るとこちらの方もにっこしてしまう。全員の顔を撮るのが恒例行事である。その弁当に惹かれて来たのか、上空で輪を描くトビの姿。老夫婦と同じテーブルで弁当を食べた。ここで食べ物を盗られてしまったそうだ。後ろからこっそりとやって来るとのこと。毎週、岡崎市から来られるとのこと。下山は宮道天神社コースをとる。2つの神社を通るというのも面白い。山の名前にも宮が付いているではないか。麓にある福祉保健センターで休憩する。常と違って平日探鳥会なので、トイレも利用できありがたい。山から流れ下りる水を集めた小さな川があって、いつも川遊びをして帰ることにしている。前日までの雨で水量はあるが、安全面では全く問題がない。すなで池を造ったり、カニを探したりして思い思いに楽しんでいる。子どもは遊びの天才とはよく言ったもの。時間をうまく配分するのはもう慣れている。大体思い通りに進められる。田んぼが見えるとノビタキを探す、その癖が染みついてしまった。そして、その甲斐あって、1個体見つけることができた。良かった。最後は、赤坂の街で見つけたメジロ。柿をついばんでいたが、我々が近くで見ていることにも頓着する様子もない。実に可愛かった。メジロは萩小の中では4つの特別な鳥。クラス別けとは別に縦割り班を4つ作り、それぞれに鳥の名前が付いているわけだ。メジロ・カワセミ・オオルリ・キビタキの名前が付いている。その中で、身近で親しみやすいのはメジロだと思う。姿も可愛いし声も可愛い。5分遅れでお母さんたちの待つひまわり農協に到着。怪我無く、無事に行って来れたのが何よりだ。
秋の空の下、色々な環境の野鳥を楽しんだ。
①②柿の実をついばむメジロ 音羽川から杉森八幡社へ 宮路山登山道を登る 楽しいお弁当を食べたら 最後は川遊び
2024 10 6 羽根長根ラインセンサス
ノビタキの時期を逃していては、何のための野鳥観察か。夏の田んぼは稲ばかり。ついつい遠ざかっていた。そして、稲が収穫され鳥たちの姿が見られるようになり、季節の変わり目の今、ラインセンサスをやる条件はしっかり整っているのだ。田んぼに行かねばならぬ。室林道をそのまま突っ切って長根地区に下りる。林道は枯れ枝だらけ。フロアから枝のこすれる音が聞こえるとすぐストップ。枝を引き出してスタート。民家を抜けると目的地の田んぼが広がる。約1時間かけてセンサスを行っている。目的のノビタキだけでなく、センサスの名の通り、目に入る鳥全てを記録しているつもりである。大きくて白い鳥のダイサギは最も目に付く鳥である。ダイサギが2種いることは最近まで知らなかった。留鳥とばかり思っていたが、夏鳥の亜種と冬鳥とが交互にやって来ていた訳であった。従って、今見ているのがどちらなのかは、自信をもって言えないのがもどかしい。セグロセキレイやモズの姿もある。暮を成しているのはスズメとカワラヒワだ。色と声とで区別は容易だ。忘れてくれるなと鳴くのはケリだ。3羽が田んぼのあちこちを飛び回る。畦にはヒガンバナの赤と、ツユクサの青と、ノボロギクのクリーム色の花が咲き乱れる。どの花も綺麗だ。ノビタキは2羽確認できた。それよりも、思ってもいなかった野鳥に出会えたのが嬉しい。特別な鳥ではない。ヒバリが鳴きながら田んぼから飛び立っただけの事なのだが、予想外の事ととして印象に残った。
田んぼの中でひっそりと佇むダイサギ、草むらに隠れるように南下するノビタキ、どちらも秋の羽根長根の風物詩である。
①アオサギ ②-⑧㉘ダイサギ ⑨⑩ノビタキ ⑪セグロセキレイ ㉘カワラヒワ
2024 10 6 室林道ラインセンサス
セミの鳴き声が止んで、室林道に静けさが戻って来た。このことは、野鳥センサスをやる身にとってとても朗報なことである。山の野鳥観察のほとんどは鳴き声が情報の大部分を占めることは、ほとんど間違っていないと思う。野原や海岸では目視がほとんど全て、それこそ、高性能な光学機械が物を言う訳です。しかし山は違う、耳が頼りです。集中力も試されます。ヒヨドリとオオルリとを同じに扱わなくてはいけないのです。お気に入りの鳥が鳴いたからと言って、そればかりに気を遣うわけにはいなかい。カケスが盛んに鳴いていた。山から下りてきたわけですが、渡りと言ってよいのか迷っています。伊良湖の先端から対岸に向かう姿を見ているので、渡りと言っても差し支えないと思っています。もうひとつお気に入りのものが沢山見られて幸せでした。クモと言うと眉をひそめる人が多いのでは。ジョロウグモが巣を造っているのを見ました。その巣は小宇宙のような形をしていて、真上から、真横から、斜めから、それぞれが、天文書で見る銀河宇宙を彷彿とさせるのです。太陽光との角度の関係で虹色も見えます。何とかいい写真を撮ろうと思っているのですが、センサスの歩みを止めるのは良くないと、ハット思い返して、先に進んでいます。
2024 9 29 羽根・長根方面
子ども5人とおとな3人で羽根・長根方面を探鳥した。曇り空が幸いしたのか多くの野鳥を観察できた。山陰川を渡る時にカワセミを確認。堤防から突き出した竹のようなものの上にちょこんとのっている。写真で見てもとても小さく普通の鳥ならば種の同定も困難なのでは。神社を右に見て進んでいく。モズとキジバトが目に付いた。少し前まではイソヒヨドリが目立って鳴いていたが、今はキジバトとモズが主役となりつつある。羽根・長根の田んぼが見えてきた。所々に白く見えるのはダイサギだ。図鑑によると亜種のダイサギ(チュウダイサギ)である。秋本番になる頃冬鳥のダイサギが現れる。留鳥ということで同じ種がいるのかと思っていたがそうではなかった。田んぼではノビタキを探した。畔の草刈りを終えていない所が狙い目。今年はそういった場所がとても多い。目を凝らし(肉眼)探す。肉眼の最大の利点は視野が広いことである。短所は当然ながら小さく見える事。たまたま肉眼しか持ち合わせていないので、怪しいものは参加の人に伝えて確認してもらう。そんなやり方で数羽のノビタキを見つけた。スコープで捉えた姿を皆さんに見てもらう。その役はベテランの域に達した児童のものだ。そろそろ「お腹がすいたー」の声が出始めた。旧家場所は長根の大池とした。人目に付かないし景色も良い。運が良ければカワセミにも出会えるかもしれない。そのかもが現実のものとなった。初めに声が聴こえた。それから姿も現した。池を1周するように飛んでいた。その綺麗な事。言葉では言い表せない。どうしてもありきたりの表現になってしまう。付近にクリの毬がお落ちていた。実がぎっしりと詰まっていた。田んぼの畦にはヒガンバナガびっしりと咲いている。ノビタキの背景にはヒガンバナ。もう言うことは無い。
①カワセミ ②キジバト(オスがアタック、メス逃げる?) ③④ノビタキ南下個体 ⑪ヤモリ(家出?) ㊿-55得体の知れないもの 59-63カマキリふらふら
2024 9 23 室林道ラインセンサス
昨晩はずいぶんと涼しく過ごしやすかった。そのまま今朝を迎えたようだ。鳥を見に山に入る時のスタイルは虫対策だ。長袖がちょうどよい気温でやる気もでる。特記事項があった。カケスがやってきたのだ。秋の南下の一陣であった。さらに本格的に冬鳥が来るのを先取りしているようだ。ヤマガラやシジュウカラも見られた。特にシジュウカラはさえずりも交えていた。気を付けて見ているがアサギマダラを身だ確認できていな。1度だけ萩小学校で見たが、それは夏休み前の事であった。今年の夏は例年よりも一層気温が上がった。そのおかげで蚊も少なかった。それは結構なことではあるが、アサギマダラがなかなか見られないのに関連があるのかも知れない。
何でもインスタ映えするものである
2024 9 21 寺の入林道ラインセンサス
今日は谷間だったのか?つまり鳥が少なかったと言うこと。カケス、ヒヨドリ、メジロ、アカゲラ、キジバトがその全て。その中でヒヨドリの20羽ほどの群れが目立った。ヒヨドリも移動している。他所から渡って来た個体なのかもしれない。秋が深まれば南下行動が加速する。今日のヒヨドリはその一端かもしれないのだ。親子のシカと出くわした。ピッと鋭い声を残して沢を下って行った。標高600メートルは伊達ではない。随分と過ごしやすかった印象だ。
秋の雰囲気が漂ってきた
2024 9 21 ふるさと公園ラインセンサス
8時からセンサスを開始した。駐車場はもう半分は埋まっている。やはり、朝の涼しい時間に利用する人が多いようである。相変わらずヒヨドリの声が一番よく聴かれる。次いで、メジロが多いか。両者はほとんど差がないように感じた。珍しかったのは、サンショウクイが2羽見られたことだ。つがいのように仲が良く、色も少し異なっていたので、たぶんオスとメスであろう。公園のメイン道路に沿ってヒガンバナガ咲いている。間違いなくこれらは植えられたものであろう。一度植えたなら後は何もしなくても毎年咲いてくれる、そう思うのは素人考えであろうか。肥料を施しているのかしらん。その花に一匹のアゲハチョウが止まった。シャッターを押すタイミングを見計るのが結構難しい。結局学習通りに撮る。それは、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるである。
①サンショウクイが
2024 9 16 茶臼山ラインセンサス
先週は用事だらけであった。自分へのご褒美に茶臼山へと向かう。ひと月で一番嬉しい日である。その割には起きる時間が遅かった。疲れが溜まっていたに違いない。豊根ヴィジターセンターに8時到着。気持ちの良い朝だ。キセキレイが目の覚めるようなきれいな声で鳴いてくれた。登山道を登る道中がまた楽しい。どんな鳥が見られるやら。気温は24度である。今の時期としては格別なのでは。7キロの茶臼山周回路を時計回りに歩く。いきなり滅多に見ない鳥が出た。それも2種。アオサギとカワウと名前を言えば「なんだ~」と思われることだろう。しかし、ここは標高1300メートルなのだ。確かに、ここには彼らが好む池もあるし沢も多いのでいても不思議ではないが、毎月通ってもそう頻繁にはお目にかかれない鳥だ。道中で個体数の多い鳥は、声で判断すると、ソウシチョウが1番だろう。ウグイスも鳴いている。地鳴きは声が小さいし、単独でいることが多いので、ソウシチョウに比べると見つけにくいのは確かだ。しかし、道中で多くの鳴き声が聴かれたのは嬉しかった。茶臼湖の近くでゴジュウカラのさえずりを聴いた。それも大きな声を。「フィフィフィ・フィフィフィ」と他と間違えようもない声を聴いた。半分ほど来たところで厚い雲が広がって来た。正午過ぎから雨の予報になっている。その正確な予報には驚くばかりだ。ススキが風に揺れる。ノギクの白い花が咲き誇るのももうすぐそこだ。
快晴から雨模様まで 7キロを3時間でセンサスした。
④-⑦アオサギ ⑰エサ(虫の一部)を運ぶアリ ⑲キジバトとカケス ㉘㉙何とも可愛いいキノコ
2024 9 13 室林道ラインセンサス
用事を済ませて室林道に向かう。ツクツクボウシが最後の夏を惜しむように鳴いている。野鳥観察には邪魔になるが、自然の中の野鳥なのだから、セミの声が無い夏の室林道を要求するのはお門違いというもの。メジロのようなエナガのような声がした。しばらく留まっていると声の主が見えてきた。エナガは形でわかり易い。人腹の兄弟姉妹なのか。双眼鏡で確認すると成鳥とは色が異なるので幼鳥だと思う。ウグイスの地鳴きがする。ソウシチョウも地鳴きが殆どで、さえずりをしていたのは、センサスの最後に聴いた1個体だけであった。オニヤンマ、シオカラトンボを見る。チョウもいるが名前が出てこない。狙っていた渡りチョウのアサギマダラは見る事ができなかった。もしやと思い注目したのがヒガンバナ。彼岸には必ず咲く律義さが良い。場所は毎年決まっている。そのあたりを探すと、あったあった。1本だけ見つかった。そして、律義者らしく真っ赤な花を見せてくれていた。形が少々崩れているが問題は無い。アオゲラの突然の奇声には驚いた。奇声とは失礼!
2024 9 8 観音山方面
子どもひとりとおとな5人の変わった構成の探鳥会となった。別に構成比にはこだわっていないのでいつもの通り進めて行く。初めて参加する人は朝早く遠くから来てくれたことが分かった。個人情報に属すると思うので具体的には言えないが、凄いと思う。ただただ感心し、少しでも良かったと思ってくれたらと願うばかりである。あとの人達は何度も参加している。だからと言って疎かに扱うことはしないが、どうしても、気持ち的には前者の人を贔屓にしてしまう。ただ、そのことはおくびにも出さないつもりだ。学校の付近で最近、イソヒヨドリのつがいか家族が飛び回っているのを見る。それらの個体が今日も現れた。さえずりも交えているが、スコープで見る限りは成鳥の青色をしていない。オスの若鳥なのかもしれない。校庭の隅を歩いていたのはハクセキレイ。久しぶりにハクセキレイを見た。リラの前を抜け川沿いを歩く。キセキレイが水辺で腰を振っていた。メンバーには川面から目を離さないように言う。カワセミがいるかもしれないからだ。そしてそのようになった。先頭を歩いていた先生が見付け大声で皆に知らせた。残った人の目撃したか否かは正しく運である。6人中3人は見て3人は見られなかった。私は見られなかった方の仲間入りをした。心の中で贔屓した人は見られた仲間に入った。考えが俗っぽいと思うがカワセミが見られると雰囲気が変わる。気持ちがハイになるのだ。だからカワセミは有難い存在だし人気も一番なのである。校門から入った通路はレンガ風になっていて、灰色がその色なのだが、一部は黒っぽいレンガが生みこまれていて、その形がカワセミなのである。萩小の子が最初に覚えると鳥がハシブトガラスとハシボソガラスである。あわせて鳴き声も覚える。ハシブトガラスはカーカー、ハシボソガラスはガーガーと教わる。まさにその鳥がいた。稲刈りの終えた田んぼが広がる。ダイサギ(亜種チュウダイサギ)が餌を採っているのを見た。かなり上空なので気づくのが遅れたがコシアカツバメ・ツバメ?も舞っていた。前に戻るが、田んぼから異様な声が聴こえた。それは、ヘビに捕まったカエルの声であることが分かった。大きなヘビがとぐろを巻いていたのだ。コゲラの羽が落ちていた。部位の違い、色の違いを確かめることができた。換羽で抜け落ちたのであろう。今日も日なたはかなりの暑さである。できるだけ日陰道を選んで進んだ。周りから見難い所に腰を下ろしてもぐもぐタイムとした。この時間が一番うれしい。色んな話で盛り上がる。そうこうしているうちに時間となった。朝と同じ道を学校へと戻る。そこが相変わらず日陰になっているからだ。遠くから来た人は駅まで送ってもらい電車で家に帰ると言う。はたして、手間をかけ参加していただいたのに見合うもてなしが出来たのだろうかと思ってしまった。間違いなく否であろう。
ジャルダンリラ付近を歩く 山陰川ではカワセミを見た。
2024 9 2 室林道ラインセンサス
台風10号は熱帯低気圧になり東海地方を北上。降り続いた雨も上がったので、何はともあれ室林道に向かうことにした。林道はツクツクボウシの大合唱で、これは鳥の声を聴くのは大変だと瞬時に思った。姿を探さないといけない。センサスでは目視が有効だと思う。姿・サイズ・鳴き声をトータルで見て、種名を決めていく。いちいち双眼鏡で姿を追っていてはセンサス所ではない。第一間に合わない。複数の種を見分けて、およその個体数を割り出すのは、未だに出来ていないし、至難の業だと思っている。メジロが最も大きな群れであったが、センダイムシクイの姿やコゲラの声もしていた。ヤマガラやシジュウカラも時々鳴いていた。ソウシチョウはさえずりと地鳴きの両方を確認する。ウグイスは1個体だけ地鳴きを聴く。アブラゼミが羽をバタつかせて道ばたに転がっていた。やがて息が絶えるのだと思うと、感慨深いものがある。あらゆる生物には必ず死が訪れる。自身の事を思ってしまうのは自分だけではもちろん無いだろう。
時間の制約もあり写真におさめる枚数も極く少なくなってしまった。
2024 8 25 室林道
5名で探鳥会をした。まずは1台に全員が乗って室林道へと向かう。最近は、夜になると雷雲が発生し雷鳴が轟くことが多い。濡れた林道は注意が必要だ。坂道は、特に下りは、思いっきりスリップするからだ。落ち葉や枝が積もっている所を選んで歩くと滑りにくい。昨日のラインセンサスでは沢山見られた。うって変わって今日は静かだ。まともに聴かれるのはソウシチョウばかり。後は単発で聴こえるのを待つ。メジロ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、アオゲラ、キジバトが鳴いていた。野鳥が少ないと外に目が行くのは仕方がない。特に子供にとっては辛い。運よくいつものようにクモの巣が目に入った。銀河宇宙のように輝いてみえるのだ。本物の銀河のように、見る角度によって丸かったり楕円で会ったり紡錘状であったり。宇宙を旅行しているみたいだ。更に嬉しいのがその色である。これも、目の位置を変える度に虹の色が現れるのである。秋は特にクモの巣が多いと思う。こんなに綺麗なものもそんなに無いと思っている。もぐもぐタイムをやる。腰を下ろしお菓子の袋を広げる。平地では考えられないほど涼しくて気持ちが良い。贅沢なひと時を過ごした。
萩小→室林道→萩小。
①イソヒヨドリ(萩小) ②-⑤クモの巣銀河 ⑭カマキリ ⑮アキアカネ(萩小 見事に真っ赤)
萩小→室林道→萩小。
①イソヒヨドリ(萩小) ②-⑤クモの巣銀河 ⑭カマキリ ⑮アキアカネ(萩小 見事に真っ赤)
2024 8 24 室林道ラインセンサス
昨夜の雨で気持ちの良い朝が迎えられたようだ。鉢への水遣りも省いて室林道へと向かう。念のために、杖代わりのビニル傘を持って歩きだす。換羽に入っているので声は少ないしツクツクボウシの声が大きいので目視中心に進めた。ヤマザクラの並木が一番の狙い場所である。様々な野鳥がそこで採餌をする。センダイムシクイ、メジロ、エナガが群れている。大きなのはヒヨドリだ。シジュウカラは鳴きながら、ヤマガラは地上付近で、それぞれの場所で餌を取っている。サシバの声を聴いたが、もう3回連続である。9月終わりから10月にかけて、近隣では渥美半島伊良湖岬で、サシバの渡りのショーがある。ソウシチョウは相変らずさえずりをしているが、ライバルであるウグイスはさえずりを止めていた。予定どおりの行動である。夏鳥はもちろんここにいるが、ほとんど鳴かない。さえずりは全くない。地鳴きは聴かれるのであるが、今日はサンコウチョウが鳴いていた。室林道を離れるのは10月くらいか。ヒノキ林を霧が蔽っていた。爽やかでもあり幻想的でもある。虫にも目を向ける。渡りチョウで有名なアサギマダラを探したが残念ながら今日は駄目であった。
野鳥のカウント(センサス)の合間に、色々な物に面白い形を見付けようとした。必然的に往路よりも復路での楽しみとなる。
①⑤⑥岩の色や地衣類の模様、節理などが模様となる。⑥はクラックが広がり崩壊も近い。 ⓻⑧⑩は霧の美しさ ⑨マムシグサの実の断面は六角形
⑪⑫⑲は樹皮の面白い形 ⑰最近切られたソメイヨシノの切り口の色、血の色を連想する ⑯-⑱クモの巣は一番のお気に入り対象物だ
2024 8 19 寺ノ入林道ラインセンサス
腰と相談。2時間歩くけれども大丈夫?多分。幸い曇り空で暑さは感じない。傘の携帯もいらない。鳥の声はアブラゼミやツクツクボウシの合唱にかき消されがちになる。ヒヨドリとコゲラとアオゲラが鳴いた。声がそろそろ欲しいなと思うと彼らが答えてくれることが多い。ありがたい存在なのだ。確認できた個体数は多くないが満足している。スタートが正午、それに、繁殖期も終わり、などの条件を考えたらそうばんばん鳥が見られたら不自然でもある。意外なのはヒガラのさえずりだ。まるで繁殖期のように聴かれたのには驚いた。林道を疾走するオニヤンマが美しい。それと較べると、バッグにぶらさげげられたオニヤンマ(スズメバチ対策)の偽物感を切実に感じる。この地の不思議は、どこでも聴かれるウグイスをほとんど感じないこと、と思っている。今日は当然のようにいなかった。鳥のセンサスをするためにはキョロキョロする。その脇見をしている合間に見えたのが子どものニホンジカである。ピョンピョンと安心距離まで離れてこちらの様子を見ている。(写真)ウグイスは滅多に出合えないけれども、ニホンジカの声や姿は珍しくも何ともないのである。
セミの音楽で鳥の声が聴こえない? ⓻ニホンジカのこども
2024 8 19 ふるさと公園ラインセンサス
仕事の中でセンサスを行った。仕事への影響は全くない。10分ほど帰宅を遅らせるだけである。ツバメは巣立ちビナとそれを見守る親鳥の姿をみていたのであるが、今朝はまったくいなかった。カワセミが一声鳴いた。緑の葉陰の中から聴こえる声はメジロ・ヒヨドリたち。運転中は無理出るが、歩く工程ではちらちらと覗いてみる。ヒヨドリは2羽のつがいで、メジロは葉っぱと見間違えるような格好なので、じっとしている時は分かりにくいものです。時々さえずりをするが以前よりは減っているようだ。繁殖期も終わりということか。道路に下りていたのはアサギマダラ。渡りの中の一休みであろう。真夏は草花もくたびれている。ただ、ヒマワリだけは元気である。
朝景・夕景
2024 8 11 室林道早朝探鳥会
8月は1時間早く探鳥会を開始している。昨年から以前のやり方を復活したのである。理由は健康を考えての事であることは言うまでもない。それに、早い方が野鳥に多く出会えるのも理由だ。今日は児童と二人して林道を歩いた。常日頃から歩いている場所をそっくりそのままやったのだ。注目点を子どもに話した。ウグイスのさえずりは、お盆を境に、急に止んでしまうという実績がある。まだお盆前ではあるが、今日の2時間の間、どれだけのウグイスのさえずりがあるだろうか。全くゼロかもしれない。今日の記録は、今までのものに重なり、ウグイスを初めてとする野鳥たちの様子を映すものとなる。そのような意味のととを話しながら歩いた。鳴き声だけの記録もたくさんある。むしろそちらの方が多い。サシバの声が聴こえた。「サシバだ!」児童は、直ぐに図鑑を開きサシバを探す。「タカなのか。」「そう。」そのような会話であったと思う。しかし、ひとつのことに没頭するのは良くないと話す。ラインセンサスは、一定の速さで歩き、同じような感度で鳥を感じ、淡々と記録していくのが大切であることを強調して行く。サシバの次はアオゲラであった。けたたましい声だ。すぐさま、図鑑からアオゲラの姿を見出す。隣の、ヤマガラと、見分けが付き難いなどを知った。折り返し点からは、ウグイスの声が一番の関心になった。往路では聴かれなかったが復路のどこかで鳴くのか?「できたら鳴かないで欲しい。」と私は言った。結果は私の願いが叶ったようだ。
ふたりの探鳥会。後継者になって欲しい感一杯!
2024 8 10 茶臼山ラインセンサス
頑張ったおかげで、朝の7時半頃には豊根村ビジターに着いた。これから野鳥を見ながら山頂へと向かいのであるが、これが、何度経験してもわくわくするのである。正確に言うと409回目の観察となる。8月に入ると気になることがある。鳴禽類の最高位と言っても差支えないであろうウグイスのさえずりの止むタイミングのことだ。まずは今日の結果を見てみたい。ウグイスは盛んにさえずりをしていた。しかし、繁殖最盛期と比べるとどうなのか、とは思う。むしろ、ホオジロが目立っていたように思う。さえずりだけでもかなりある。地上で採餌する姿もあった。夏鳥は静かになっている。わずかに確認できたのは、サンショウクイとセンダイムシクイばかり。そうそう、カッコウが鳴いていた。スタートして忘れ物に気が付いた。コンビニで買った朝食・昼食のパンとお茶。お茶を車に忘れた。これはショックである。戻るには気が付くのが遅すぎた。幸い平地の酷暑はここには無い。我慢だ。2台のスポーツカーと何度も出会う。なにやら行ったり来たりしている。エンジン音はまだしも排気ガスに閉口した。スタート、登り、長い下り、長い登り、緩やかな下り、ゴール。およそ7キロメートルのセンサスコースをひたすら歩く。なにやら苦行している様にも思えてくる。しかし止めることができない。まだ気持ちは前向きだ。牧場のふちを額のように縁取る木々がきれいな絶景?ポインと来た。何かおかしい。緑の牧場が汚れている。その正体は沢山のシカであった。シカが草を食べていたのだった。こんなに多くのシカを見たのは初めてだ。
野鳥から獣まで盛りだくさん。 ①ホオジロ ②③ハシブトガラス ⑩⑪-⑭ソウシチョウ ⑲アカゲラ ㉒カケス ㉖㉗ニホンジカ ㉗ハシブトガラス
2024 8 3 室林道ラインセンサス
早朝の涼しい時間にと頑張って見たが既に7時近くになってしまっていた。今朝は近隣の夏祭りの号砲花火が盛んに鳴っている。これも嬉しい夏の風物。鳥の観察に邪魔になるなんて言ってはいけない。ウグイスはまだまだ元気のさえずりをしている。しかし、地鳴きも頻繁に聴かれるようになってきた。夏鳥の鳴禽類たちはほとんどさえずりをやらなくなっている。突然の声で驚かせるのがホトトギスだ。遠くで鳴いていたかと思うと、突然直近で大声を張り上げる。予測しがたいので録音機の操作が1テンポ遅くなる。録音開始した途端うんともすんとも言わない。全く意地悪だ。微かに聞こえているサシバの声。先ほど上空を横切ったのがやはりサシバであった。夏のタカとして飛来しているはずなのに今日見たのが初確認個体であった。再び鳴き声が。前よりもやや大きく聴こえる。うまく録音できているとよいが。
目を皿にして写真ネタを探す
⑥⓻クモの巣虹色を表現したいが? ⑨⑩模様の面白さ ⑪オレンジ色の虫が! ⑬甲虫が! ⑫朽ち果てたオオルリの巣箱 ⑭できた頃の姿 2009年撮影 ⑮営巣もされていた マイフィールドノートへリンク
2024 7 28 鳥川ホタル学校
連日の酷暑。探鳥会の運営もこの暑さを考慮に入れない訳にはいかない。今日も暑くなる。安心と不安が半分半分の心持である。安心要素は標高と林間道であること。不安要素は勿論それでも厳しい暑さである。終わってみると若干前者寄りに傾いてくれたと感じた。しかし、子供は無論、大人たちへのダメージも残った探鳥会であったと思う。ウグイス、ヒヨドリ、メジロ、カワラヒワなど、数は少なかったが、半面では少ないことが、後から振り返る時には記憶に残りやすい良さも出たように思う。森の中を歩くことは滅多に無いが、爽快な気分を味わうことができた。この時ばかりは暑さを忘れられた。ホタル学校に着くと、夏休みのためでもあろう、車が結構止まっていて、旧鳥川小学校を利用して作ったホタル学校の中には、幾組かの親子の姿が見られた。探鳥会の参加者には先生も多数いるので、先生の目線で話す会を聴くのは興味深いものだ。ここで書くのは語弊があるといけないから止めておきたい。のんびりとお菓子タイムも考えていたが、多くの親子連れで場所の確保ができなかった。また、展示の見学にも時間を取ってしまった。帰途に就いたのは30分オーバーとなってしまった。
ホタル学校の展示素晴らしかった。..
2024 7 27 寺の入林道ラインセンサス
午後からセンサスを開始した。それでも標高が500メートル以上はあるため、随分と歩きやすいことは確かである。野鳥が暑さで鳴かないのではと心配したが、大体予想通りの結果となった。もっと考えて行動しなければと反省している。それでもできるだけ丁寧に記録をしていった。ヒヨドリが圧倒的に多いが、少数の中には魅力的なのも混ざっていた。ヒガラのさえずりは平地では聴かれない。さすがと思った。サンショウクイは平地でも生息域を広げているが、野鳥観察を始めた30年前には、ここまでやって来てようやく姿を見たくらいであった。ここはウグイスがほとんどいない。ライバルのソウシチョウもいない。一風変わった場所である。
日陰と日向が均等に現れる。無意識に、早く日向を過ぎようとしてしまう。
2024 7 23 茶臼山ラインセンサス
早く家を出ようと頑張ったのであるが、結局、豊根ビジターセンターに到着したのは8時近くになっていた。40代の頃に1度だけ車中泊を経験した。何とも物騒な感があったので、その後は、午前2時起きで対応していた。しかし、必ず反動があって、帰宅時に睡魔に襲われ、何回かの仮眠を余儀なくされてきた。いまはかなり図々しくなっているので車中泊も好いと思える。最初に聴こえたのはミソサザイ。幸先が良い。ウグイスとソウシチョウのさえずりは、声量があるので黙っていても聴こえてくる。それ以外の鳥では、ホオジロとカワラヒワが目立っていた。ホオジロは、道に沿って立っている電線でさえずりをしている。3時間半のコースで途切れる事なく鳴いていた。カワラヒワも多かった。カワラヒワへのイメージは、冬季に田んぼで群れる鳥ということだと思うが、繁殖期には山に入り、他の鳥と一緒になって生活しているのだ。歩道の落ち葉を掻き分けている姿を、コースのいたる所で見られたのだった。同じ黄色い鳥にキセキレイがいる。今日は全てカワラヒワであった。長野県側で子どもたちの歓声がした。木登りをしたり、滑車で空中を飛んだり、年齢に応じた遊びをしていた。とても良い。コースの気温は28度であった。平地では6・7度は高いのでは。標高1300メートルの威力。強めの風も心地よかった。子どもの声のバックにカッコウが鳴いていた。ああ高原だ~。
1300メートルの高原は28度という快適な気温。
⑮上河内岳・茶臼岳・光岳 ⑯赤石岳・兎岳・聖岳 ⑰北岳・間ノ岳・塩見岳 ⑱仙丈ケ岳 ㉝-㊱シジュウカラ ㊲ホオジロ
2024 7 22 室林道ラインセンサス
用事の前に室林道をひと歩きした。探鳥会とはだいぶ様相が違う。通常の状態に戻っていた。1日の違いがこんなにも違うのかと思う。何があるのだろうか。ウグイスは相変らずではあるが、地鳴き個体がちらほら現れるようになった。たぶん1か月後にはさえずりは聴かれなくなると思うが、さえずりも地鳴きも、最初に聴いた時には新鮮に感じるものだ。それはウグイスだけに限らない。ここにきて夏鳥のさえずり個体がグッと減った。オオルリ、キビタキは全く聴かれないし、個体数の多いセンダイムシクイもかなり減ってきた。割と鳴いているのはホトトギス、サンショウクイだ。両者ともお気に入りの鳥である。正直に言うと、クモの巣の虹色をうまく撮ることに苦心した。なんとも言えない美しさだと思う。
今回は光が主役。 ①②アオゲラ ➈-⑬お気に入りの構図、クモの巣に光が当り虹色に輝く。
2024 7 21 室方面
室の田んぼを歩く計画ではあったが、熱中症を考え全く違うコースに変更した。移動は涼しい車で行い、3か所をぐるりと回った。最初は倉地区の山陰川でカワセミ狙い、羽根の田んぼでサギ、最後は室林道を考えた。山陰川ではセグロセキレイとカワラヒワがいた。川原の石ころをちょこちょこと歩いている。スコープに大きく映し出された姿をスマホにうまくおさめようと苦労している姿が微笑ましい。こういった作業は小学生の方が格段に上手である。隣の田んぼの稲の穂が随分大きくなっていた。電線に止まるツバメもスマホ写真の対象となった。車で数分、羽根の田んぼ道に停める。梢にダイサギの姿を認めたからだ。2羽いた。大きな鳥のそばには小さな鳥もいる。セッカの特徴あるさえずりを覚えた。最後は室林道。長根側から入って行く。ひんやりとする。それは嬉しいのであるが、しかし、鳥の声がしないのには参った。時々ではあるが異常に鳥が少ないことがある。そんな時、思い出すのは師匠の「谷間に入ったね」の言葉だ。それでも何某かの収穫はある。ウグイス、ソウシチョウは声が大きいので分かりやすい鳥だ。平地よりも明らかに気温は低い。それに微風が心地よい。学校に戻ると、室林道がいかに良い所なのかが身に染みて分かる。
暑さにもめげず観察した 移動は車にした。スイカを用意していただき、何よりの御馳走となった。
2024 7 14 室林道ラインセンサス
昼から室林道に向かう。曇空であることから、晴れ間のように早朝と午後とで野鳥出現に差がないのでは、と思ったからだ。結果はほぼ予想に近かった。早朝での個体数が39は、直近2回の43、36、46と大差はない。夏鳥の様子を見る。確認数でみると徐々に減ってきている。その顕著なのがキビタキ。今日は1回しか声を聴かなかった。センダイムシクイ、あれほどよくさえずっていたのに。先回のサンショウクイで分かったことは、声だけでは個体数を軽々に判断できないというものだ。無言での群れ行動はごっそり漏らしているわけだ。ここに来てサンコウチョウの声をあちこちで聴かれるようになってきた。午前地に行ったふるさと公園でも聴いた。今日の午後からのセンサスでも鳴いていた。飛来が他の種よりも遅かった分なのか、どうであろうか。
沢の音

被写体探しに目を凝らす。ツバキの葉っぱの上に小さな水溜まりを見つけたときは嬉しかった。⑤⑥
濡れた林道は危険。何度もスリップした。
2024 7 14 ふるさと公園ラインセンサス
今日は車上からセンサスを行った。駐車場から公園最高点遠見山(180メートル)までの往復。途中でトイレ5か所のシャッター開きと、獣シャッタアウト用メッシュ柵の扉を開ける。片道30分の、センサスとしては丁度良いコースだ。わき見運転をすることは絶対できない。だから声が中心になるのは仕方がない。歩行でのセンサスにはかなわない訳だ。常連の、ウグイス、ヒヨドリ、メジロに交じって聴こえるのは、ホオジロ、サンコウチョウ、サンショウクイたち。いずれも私のお気に入りの野鳥だ。地元の山ではよく聴かれるソウシチョウが、ここではあまり声を聴かないのも不思議な事ではある。何か地形的なことが影響しているのであろうか。わざわざ立て看板で案内表示をしている植物が咲いていた。名前はハンゲショウ(半夏生)。意味ありげな名前が付けられているが実物は至って地味に見える。
半夏生、珍しい植物なのであろうか?
2024 7 7 室林道ラインセンサス
日の出と同時に家を出て林道を歩き始める。林を抜けて道を照らす日光が柔らかく感じて良い。林道から下に下がれば、すでに暑い太陽になっている訳ではあるが。2つのことに出会えた。さえずりの鳴きかわしである。鳴き交わしているのは2種。センダイムシクイとオオルリ。2種が鳴き交わしているのではなくて、同種同士が鳴き交わしているのだ。本当に相手のタイミングを合わせているのであろうか。自分勝手に鳴いているだけなのか、本当の所を知りたいと思う。ライバルなのか信頼できる仲間なのか。2つ目は、サンショウクイの群れ行動を見たこと。声だけでは個体数は正確には分からいものである。声がしたと思って様子を見ていたら、2羽3羽と姿を見せ始めた。一つの樹に次々入っていく。およそ10羽くらいであった。これほどの個体数を目の前で見たのは初めてだ。お気に入りの鳥なので嬉しい。そんなこともあって、ラインセンサスの2時間30分も掛かった。早起きは三文の徳とはよく言ったものだ。
センダイムシクイ鳴き交わし

オオルリ鳴き交わし

見所満載
①-④コサメビタキ(にしか見えない) ⑩湧き水が朝日に輝く(ダイヤか?) ⑪カナヘビ ⑫ネジバナ ⑭-⑲クモの巣はすばらしい被写体(小宇宙) ⑳㉑ネムノキ ㉑にはサンショウクイも写っていた ㉒-㉔オオルリのメスが捕食 ㉕-㉟サンショウクイ ㊱ソウシチョウ(特定外来種に指定)
2024 6 23 鳥川ホタル学校
天気予報で雨間違いなしとあった。集合場所に来たのは萩小の先生ひとり。個人情報なので名は伏せる。ホタル学校も見たいし、せっかくなので2人で探鳥会を行った。新東名が見渡せるところまでは急な登り、あとはホタル学校までダラダラの下り。体感的に鳥川の標高がかなり高いことに気付く。登り道でキビタキがさえずっていた。新東名の法面にはホオジロがいる。この場所はホオジロの別天地だと思う。メジロとイカルの群れ、ヒヨドリのつがい、雨も心配がないので楽しくやっていく。新東名から先は岡崎市鳥川町。雰囲気のある森の道を進む。マイナスイオンを感じられるように思う。視界が開けた。右手に田んぼ。ホオジロとキセキレイに出会う。ツバメが飛び交い、ハシボソガラスが田んぼに降りていたり、電柱に数羽とまってガサガサしている。鳥川ホタル学校が見えてきた。最初からホタル学校であったわけではなく、鳥川小学校の廃校後に引き継いだものだ。鳥川はゲンジボタルの生息地で、岡崎にあるゲンジボタル生息地のひとつである。確かに岡崎市には清流が多いイメージがある。私の地元萩町からひと山越せばカワガラスの棲む乙女川があるのがその証拠である。天気が心配な状態であったので学校に入ったのは我々2人だけであった。小学校の歴史にも目が行った。卒業写真に子どもの姿が2人3人と写っているのを見ると胸が締め付けられる気がした。子どもたちが地域の人と一緒になってホタルのほど活動をしている写真ではやはり胸が締め付けられた。学術的な展示も豊富である。2にと入れ替わりに数名の入館者が来た。女性は登校の先生であった。私からは、この人は萩小学校の先生ですと紹介する。天気が良ければ子どもたちも一緒にくるハズでしたと挨拶して別れた。一時雨がぱらついたが直ぐに止み、傘を使うことも無く出発地点に戻ることができた。先生とホタル学校のリベンジを約束して別れた。
のんびりと萩と鳥川を結ぶ路を歩いた 学校の展示は特筆もの 大勢でリベンジだ!
2024 6 22 蛇峠山
めったに梯子をやらなくなったが、今日は、茶臼山から蛇峠山へと回ることに決めていた。理由はひとつだけ。コマドリのさえずりを聴きたいが為である。だから今の季節でないとだめなのだ。さえずりが聴きたい訳であるから。国道153号線を治部坂まで行き、別荘地帯を通過、馬の背までは車で登れる。蛇峠山は独立峰である。そのせいなのかは分からないが電波塔が林立している。1番大きいのは察しのとおりNTTである。あとは企業規模に応じて立っている。その中で丸いドームが目立っているのが国土交通省の雨雲レーダである。(案内板は未だに建設省になっているが直し忘れたのだろうか)馬の背からセンサスを開始。ウグイスやコルリなどの声を聴きながら山頂へと進む。今日は山頂までは行かない。コマドリの居そうな所だけにした。(理由は疲れているから)5月6日に来た時とはずいぶんと様子が違う。ハルゼミの大合唱が始まっていたのだ。よほどの大声の鳥で鳴ければハルゼミの声にかき消されてしまう。ヒガラ、コガラも、たとえ鳴いていたとしても耳に入って来ない。コマドリも同様の可能性があると、気を引き締めて歩き出す。コルリは茶臼山同様かなりいた。しかし、コマドリは、5月6日のようには行かなかった。運も良かったと思うが、やや遠い所から1つだけさえずりを確認できたのだった。まあ満足した。種目はしらないチョウの交尾らしいのを見た。自然の営みの一端に触れることができた。蛇峠山で印象に残る植物はマツムシソウである。さすが長野県!もちろん開花の季節にはまだ早い。
ツツジの花が未だ健在
2024 6 22 茶臼山ラインセンサス
天気と残りの日程のことを考ると明日しかないと思い、急遽本日土曜日に茶臼山へと出かけることにした。行き当たりばったりである。もっと早く寝ておけば良かった。4時にセットしておいたのに起きたのは5時。豊川市の上には厚い雲がかかっていて雨が心配であったが、新城市に入ったら晴れ間になっていた。茶臼山も当然のように良い天気であった。茶臼山周回道路がセンサスコースである最近は時計の右回りに回っている。以前は左回りであった。さらに前は右回りであった。理由は簡単、歩いてみて楽な方を取っただけだ。ゲレンデが上を通ている町道の橋(トンネルかも)に沢山(10個くらい)のツバメの巣があった。姿を見るとイワツバメのようだ。およそ20羽くらいがぶつかりそうな勢いで飛び回っている。昔、愛知県の体育会の軒先に大量のイワツバメの巣を見たことがある。普通のツバメよりも数は多いイメージがイワツバメにはある。その体育館も昨年末の取り壊されてしまった。空家には巣を造らないイメージがある。人間は彼らにとって良い仲間なのだろう。人間の方もツバメのことを心配しながら営巣場所を貸している節がある。センサスで印象的であったのは、コースの前半(西側から北側)ではウグイスの声がとても少なかったこと、後半(東側から南側)にとても沢山鳴いていたことと、地味ないケージのコルリであるが、今日は頻繁にさえずりが聴かれたことの2つである。全く確認できなかった種もある。山の住人を自任しているコガラが、声すら聴かれないのも珍しいことだ。今ならではの鳥の代表格なのがカッコウであろう。カッコウが鳴いた。ああ高原にいるんだなーとしみじみ思う。私に高原の印象を深めてくれる鳥があと2種いる。アカハラとマミジロである。マミジロの方がまず見られなくなり、アカハラもやがて見なくなった(正確には声を聴くことが無くなった)。寂しい限りである。
カッコウ

コルリ

雲のかたちが頻繁に変わってくる
⑬⑭イワツバメ ㉘㉙ホオジロ ㊺モズ(つがいか?)
2024 6 15 羽根・長根ラインセンサス
早苗から、どんどん成長し、どんどん株がおおきくなり、やがて稲穂が垂れる。その決まった工程を横道に逸れずに進んでいる様に見える。セッカの声がした。ヒッツ・ヒッツ、チャ・チャと鳴いている。久しぶりに聴いた声だ。そういえば、最近は山ばかりに行っていてセッカの声を聴くことが無かったな。アオサギが2羽飛び立った。はっきりとはしないが若鳥のような色であった。もうあんなにデカくなったんだな。ダイサギがどこからともなくやって来て畦道に降り立った。ああ、この個体はチュウダイサギか。最後にうれしいものを見た。ツバメが舞っている。動きをみると何となく感じが違う。イワツバメの群れであった。白い一本の筋が目に飛び込んでくる。ああ、イワツバメだー。
緑の絨毯?
2024 6 15 ふるさと公園ラインセンサス
今日は車の上からラインセンサスを行った。週末まで忙しく過ごしたばかりだったので、今朝の静かな時間がとても心地よく感じた。次々と鳥の声がしてくる。車からなので姿を見ることはなかなか難しい。声だけのラインセンサス記録である。それでも好いと思っている。きれいな声の主はキビタキだ。ウグイスの声は無論いい。一番多いのはヒヨドリ。ヒヨドリは何種類もの鳴き声パターンを持っているというなかなかの優れ者だ。さえずりの中にいれてやってもようにして思えてならない。それと、目一杯出し惜しみしないで声を出しているのがとても好ましい印象を与えるようだ。
遠見山からの眺め。豊橋市市街、三河湾。
2024 6 13 室林道ラインセンサス
ヤブサメの地鳴きらしい声を聴いた。今年に入ってから、ヤブサメの姿はおろか鳴き声さえも確認できていない。もうこのままで終わってしまうのではと諦めていや矢先のことであった。確認できたのは地鳴き。さえずりであったなら間違いなくヤブサメと言い切れるのであるが。地鳴きも聴いたことは頻繁にあったので、併せて姿も確認したいとかなり時間を掛けて探したが駄目であった。舌打ちのような声というのがヤブサメの地鳴きに対しての印象である。無論直ぐに録音機のボタンを押した。電源ボタンは入れておいて、録音ボタンを2度押しすると録音に入れるようにしてスタンバイしているのだ。場所も重要だ。その点今回は、過去にも確認している所であったので気を強くしている。1回だけでは精度が低い。2度3度と確認していきたい。
ヤブサメ地鳴き?

オオルリ

2024 6 9 夜の探鳥会龍源寺
夕方過ぎ7時に50名を超す人の列が目的地の龍源寺に向かって歩き出す。それも、何があったのだろうと思うほど賑やかに。今年の夜の探鳥会はマンモス探鳥会となった。普通の昼間の探鳥会ではとても捌ききれない多さである。どちらかというと、鳥よりも何よりも、夜道を歩く楽しさに特化した探鳥会なのである。少なくとも最近はそうなった。そんな中でも何か記憶に残るように、それにはホタルがいい、そんな考えで例年よりも1か月は止め、今年は6月に開催した。歩くコースもできるだけホタルの見られそうな川沿いの道を選んだ。(その場での思い付きである)その結果は上々であった。最初の1匹でも喜んで見ていたが、やがて数も増えうっくりと光が舞うのを見て、改めて地元の良さをかみしめることになったのである。先生方も多数参加していただいた。ある先生から、去年4年が調査したら、ホタルの餌となるカワニナが見つかった、と教えていただいた。だから、いるべくしていたホタルなのだ。先生方は全員萩町以外に住んでいるが、なかなか蛍は見られないそうだ。そうこうしているうちに龍源寺に到着。境内でムササビの出現を待つ。校長先生が正体は分からないが何か動くものを見た。子どもたちにとって、たとえ10分でもおしゃべりを我慢するのは大変だ。しかし、今年も黙って観察できたことは褒めてあげたいと思う。場所を隣の墓地に移して肝試し大会が始まった。ご先祖様が驚くくらい大きな悲鳴を上げて楽しんだ。時間はあっという間に過ぎ、予定時間をオーバーしそうだ。学校への帰り道も賑やかな事この上ない。ご父兄が出迎える中意気揚々と校庭に入る。多分喉はカラカラであろう。スイカの出回る季節には少し早く入手に苦労をしたが、子どもたちには「スイカ片」を食べてもらった。
大勢の子ども・大人が参加した
お寺のお墓で肝試し、校庭に戻ってスイカを食べた
2024 6 9 寺の入林道ラインセンサス
一時だけ国道301を走って目的地へと着くのであるが結構車の量は多い。その生には、10人ほど1列になって自転車が走っている。先頭は風圧をまともに受けるから、プロのレーサーのように先頭交代をしているのであろうか。この道を走っているということは、ここに至るまでに400~500メートルを登って来たということになる。ご苦労様と言いたい。反対に下りは楽ちんなのだが。三河湖に向かう県道363からさらに寺の入林道へと入る。ここから車はほとんど走らない。地元の軽トラックくらいである。ところが、数台のミニバンなどが通り過ぎて行った。春いていると車が止まっていた。すぐにピンときた。アマチュアの樵さんたちだ。見覚えのある人に声を掛けたらやはりそうであった。新城市区域の間伐が終わった後なので、様子が変わってしまったことを話題にした。彼ら(新城市の森林組合)と違い我々はずっと小規模でやっている。1日かけて5本くらい倒すのが精一杯です。などと教えてくれた。私としてはこちらの方に共感したい。野鳥ではツツドリの存在感が半端なくあった。声をよく聴くと単純なポポではない。結構濁った声を出しているのだ。新しい発見である。呼応するようにして、ホトトギスも鳴きだした。托卵寄生鳥に挟み撃ちにされていて宿主鳥も気が気ではないのかもしれない。オオルリが枝先でさえずっているのが見られた。これだけオープンに見たのは久しぶり。そんなこともあって、センサスの道中オオルリの営巣に注目した。そして一つの真新しい巣を見つけた。覗き込んでみるといきなり抱卵中のメスが飛び出てきたので、思わずあとずさりしてしまった。心臓もドキドキだ。面のため卵の存在を確認してみると丸いものが見えたので、その場を直ぐに後にした。付近でオスがさえずりをしていたが、この巣の持ち主であった可能性が高いだろう。無事津だってくれることを願うばかりだ。
ニホンジカの声

ハルゼミの声

気持ちの良い景色。野鳥を見ながら歩く至福の時。
➈⑩オオルリがさえずっていた。
2024 6 2 ふるさと公園ラインセンサス
今日は車でラインセンサスを行った。園内は20キロ以下の速度で行くため歩いてのセンサスとそんなに変わりはない。公園の隣の杜からアカショウビンとサンコウチョウが鳴いていた。アカショウビンの声を聴くのは今日が最初だ。音羽の野鳥初確認記録には載せられないのが残念。きっと音羽の地からもさえずりが聴かれるであろう。同時にサンコウチョウの声がしたが、大木の繁る森なので何ら不思議はない。今日は法事の日。天気が心配になるが、予報通り厚い雲が覆いかぶさっている。遠見山からの景色もやや靄がかかっていた。キビタキ、ウグイス、カワラヒワ、メジロのさえずりが多く聴かれた。ヒヨドリはとても賑やかだ。
雨になりそうな天気
2024 6 1 室林道ラインセンサス
6月初っ端から室林道に行く。青空にぽっかりと白い雲。早苗の上を吹く風が実に気持ちがいい。なんと表現したらいいのか。ジブリの映像の世界を思い浮かべる、そんな景色のような気がする。我田引水でも敢えて言おう。私の故郷の風景は市内でも一番だ。田んぼの所々で見る白いもの。ダイサギが夏鳥としてやってきた姿である。亜種のダイサギであった。林道に入ると鳥の声が聴こえてきた。シジュウカラだけは確認できなかった。彼らはどこに行ったのか。平地でさえずりをよく聴いていたので、下がっていたのかなと思う。あるオオルリの個体が面白い。キビタキの声を真似ていると思わせるのである。過去にも同じ経験があった。一瞬キビタキではないかと思ったが、その後に続く節回しはやはりオオルリであった。キビタキがオオルリの真似をする個体はないのであろうか。自分はまだ聞いたことがないが。それを考えると、オオルリは真似上手なのかと。クロツグミと似ていると思う。日本三鳴鳥の中でもオオルリは、節回しが複雑という意味で特出している。ウグイスとコマドリはストレートだ。オオルリはクロツグミに似ている。
キビタキ、ソウシチョウの競い合い

影がおもしろい
②ソウシチョウ ⑧➈ヒヨドリ ⑩カナヘビか?
2024 5 25 室林道ラインセンサス
6時40分スタート。これでも早すぎるとは言えないが、野鳥のさえずりなどはいつもより多く聴かれたように思える。やはり時間は早いに越したことはない。最近朝夕必ず聴かれるのがカッコウの鳴き声である。この托卵寄生鳥ほど興味を引く鳥もそうそういないのではと思う。繁殖期なのでペアや餌運搬の姿を見ることもある。オオルリのペアらしい姿も見られた。オスのさえずりに惹かれるメス。ヒナに虫を運ぶメス。色々な見所に溢れているのがこの時期だ。ウグイス、オオルリ、キビタキが主役ならば、センダイムシクイ、メジロ、サンショウクイは名脇役。そして、良くも悪くも個性派なのはソウシチョウやヒヨドリ。その中でホトトギスは超癖の強い鳥である。なんせ、一声鳴くと周りの鳥たちがすぐに反応する。朝早いせいなのか少し肌寒い。でも神経を集中して歩き続けるので程よい寒さだ。こんな場所を独り占めしている贅沢さ。お金では買えない。
キビタキ地鳴き

ウグイス

ホトトギス

朝日が林の中を通り抜け道を照らす。緑色が一層鮮やかに見える。気分は最高だ。
2024 5 22 ふるさと公園ラインセンサス
ホトトギスが大きな声で鳴いていた。托卵寄生するこの魅力的な鳥のことをもっとよく知りたいと思う。ホトトギスが鳴いた途端ウグイスも反応(そう感じた)した。擬人化するのは良くないとは思うが被托卵鳥はどのような思いでいるのだろうか。ここはヒヨドリが多い所だ。明るい樹林が好きなのだろうか。薄暗いスギ、ヒノキの林に多い鳥のイメージがある。万能選手なのであろう。だからこれほど栄えているのだと思う。サツキが真っ赤な帯になっている。もうすぐ梅雨入りだ。
キビタキ

ホオジロ

公園では毎月様々な催し物を開いている
2024 5 20 愛鳥クラブ
1学期のクラブ活動に参加した。クラブの名前は「愛鳥探検クラブ」と言う。今年は7名。ただし今日は6名でである。さらに、先生もお二人参加してくださった。サギやカワセミ、できたらセグロセキレイのアルビノを観察したいと思い、学校から下の方面に向かう。樹の種類ごとに緑色があって、これを正確に写生するのは難しいと思うし、できたらいいなとも思う。市民館の軒先に陣取ったツバメを観察。親が餌を運んでくると、ヒナたちは一斉に大きく口を開け鳴きき叫ぶ。その仕草に癒されるのだ。隣にあるコシアカツバメの巣には、主人が留守の間にスズメが占領していた。市民間だけでなく、小学校の校舎にある全てのコシアカツバメの巣は、スズメが運んだ巣材が覗いており、コシアカツバメのものではなくなっていた。今の所、コシアカツバメの姿はなく、巣作りもなされてはいない。学校から離れるとすぐに山陰川が見える。ここにアルビノがいる。さらに神社の前を進んでいくと、電線でホオジロが鳴いていた。スコープは子どもたちが交代で使った。ホオジロの顔もハッキリと見られた。ホオジロはその後も姿を現した。すっかり友達になったようだ。カワラヒワやキジバトを見ながら最終目的地の羽根の田んぼに向かう。サギがいるかな?この時が一番緊張する。いないと困ってしまうからだ。ざっと全体を見渡し、2か所で白い点を見つけたのでひとまず安心をする。最も見やすいのをスコープで捉えるよう指示をする。数羽ほどいたようだ。首を伸ばすと現れ、縮めると視界から消える。だから、正確な数はハッキリしない。それでも、この群れにはダイサギとアオサギの2種類がいることが分かった。ダイサギについて、今いるのは夏鳥として飛来した個体で、チュウダイサギというダイサギの亜種であることを説明する。それに対をなすダイサギ(オオダイサギ)は冬鳥なのだ。今まで留鳥として覚えたダイサギは、実は、2種類の亜種であり、それぞれ、冬鳥として、夏鳥として飛来してのだ。下校時間が迫った。帰途で見つけたのはあのカワセミであった。
五月晴れの下、いろいろな野鳥を観察した。大きなシマヘビに一同びっくり。
2024 5 18 寺の入林道ラインセンサス
13時過ぎに茶臼山からやって来た。時間的には鳥たちも休息している頃で、センサスするには最適とは言えないが。それでもまあまあ楽しむことができたと思う。オオルリ、キビタキ、ヒガラ、ヒヨドリ、サンショウクイ、ハシブトガラス、トビたちである。茶臼山もそうであったが緑が美しい!今は緑を鑑賞する時なのだ。花でなくてもよいではないか。先の鳥のリストにウグイスが無いのは寺の入林道の七不思議である。今日は全く聴くことは無かった。
緑がきれい。
間伐の結果、真夏のセンサスでは暑く感じらることが多くなりそう。
2024 5 18 茶臼山ラインセンサス
車のタイヤをノーマルに替えたので、茶臼山へのドライブも気持ちよくできそうだ。スタッドレスタイヤが必要なのはほんの少しの期間ばかり。それでも数回はお世話になっている。茶臼山と寺の入林道には必需品であるのは確かだ。昔だったらタイヤチェーンを付けたりハズたりして鳥を見に行っていた。ほんの10数メートルが踏破できないで引き返すこともあった。ありがたい世の中になったものだ。この時期はシバザクラ祭り。駐車場が有料(1000円)なのは困る。(シバザクラを見に来たわけではないので)だから、駐車場には停めていないのだ。コルリのさえずりは結構あるけれど、肝心のコマドリの声が聴こえてこない。このような風になってもうかなりの年月が経った。会えなくなった鳥は外にもある。アカハラとマミジロのさえずりを聴くことが楽しみのひとつであった。しかし、全く聴かれていないのが実情だ。地元でもアカハラを見ることはあるが、茶臼山で会えないとは。逆に毎年出会える鳥もいる。カッコウとホトトギスが鳴くと高原(標高1200~1400メートルある)にやって来たと思う。ヒガラのさえずりは沢山聴かれるがコガラも聴いてみたい鳥だ。コガラは頑固に冬季をここで過ごす。自然児らしく人をあまり恐れない。そこが好きな所だ。駐車場の入口ではガードマンの人が案内をしている。自分はその前を通り過ぎる。2つ目のフィールド三河湖に向かうためだ。三河湖への道が何年かぶりに通行止めが解除されたのだ。
ソウシチョウ(地鳴き)

ソウシチョウとコルリ

ウグイス・ヒガラ・コルリ

車場は有料だけど満車。帰途、高原道路の駐車場へ向かう車の渋滞が半端ではなかった。
㉞㊲ひっそり残っている昔通った道、もう30年以上歩いている。
㊴ヤマカガシの子どもが死んでいた。
2024 5 17 室林道ラインセンサス
10時から用事があったので、今日は車でラインセンサスを行った。幸いにして、自分の車はハイブリッドなのでモーター駆動時はとても静か。下りは回生ブレーキになるため充電も可能。歩きの方法には及ばないかもしれないが、できる限りの努力はしたい。室林道ラインセンサスは、月を旬で区切り、旬のどこかでやる方法にしている。だから、10日間しかチャンスが無い。このことが結構大変なのだ。ウグイス、ソウシチョウ、ヒヨドリなどの大きな声の確認は簡単なのだが、小さな声の地鳴きは、いくら静かな車とは聞き漏らすのではと不安になる。歩く速度で走行するのも難しいものだ。どうしても歩行の倍のスピードになってしまう。大きく変わる点はまだある。歩行では、林道の中間点を折り返している。車では、林道全コースを片道走行するのだ。枯れ枝や落石にも注意を払う。キョロキョロとしながら走ると、枝をタイヤに巻き込んだり、石を踏んずけてびっくりしたりする。第一車にも良くない。だから鳴き声が全てといってもよい。枝先を子細に見るようなことは無理なのだ。
車窓から
2024 5 14 春の探鳥会1年生 羽根・長根方面
1日遅らせたのが良かった。スタートは曇り空ではあったがやがて雲が切れて青空が広がった。田んぼの間を歩いて野鳥を見る。ぽっかりと浮かぶ白い雲と青い空、ジブリ映画の一場面を見ているようだ。市民館の軒先にツバメが巣を造った。子どもたちが見守る中、親ツバメは巣に戻ってヒナに餌やりをする。その度に、ヒナたちは大きな口を開けて餌をねだる。親鳥は休む間もなく再び餌を探しに飛び去って行く。それを休むことなく繰り返すのだ。学校を離れて、子どもたちが毎日通う道をセンサスする。ツバメが飛び交う。きっとヒナが待っているのだろう。電線に止まっているものもいる。休むことも必要だろう。田んぼのオタマジャクシを見つめた。大きいのはカエルのような形が見えてきた。小さなのはまだまだオタマジャクシだ。あめんぼうや虫の様なのもいる。山の方からウグイスの声がする。田んぼにアオサギがいた。右にに行ったり左にきたり。スコープ泣かせのアオサギである。ここでハシブトガラスの声。いいタイミングで鳴いてくれた。2種類のカラスの名前と鳴き声の違いについて話す。これは、萩小の子どもにとっての登竜門と、私は勝手に思っている。今日の探鳥会は1年生として最初の探鳥会なので、できるだけたくさんの鳥たちを見せてあげようと思い、フィールドスコープを目一杯使った。それでも、最初の内はうまく覗けない子が多かった。すぐに見られそうに思ってしまうが、実は、練習をしないといけないのだ!この辺りはよく理解しておく必要がある。あと数分で探鳥会も終わる。そんなタイミングで、待ちに待ったカワセミが出現した。山陰川の本流ではなく、狭い水路を縫うようにしてカワセミが飛び去って行った。それは瞬く間に姿を消した。トンネルに入ったのだ。1秒の半分くらいの時間だった。それでも、「見た!」「見た!」の声が挙がったのは嬉しかった。もうひとつ、大きなサプライズがあった。あの、秋の探鳥会で見つけたアルビノが、まだ元気にしていて、みんなの前に姿を見せたのだ。彼は(アルビノ)民家の屋根にとまってジャンプをしていた。とても気分が良さそうであった。もう一羽の普通種のセグロセキレイと一緒にいるので、孤立していないのが安心材料である。アルビノは萩小の子のアイドルといっても過言ではなくなった。
1年生にとっては初めての探鳥会である。
①②ツバメの子育て ③-⑦セグロセキレイのアルビノ
2024 5 11 室林道探鳥会
本日の参加者は、御津町障害福祉センターが主催する探鳥会のメンバー4名である。今年の初め頃に計画し開催の運びとなった。メンバーとは昨年秋以来の再開で、今回で、お会いするのは3度目となる。すっかり顔なじみとなった感がある。行先は室林道。直近の子ども探鳥会や小学校春の探鳥会で訪れており、今が一番の探鳥会シーズンと踏んだのだ。特にさえずりの盛んな時期である。一番賑やかでおいしい場所をと、室林道の麓に車を停めて(集会所の駐車場を借りて)室林道まで徒歩でラインセンサス。林道に入ったらゆっくりお菓子を楽しむ。そんなプランを考えた。林に入った。しかし、以前と少しばかり様子が異なる。鳥の声があまりしないのだ。このままでいったら正直まずいと思った。じりじりした気持ちで進む。「声が少ない」と思わず声に出してしまう。その弱気になった気持ちを腐食してくれたのがキビタキであった。右手の林からさえずりが聴こえてきた。助かった!その後は怒涛のさえずりが戦となる。このようなことはたびたび経験している。センダイムシクイの「焼酎一杯グイー」。「ツキヒーホシ」のサンコウチョウと耳をそばたてさせる鳴き声が続いた。サンコウチョウを見たメンバーも現れる。『これはいいぞー!』真打はやはりオオルリであった。さえずりの声がどんどん大きくなってきた。「近くにいる」「ここは気長に待って姿を見つけましょう」。そして、とうとう姿を見つけたのだ。少し前に車が下って来た。知り合いで野鳥写真を趣味にしている人だ。「何か成果は?」「オオルリがいた」と撮ったばかりのオオルリを見せてくれる。メンバーは、「きれい!」と感心している。その直後に先のオオルリの発見となったのだった。実物は格別である。写真や動画は大きくきれいではあるが、実物にはかなわないと思う。たとえ小さくぼんやりした姿でも。その人からはコマドリ、キビタキの写真も見せてもらった。室林道に入ってゆっくりと休んだ。お茶を飲みささやかなお菓子を食べる。周りでは様々な鳥が鳴いている。気持ち良い風が吹いている。最高の場所でのんびり話をした。最高の気分だ!帰りはひたすら下るばかり。あっという間に車の元へ。秋の再開を誓って別れる。遠くるから来ていただきありがとうございました!
2024 5 8 萩小探鳥会室林道
萩小学から室林道まで6名の児童と野鳥を観察して歩いた。学校付近では、ツバメ、ヒヨドリが空を飛び交っていた。電線で鳴いているのはホオジロだ。きれいな声でさえずっている。林道への登り道を息をきらせて行く。民家が途切れて林の中を歩きだすと、ようやく山の野鳥が現れた。ウグイス、センダイムシクイ、ヒヨドリなどが鳴きだした。そこへ突如として現れたのがサンコウチョウであった。特徴ある鳴き声とその姿は一度聴いたり見たりしたら決して忘れない。何人かの子は姿も見たようだ。そして目当てのオオルリとキビタキがさえずる鳴き声を耳にすることができた。観察の合間にはサワガニも見た。最近の子はこの種の生き物に触りたがらない。しかし、このクラスは全員が、ハサミに注意をしてカメラの前におさまってくれた。今回のように学校から室林道の入り口まで歩いて観察するのも悪くないと感じた。林道の中に入ると姿を見つけることがとても難しいからだ。今後の参考にしたいと思う。
とても仲の良いクラス。
2024 5 6 高嶺
国道153号線を隔てて隣あわせの高嶺に向かう。そういえば2年ぶりだ。ここはたびたび通行止めになるのだ。砂地のような表層が崩れやすいのだと思う。天気が良ければカラマツ林が輝いて素晴らしい。全て植林されたものと思う。カラマツやシラカバの林はいかにも高原らしくて好きだ。ゆっくりと車を走らせ記録を取りながら山頂に向かう。圧倒的にウグイスの声が多い。1個所コマドリを期待できる場所があるが残念な結果に終わった。山頂の展望台から人の声が聴こえた。自分の以外に車が見当たらいのでどうしてやって来たのだろうかと思う。徒歩だと思うがそれでも直ぐには合点が行かない。
春秋ともに美しい山である。(カラマツが絶品)蛇峠山と兄弟姉妹のような山容をしている。共に大切な野鳥観察フィールド。
2024 5 6 蛇峠山
コマドリに会いたくてやって来た。私の知っている場所では一番近場である。茶臼山が2時間ちょっと。さらに30分以上は余計にかかる。1枚羽織るものを持ってきて正解であった。蛇峠山の気温は14度。山頂は霧で見えない。場所によってはかなりの強風で体感温度は10度以下だと思う。1か月は季節が逆戻りした感じ。こんな天気で鳥たちがいるのかと心配したが大丈夫であった。ウグイスは限りなく鳴き、コルリ、ヒガラ、ソウシチョウも凄い。しかし、今日はコマドリを聴きたい。しばらくは気配も無し。コルリばかりであった。ポイントが決まっていて、そこでは暫く立ち止まる。そして、霧の中から一声、ヒーンと聴こえた。かなり遠そうだ。それでもコマドリの会えた安堵感が大きい。さらに山頂に向かう。今度は2個体が尾根を隔てていた。先ほどよりもハッキリと聴こえる。山頂(正確には違う)で憩いたかったが寒い。電波中継基地や雨雲レーダーがぼんやりと姿を現す。霧の蛇峠山も雰囲気があり悪くないように思える。下山は足首をバネにする。しかし勢いよくはご法度。小石がコロの役割をしてズルッとくる。録音機のボタンに親指を乗せコマドリが鳴いたらすぐに押す。反射神経が試されるのだ。こうしてコマドリのコレクションを増やしていった。さえずり間隔が長いのはどうも苦手だ。気短には務まりそうにない。ゆったりと構えて「いくらでも待つよ」の気持ちで行くのが良い。録音を停止した途端さえずるという意地悪なのもいる。慌てて録音ボタンを押すも、こちらの心を察してくれないのは憎い。
コマドリ

ウグイス

雲の中の頂上をめざす
①オオルリ ②③ウグイス ㉑高嶺より蛇峠山を望む
2024 5 5 宮路山
目の前に標高362メートルの宮路山がそびえる。「今からあそこまで行って来るんだよ」と話す。雲一つない少し暑い日。町中を歩いていると初夏の暑さではあるが、山道に入れば変わって来るだろう。そう思いながら徐々に登っていく。キビタキ、メジロ、センダイムシクイなどさえずりを楽しむ。キビタキの声が多かった。その度に懸命になって姿を探すのであるが見つからない。第1駐車場から最後の登りに入る。ここが一番きつい。秋の紅葉の名所ではあるが初夏の新緑もすばらしい。そこからウグイスのさえずり。体はきついが気分は最高だ。さらに聴こえたのはツツドリの声。今日は子どもの日。親子連れがすでに弁当を広げていた。我々も思い思いに場所を取る。子どもたちはみんな笑顔だ。2時間あまり山道を歩いてきたのである。お腹はペコペコに違いない。45分で下山する。トイレのこともあるし、山頂は混みあっていて遊べない。下りの方が怪我が心配だ。不安定な敷石を歩く。泥濘もあり心配だ。それでも何とか無事に下山できた。保健センターの川は様変わりしていた。出水で川が土砂に埋もれていた。残念!これでは遊べない!それでも靴を脱いで川の中に入る。意地であろう。尻もちを付いている。下半身びしょ濡れになった。遊び足りないがもう時間だ。再び暑い道を親の待つ駐車場に歩きだす。
2024 5 4 ふるさと公園ラインセンサス
今朝は10度を下回るやや肌寒感じの気温であった。仕事でふるさと公園内を車で移動するが、道々で出会う野鳥を記録すれば、これほど良いことはない。野帳を手元に置いて、次々と見たもの聴いたものを記入していくことにしよう。ゆっくり走るので歩行記録と遜色ないはず。もちろん運転中には記入できないのでその都度停車する。数分程度余計に時間がかかるので、シルバーの仕事の後子ども見守りの仕事の無い休日がねらい目となる。ただし、じっくり観察できないことは分かっているのであくまでも補助的に考えている。早朝は鳥がよく鳴いてくれるのでありがたい。
2024 5 3 室林道ラインセンサス
サンコウチョウの声を初めて聴いた。かなり早いなと思った。夏鳥の飛来も温暖化のせいなのか分からないが早くなっている印象だ。夏鳥の中で未だ確認できていない鳥はヤブサメとホトトギスくらいか。ヤブサメを中々見なくなって久しい。個体数が減ってしまったのか?どうなんだろうと思う。そういえばアカショウビンもいる。室林道ではないがセッカ・コムクドリ・チュウサギも忘れてはならない鳥だ。奥からアオバトの声がした。不思議な声だ。
ハルゼミが鳴いていた

5月の明るい空が広がる
⑧ヒヨドリ ⑫⑬センダイムシクイ
2024 4 28 寺の入林道ラインセンサス
ふるさと公園で野鳥を見たその足で三河湖へと向かう。今日はハシゴをする。これまた締め切りに追われているタメだ。こんなことを言ったら野鳥が好きでやっやいるのかと疑われそうだ。野鳥が好きだからこそ頑張れるのだ。林道が少し様変わりをした。大々的に間伐が入り空が広がったのだ。タカの類を発見する機会が増えるかもしれない。きょうはエアバスA380を見た。4本のジェット雲が特別感半端ない。標高600メートルは伊達ではない。平地では聴かれない、ミソサザイやヒガラのさえずりを堪能した。ミソサザイは渓流に多い。沢音にも負けない声で朗々とさえずる。自分にとっても特別な鳥である。オオルリキビタキも負けてはいない。沢で多いのはオオルリ。声に個体差が多いというか、わかりやすいのもオオルリの方だと思う。それだけさえずりが複雑なのかもしれない。決してキビタキのさえずりが単純とは言わないが。不思議な事ではあるがウグイスがここでは少数派なのだ。ゼロだとよいのであるが必ず1個体はいるところが現実だ。
ミソサザイ

寺の入林道の緑色は最高だ!
2024 4 28 ふるさと公園ラインセンサス
シルバーの仕事が終えたらセンサスをしようと決めていた。4月分の記録を取るためには後がない。締め切りに追われる作家先生のようにも思い何か空しくも感じられる時もある。しかし、自分的には結構楽しんでもいるのだが。ツバメが飛び交い草花の様々な色が映え、若葉の若緑色が目に快い。その上に野鳥の声がパワーをくれる。こう止められない訳だ。
キビタキ

サクラが終わってツツジが満開。山頂からの三河平野の絶景とピンク色のツツジ。
2024 4 27 茶臼山ラインセンサス
天気が心配であったが今日しか行く時がないと思い、傘さしを覚悟で茶臼山へ出かけた。青空ではなかったが雨は降ってはいない。それでもここは1300メートルの山の中である。山の天気は急変するを金言に、ビニールの傘を杖代わりにして、茶臼山を時計回りに一回りした。曇り空が幸いしたか分からないが、とてもたくさんの声が聴かれたので大満足である。冬季のセンサスが絶対的に個体数が少なかったので、春は確かに生き物が喜ぶんだなと納得している。ウグイス、ソウシチョウが鳴き声の中心にあって(コースのどこにでもいる感じ)、それにその他の鳥たちが加わっている感じだ。ヒガラ、コガラ、ミソサザイのさえずりは高所に来ていることを実感させてくれるし、オオルリ、キビタキ、センダイムシクイ、サンショウクイなどの、身近で鳴いている鳥たちも既に来ていることが分かると、植物ならばもっとゆっくりと春の線が移動するはずなので、鳥類の移動速度の速さを改めて実感させられる。コルリにも出会えた。コマドリと間違えたことを思い出す。初めて野鳥観察をしに茶臼山にやって来た時、コルリの声をコマドリを間違えて覚えたことを、今でもハッキリと覚えている。当時は野鳥の声を知る情報が全く少なかった。コルリの声は良かったが相方のコマドリがいない。これが本当に寂しい。
若葉のさまざまな緑色が目にも心地よい 鳥たちも気もちよさそうにさえずっている。
④⑥ノスリ ⑤⑦⑬ホオジロ ㉑タヌキ?
2024 4 23 室林道ラインセンサス
一昨日の子ども探鳥会でも野鳥の声が凄かったが今日はそれ以上に鳴いてくれた。あのコマドリもいて比較的大きな声でさえずっていた。この日の確認数は1羽。もう1種、初めて聴いたのはツツドリ。2日ほど前にふるさと公園でも聴いた声である。同じ科の鳥であるカッコウやホトトギスも次々とやって来るだろう。普段は聴かれない鳥の声が聴かれるのも夏鳥飛来時期の楽しみである。記録には載せないが気になる鳥がいた。最初はキビタキのメスのように思えた。双眼鏡でじっくり眺めていたらちょうど顔が見える位置になった。その時目に入ったのが喉元の薄い赤色であった。すぐに思い付いたのはノゴマであった。にわかには信じられない鳥である。改めて3種の図鑑でノゴマの特徴を調べる。オスのハッキリした赤ではなくメスの薄い赤色の方が見たときの印象ににていると思った。ただし、普通はメスは白い喉もとなので疑問は残る。本当にノゴマであったのならとても嬉しいのであるが正式記録とするのには正直自信が無かった。改めて野鳥観察の醍醐味を知ったように思う。自然は予想を超えたものを見せてくれる。
本日の室林道の野鳥アルバム
ヒヨドリ

キビタキ

コマドリ・ウグイス・ソウシチョウ
センダイムシクイ
ウグイス2(中音と高音を繰り返す)
再びマムシグサが出現! 道端でマムシの死がいを見るのもこれから
2024 4 21 室林道・倉地区山陰川
前日までの天気予報では探鳥会を危ぶむ見方もあった。そのため、直前の、学校とのやり取りでは、小雨決行と伝えました。せっかくの野鳥観察の好機をみすみす捨てるに忍びなかったのです。結果は、青空があちこちに見られて、暑すぎず寒すぎない絶好の探鳥会日和となった。3台に分乗して室林道へ。その前に山陰川にも寄った。これは、カワセミなどを見ようと思ったからである。残念ながらカワセミは見られなかったが、セグロセキレイやコチドリを見つける事ができた。コマドリのさえずりを同地でも聴いていたので期待がさらに高まった。しかし、これも残念な結果となった。室林道へはいつもと反対の方向から進入した。それは、県道を使うことが無いため、鳥の声を確認したら車を停め、じっくりと観察することができるからであった。何時ものコースでは、林道に入るまでは県道を進むため、実際に交通量も少ない訳ではない事もあって、のんびりと車を停められないのだ。林に入るとすぐに野鳥の鳴き声が聴かれた。ウグイス、ヒヨドリはもちろん、クロツグミ、オオルリが美しいさえずりを競っている。そのため、しばしば車から出て耳を澄ませて楽しんだのであった。日本の野鳥で美声と言われている5種(6種)の鳥がいる。それは、ウグイス・オオルリ・コマドリ・キビタキ・クロツグミ(ミヤマホオジロ)である。その選ばれた5種のうち4種までを今日の探鳥会で確認できたのだ。できなかった1種はコマドリである。コマドリも可能背が無いわけではなかった。そう考えると凄い事だと思った。オオルリのさえずりの前では一人の子どもに録音機を渡した。後でさえずりを聴かせたいと思ったのだ。キビタキは休憩中に出合った。これからお菓子タイムをしようと思っていた矢先のことであった。ごく近くで聴こえてくるので皆で探した。そして遂に林の中でさえずるのを見つけたのだ。全員が見た。これは嬉しい。これで思い残すことなくお菓子タイムに入れる。先生が車の中から出してきたブルーシートでお菓子コーナーを作った。耳と口を楽しませることができたのは、とても幸運で嬉しい事であった。
オオルリのさえずり



2024 4 14 室林道ラインセンサス
昨日、今日は氏神様の春の例大祭であるが、特別に何をするわけでもない。神事は終えているので今日は自由時間だ。子や孫は皆で店で食事をする。家に集まるのは正月くらい。だから、今朝は山に向かいコマドリを探す。コマドリのさえずりを探し求め、本当に久しぶりに、観音山の麓に分け入った。道は出水で削られ歩き辛いので道なき道を歩く。と言えば大げさすぎる。林の中は朝ということもあって静かであった。そして気持ち良かった。早々に引き上げ室林道へと向かう。本当は歩かねばいけないのであるが、車でセンサスするのにすっかり慣れてしまう(人間は簡単に楽な方に傾く)。できるだけゆっくりと、ポイント、ポイントではエンジンを止めて鳴き声を聴くことで、正規のセンサスに近づけようとはした。今日、キビタキのさえずりを初めて聴いた。宮路山では姿をみた。しかし、さえずりは今日が最初である。オオルリ、ウグイス、センダイムシクイ、メジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、ソウシチョウとさえずりを聴く。一昨日聴いたコマドリは3個体とも確認できなかった。ところがである。アカハラの姿を見、証拠写真を撮ろうと暫く1っか所に留まっていた正にその時、3個体発見とは違う所で、コマドリのさえずりを聴いたのだ。アカハラが引き寄せてくれたとしか思えない出来事であった。これで音羽におけるコマドリの個体数は4。未だ好機は続くので最終個体数が楽しみになる。一年で最もワクワク、ドキドキする時間を今過ごしている。
コマドリとセンダイムシクイ

2024 4 13 西切山林道ラインセンサス
サクラが咲きだすとそわそわする。コマドリを追って音羽の山を歩くのである。平年よりも遅れてソメイヨシノが咲きだした。もう一つのヤマザクラの方はすっかり山々を美しく飾っている。宮路山の第1駐車場は満杯であった。自分は第2駐車場に停めるので関係ない。コマドリを探しに来ているが、もちろんしっかりラインセンサスを行うつもりである。スタートして暫くはウグイスばかり鳴いていた。西切山林道にもソメイヨシノが植えられていて少しばかり開花していた。ツツジなど落葉樹の新芽が綺麗。食べられそうにも見える。上の方から聴こえてきたのはセンダイムシクイのさえずりである。夏鳥の先頭でやって来たのだ。(ツバメやコチドリは既に確認しているので、正しくは山の鳥の先頭)個体数もかなりあった。そうなると、俄然その他の夏鳥の出現を期待してしまうが、そううまくはいかなかった。その代わりと言っては何だが、ルリビタキの、それも綺麗な雄であったのは、嬉しい誤算(予想外)であった。ヤマガラ、シジュウカラ、メジロなどはとてもよくさえずっていてしっかり楽しませてくれた。これがスタート。これから頑張るつもり。
2024 4 12 室林道ラインセンサス
スタート地点でオオルリがさえずっていた。センダイムシクイも伴奏役を務めている。両者ともに見上げる位置で鳴くので、一緒に聴こえて来、よい演奏メンバーと言ってよいだろうか。ここで足止めされたのが良かったのだ。とうとう待っていた鳥の声を聴いた。室林道でもコマドリに出合える可能性が1番場所なので期待はしていた。その通りなったのは良かった。コマドリはそれだけでは終わらなかった。その後2個体もの出会いがあったのだ。コマドリは水の流れを好むので沢がある場所がねらい目。今日の2個体は沢で鳴いていた。もう一つはどちらかと言えば尾根で鳴いていたので、不意を突かれたようで驚きのほうが多きかった。このようなことは間間ある。コマドリだけではない。オオルリも3個体確認した。ウグイスも無論いるので、これでウグイス・オオルリ・コマドリ(日本3鳴鳥)の揃い踏みとなったわけだ。
コマドリ

オオルリ

ソメイヨシノはほとんど散ったが元気に咲いている樹もある
2024 4 6 室林道ラインセンサス(車使用)
一昨日のセンサスから変わった点。オオルリのさえずりを確認した。おそらく4月1日に聴いたものと同一個体と同じと思われる。相変わらず夏鳥第2番手は確認できなかった。そして、いつの間にか、室林道におけるさえずりでウグイスと双璧をなすソウシチョウの声が大きくなったことである。
2024 4 8 東霧山林道から宮路山
このコースはコマドリ狙いである。この林道は渓流がきれい。道がデコボコで急な坂もあって、ハイゼット好みの道といってよい。あまり多くはないが、ウグイス、メジロ、ヒヨドリ、あと、ソウシチョウの声があった。宮路山駐車場で辺りの様子を窺う。これまではコマドリの声は聴かれなかった。宮路山を下る間ではウグイスが多かった。樹種の多いコースなのでウグイスの多い所である。故山口氏(師匠)は宮路山のウグイスは歌が上手と褒めていた。
2024 4 1 室林道ラインセンサス
春の陽気となり、野鳥たちも繁殖行動に向けて活発な動きをしているように見える。昨日、宮路山西切山林道ラインセンサスで、センダイムシクイのさえずりを聴いた。これが今季の夏鳥初陣であった。(ツバメ、コチドリは既に来ている。)この天気なので、と期待して室林道へと向かったわけであるが、その通りの展開となったことは嬉しいことである。センダイムシクイもいた。さらにスターの一角も。ソメイヨシノの薄ピンクにとても映える姿で現れたのはオスのオオルリの成鳥だ。既にしっかりとさえずりをしているので、いつでもメスにアタックを掛けれそうに見える。ウグイスのさえずりはもう絶好調といったところか。ヤマガラ、シジュウカラもとても張り切っている。遅れれきたソウシチョウが、一気に挽回を狙い大きな声でさえずる。そのような訳でヒヨドリの声が余り目立たない程である。さえずり軍団に対抗するのには滅茶苦茶大声を出すしかなさそうだ。それができるのはこの鳥しかいない。コジュケイだ。彼らならその場を制圧する大声を出せる。今日のセン砂州の間にも何度か目撃した。鳥の姿はないのであるが、突然の大声で「びっくり」を何度か経験した。
オオルリ今春初確認

ソウシチョウ

コジュケイ

ホオジロ

ヤマガラ

夏鳥の第1陣がやって来た。 ①オオルリ♂ ②③センダイムシクイ♂
2024 3 31 西切山林道ラインセンサス
サクラが咲きだすとそわそわする。コマドリを追って音羽の山を歩くのである。平年よりも遅れてソメイヨシノが咲きだした。もう一つのヤマザクラの方はすっかり山々を美しく飾っている。宮路山の第1駐車場は満杯であった。自分は第2駐車場に停めるので関係ない。コマドリを探しに来ているが、もちろんしっかりラインセンサスを行うつもりである。スタートして暫くはウグイスばかり鳴いていた。西切山林道にもソメイヨシノが植えられていて少しばかり開花していた。ツツジなど落葉樹の新芽が綺麗。食べられそうにも見える。上の方から聴こえてきたのはセンダイムシクイのさえずりである。夏鳥の先頭でやって来たのだ。(ツバメやコチドリは既に確認しているので、正しくは山の鳥の先頭)個体数もかなりあった。そうなると、俄然その他の夏鳥の出現を期待してしまうが、そううまくはいかなかった。その代わりと言っては何だが、ルリビタキの、それも綺麗な雄であったのは、嬉しい誤算(予想外)であった。ヤマガラ、シジュウカラ、メジロなどはとてもよくさえずっていてしっかり楽しませてくれた。これがスタート。これから頑張るつもり。
ウグイス

今年初めての西切山林道だ。この林道を使って「2024年全日本ラリー選手権三河湾」が開催されたのはまだ記憶に浅い。東霧山林道を通行した時に通行止め予告を見たのだった。
2024 3 26 茶臼山ラインセンサス
もう雨なのは100パーセント間違いない。そんな中を茶臼山に向かった。本当は別の日に行きたかったのである。しかし、今日しかダメなのだ。弱気になって、歩いてのセンサスはやめようかとも思った。車の窓を開けてやればとも思った。しかし、よく考えてみれば車は未だ通れないのである。いわゆる冬季通行止めなのだから。幸い雨は小ぶりであった。気温も10度を少し下回る程度。もうやるしかない。傘を持ち、カメラは防水タイプ、双眼鏡はいざという時(種別を確認する)のため持参した。雨の日は鳥たちも黙っていて、鳴き声から種を特定できない場合が多いのである。スタートから茶臼山らしい声が聴こえた。コガラの地鳴きだ。コガラは茶臼山の定番中の定番。冬季になっても山を下りる気はさらさら持たない見上げた鳥である。スキー場の付近から聴こえたのはミソサザイさえずりである。先日、寺の入林道でも同様に聴かれたが、茶臼山のは声に力があった。繁殖を成功させるゾと気合を込めてさえずりをしているように聞こえた。萩太郎山から茶臼山へと向かう頃から雨脚が強くなってきた。粒が大きくなった。それと同時に雷の音もし始めた。これはまずい。早い所済ませてしまいたい。しかしいくら焦っても未だコースの半分しか歩いていない。これ以上ひどくならないことだけを祈って、少しでも歩みを止めないで行くしかないと思った。ホオジロのハッキリとしたさえずり。その近くで枝を飛び回っているのは3羽のシメ。こんな時には双眼鏡だけが頼りだ。鳥たちは異種でも群れているらしい。混軍というくらいであるからその通りなのであるが、平均的にいるのではなく、いる所といない所がハッキリとしているのは事実のようだ。そして、圧倒的にいない所の方が広範囲である。ヤマガラ、シジュウカラヒガラ、コゲラをみたのはほんの狭い範囲なのだ。後はほとんどと言っていいくらい鳥の気配が無い。2種目のアトリ科がいた。ウソが鳴いていた。声の先を見たら1羽の姿があった。性別は分からない。肉眼では霧で色まで分からなかった。2時間ほど歩いて車に戻った時はだいぶ体も冷えていた。雨脚はさらに強くなる。靴も湿っていて気持ち悪い。逃げ込むように車に乗る。ほとんど休むことなく山を下りる。降雨量が増えるのが心配であった。少しでも早く山から下りたかった。
霧と雨の中をセンサスした。雷も鳴っておっかなびっくり
2024 3 24 寺の入林道ラインセンサス
センサスを開始してしばらくはカケスの声ばかりで、このままカケスだけで終わってしまうのではと心配した。それはそれで面白いことではあるが。それも危惧に過ぎなかった。エナガの声が口火を切った。そばにはシジュウカラとヤマガラもいて、冬季における混群の様相を見せている。念の入ったことには、最後の声はコゲラである。これはまさに混軍メンバーだ。寺の入林道ならではの鳥も確認できた。まずはミソサザイ。ほんの少しだけではあるがさえずりもしていた。もう1種はヒガラ。こちらは遠くの方でさえずっていた。微かではあるが、シジュウカラに比べて高い声なので間違いはなさそうだ。最後に、どうしても見たい鳥がある。それはアトリ科ならば何でもよいのであるが。今日は、ずばりアトリを3羽見ることができた。これが1番嬉しかった。
カケス(雨の音も)

白いアシビの花と、雨続きで白波を立て流れる川、まだまだ春遠い林道で貴重な色である。
2024 3 24 室林道ラインセンサス
久しぶりにたくさんの声がしていた。ウグイスのさえずりは勿論であるが、ヤマガラやシジュウカラの声も多い。ホオジロのさえずりも聴かれた。普通は、ヒヨドリの声が一番目立つのであるが、この日は、先の、カラ類とか、エナガ、ウグイスがバランスよく鳴いていた。春が近づいているのを表しているのだろうか。
ホオジロさえずり

ソメイヨシノがちらほら咲きだした。
2024 3 17 室林道ラインセンサス
ウグイスのさえずりが段ちに増加した感がある。いよいよ春が来たんだなと思える一瞬である。ウグイスばかりではない。ウグイスの対抗馬と目される鳥であるソウシチョウも、ようやくさえずりが聴かれるようになった。もともと数も多い鳥なので一気に賑やかくなるであろう。今朝、自宅でトラツグミのさえずりを初めて聴いた。トラツグミの声を鵺と称していうるが、昔の人は想像力が豊かであったのだろう。そのと楽組の声がここ室林道でも聴かれたように感じたのであるが、自信を持って言える程ではない。ゆえに、記録には入れにないでおこうと思う。シジュウカラがさえずる場所にはヤマガラやコゲラの声もする。混群のなごりであろうか。それとズバリ混群か?
ショウジョウバカマがひっそりと咲いていた。しかし、今年の花はひとつだけ。
2024 3 10 羽根・長根方面
三寒四温の言葉がピッタリのこの頃であるが、探鳥会の今日は暖かい日であって欲しいとの願いが届いたのか、天気の神様は最高の日和をプレゼントしてくれた。2年生の子とおとな3人と変奥的なメンバー。しかし、全く億することなくふるまう姿はとても頼もしい。彼が持参している野鳥図鑑、しっかり使い込んでいて、かなりよれよれになっている。何度か検索の速さを競ってみたが、1回しか勝てなかった。自分ノートももちろん持っていて、びっしりと鳥の名前が書かれていた。30年前の、もう中年になっていた自分が野鳥の世界に入り込んだ状態を思い起こすきっかけになった。羨ましいことに、彼には時間がたっぷりある。この日は18種ほどの観察ができた。その中でも、アルビノを長く観察できたのは、とても良い思い出作りができるきっかけとなった。滅多に無い現象を見る事の有難さを感じる事ができたように思う。
アルビノに出合えて本当に良かった
①②ムクドリ ③-⑥セグロセキレイのアルビノ ⓻-⑨スズメ ⑩⑪ツグミ
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2024 3 10 ふるさと公園ラインセンサス
シルバーの仕事を終えるのが午前7時、子ども探鳥会が始まるのが8時30分から、それまでの間を有効利用しようと、3月度分のふるさと公園ラインセンサスをここでやっておこうと、急遽考えた。実は、出勤途中で思いたのが本当である。アオジやシロハラなどは、まだ日が当たらない早朝によく姿を見る。ところが、今日のように辺りに陽が差す頃には、あまり姿を見せないのだ。ひっそり暮らす鳥のイメージが強い。よく似た仲間の、ホオジロとツグミは、結構目立った感じで見かける事が多い。日陰と日なたの違いと言ったら分かりやすいだろうか。ヒヨドリが1番目に着くのであるが、この辺の森や林ではおそらくどこも同じのような気がする。あとは、常緑樹の多い所ではメジロも多い。山付なのでカラス類はハシブトガラスだ。
様々な楽しみ方を紹介しているのもここの特長
⑩ジョウビタキ ⑪⑫カワラヒワ ⑬ツグミ
2024 3 9 室林道ラインセンサス
鳥を見るのに最適な時間を選んで、昨日に続いての室林道ラインセンサスを行った。時間帯による違いも面白いと思ったからだ。さえずり個体は、ウグイス、シジュウカラ、ヤマガラである。カラではヤマガラよりもシジュウカラの方が多かった。昨日(正午の時間帯)の個体数は18。今日の(朝の時間帯)は26。これははっきりと差が出ていた。センサスを終えて帰る支度をしていると、軽バンが止まった。挨拶をしたら自分の名前を知っておられたのには驚いた。あとひと月もしたら夏鳥たちがやって来る。その中にはコマドリも含まれる。ハラハラドキドキの季節が始まろうとしているのだ。
2024 3 8 室林道ラインセンサス
時間的にはあまり良い条件ではなかったが、ウグイス、シジュウカラのさえずりが聴かれた。シジュウカラの声の回りには、エナガ、ヤマガラ、メジロ、コゲラが続いた。混軍でもいたのであろうか?それとも、つがいでいるのか?たとえ姿は見えなくても、野鳥たちの楽し気な様子は想像できる。空を見上げたら、ヤシャブシの雄花の房が延びてきているのが目に入った。以前ならば、この樹の球果をこじ開けてついばむアトリ科の姿を見ることができた。その種が、マヒワであったなら思わずニンマリしてしまったのであるが。近ごろトンと見かけなくなったマヒワ。もう一度この地でお目にかかりたいものだ。
2024 2 12 室林道ラインセンサス
これからの予定を見ながらセンサスのタイミングを決めている。「室林道は今日」に決めたのは2日前のことだ。天気のこともあるので、決めたとおりにはならないことの方が多い。室林道は旬に1度が決めているノルマだ。こんなことをもう20数年やっている。果たせないととても悔しい。今日はウグイスとホオジロのの初さえずりを聴いた。さえずりと言ってもぐぜりなのであるが。既にカラ類はさえずりを始めているし、アオゲラやイカルなどは真冬でも当たり前のようにさえずりをする。しかし、ウグイスのさえずり開始は特別だ。「ここから春の始まり」を強く意識させてくれる意味で特別だ。ホオジロのさえずりも大好きだ。聴きなしのせいかもしれないが、彼は日本語を知っているかのように歌う。実にホオジロのさえずりは日本語的なのだ。実は、前述の2種以外にも、ヤマガラ、シジュウカラもさえずっていたが、それほど印象には残っていない。やはり、初の言葉には負けてしますのだろうか。
茶色を探していたら、可愛いらしいもの(キノコと何かの種子)が見つかりました。昨年からの間伐も進み、健全な林に育って行けそうです。
番外編、
室林道の行きと帰りに山陰川を覗いてみた。もちろんアルビノ君に会うためである。朝はダメであった。川を覗いていたら親子連れの3人が来た。子どもは「子ども探鳥会」の常連だからよく知っている。「カラスが群れているのはなぜですか」との質問。お嫁さん・お婿さん探しだよと答えた。帰りにも寄ってみた。年を取ると粘りが利かなくなる。「まあいいか」を連発してしまう。ところが、今日に限って悪い虫を抑え込んだ。カメラを持って、動画を録るべく、しっかりとスタンバイさせて川に向かった。足音も立てず忍者の如く。嘘!と思える瞬間が訪れた。2羽のセグロセキレイがいた。そのうちの1羽は白かった。この場で3回目の姿であった。3度とも、もう1羽のセグロセキレイと一緒であった。この2羽、兄弟、親子なのであろうか?滅多に使ったことのないLumix(バリオエルマリート)には美味しい対象物だった。Leicaにお熱を入れていた昔が懐かしい。年甲斐もなく、戦後間もない頃の、コダックフィルムを装填した沈胴式エルマー50ミリ付Ⅲfのシャッターを切って悦に入っていた。家で動画を見た。「我ながらまずまず良い出来だわい」とにんまりしてしまった。
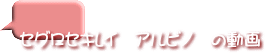
2024 2 11 茶臼山ラインセンサス
立春が過ぎて、茶臼山の様子はどうなのだろうか。定点カメラのライブを見ると、ゲレンデはなんとか雪があってスキーができそうな感じである。麓は全く積雪がないのでやはり暖冬といってよいと思う。国道151を左に折れ茶臼山高原へと登る道の様子と言えば、所々踏み固められた雪があるだけで大した積雪ではない。高原の道も除雪がなされており危険な所もない。ただ意外であったのは、駐車場がほぼ満車であったこと。スキーをする人たちには間違いないが、そんなに混んでいるとは予想しなかった。(混んでいるのは良いことではあるが)仕方がないのでいつもの場所に停めることにする。スパイク付きゴム長に履き替えて、ガリガリ言わせながら歩き始める。コースの回り順が変わってくるのは仕方がない。それと、スキー場の周辺は取りやめることにした。何となくである、特に理由はない。カメラと12倍の双眼鏡を持って行く。このくらいの倍率(12倍)が個体識別にはちょうど良い。8倍だと力不足の時があるからだ。遠くの鳥を見て種を同定しないといけないので、8倍が最適倍率だとは思っていない。条件で使い分けている。近距離が主ならば7倍も良いと思う。(低倍率の方が視野に入れ易い)アトリの群れがいた。おおよそ30羽。先月までよく見たツグミの姿は残念ながらなかった。いないというわけではないと思う。カラ類もいた。ヒガラがさえずりをしている。エナガは案内小さい体で頑張っている。それよりも大きなシジュウカラやヤマガラも余裕である。ところが、もっとも頑固なコガラの名前がノートに書かれていないことに気が付いた。たまたまに過ぎないにしても珍しいと思う。スキー場の方角からスピーカー越しの声が聞こえてくる。自分はたった一人で雪道を歩く。スパイク付きゴム長は最強だ。スケートのできそうな所も鉄の爪が食い込んでくれる。おかげできれいな風景を楽しむことができる。南アルプスの北から南まで白く化粧をした峰々を眺めながら(休憩をする時だけ見る。センサスは結構集中しないといけないからだ。)歩くのは至福の時だ。南アルプス南部の比較的標高の低い(それでも2千45百はある)山々の名前を覚えたいと思っているが、地図を持参しながら歩かないと無理。輪郭のよくわかる今が一番よいのであるがなかなかそんな暇はない。(鳥で精一)
たった一人で見ている風景(冬季通行止めで車はいません)
雪山は、山肌が露になって色っぽいですね
2024 2 7 寺ノ入林道ラインセンサス
冬季の寺ノ入林道は、個体数は多くは無いけれども、変わった野鳥が見られるのでは、と言う期待を膨らませてやってくる。たった1度だけど、くちばしの交差したあの鳥を見たこともある。マヒワやアトリは密集した群れを作っている。毬のような飛翔姿にはいつも感動する。今日はアトリであった。歩い始めて暫くは全く鳥の声を聴かなかった。もしかして個体数ゼロ?と変な期待もしてしまった。しかし、そのようにはならず、最初に見たのがアトリだった。やがて、シジュウカラの姿やヤマガラの地鳴きが聞こえてくる。コゲラもいた。混群であった可能性もある。2つ目のアトリの群れは結構大きかった。30羽くらいはいたと思う。標高500メートルはあるので寒いはずなのに、いつもの場所に氷柱が無い。暖冬なのだ。マヒワも見たかったけれども駄目であった。
間伐が「進んで、空が広がって来たようだ。
2024 2 3 室林道ラインセンサス
ふるさと公園に比べて明らかに寒い。冬季の室林道は結構厳しいものがある。いっぱい着込んで歩かないと体調を崩してしまう。カケスの姿とアオバトの姿を見たの収穫であった。アオバトは連続して見ている。それも、ほとんど同じ場所で。カケスの、喉から血を吹かないかと心配する声は、清とした山で聴くと心に刺さるものがある。自分は好きだ。浪曲の声と繋がるものがあるように感じる。カラ類のさえずりが始まったように思える。まだまだ長い節回しはできていないが、いよいよ繁殖の縦鼻がスタートするのかと思うと、観察にも一層身が入るというもの。センサスコースの折り返し地点で数頭の子ザルを見た。一頭が逃げそこなって、どうしようと迷っているのが、何とも言えないほど可愛い。
子ザルの群れに出会った。親がいたのかも知れないが? ⑥ウソ
2024 2 3 ふるさと公園ラインセンサス
シルバーの仕事を終えたので、そのまま車から道具を取り出して、野鳥観察に取り掛かった。暫くして声を掛けられた。「権田さんじゃないですか」「はい」と返事をして声の方を向くと、朝の散歩姿の女性。かなり昔、小学校の探鳥会でお世話になった人。探鳥会にもたびたび参加してくれた人であった。自然と話は鳥に。うまい具合に今日はとりの声・姿ともに多い。公園で見た鳥の話をしながら道を上っていく。キセキレイ、シロハラ、シジュウカラ、ヤマガラ、ジョウビタキ、メジロとノートに書くのが大変なくらいに姿を見せる。ソウシチョウがいたという話。自分は、未だにソウシチョウをふるさと公園では確認できていない。やはり頻繁に歩いておられる方にはかなわないと思う。それにしても今年の冬は暖かい。冬鳥の記録にも影響するのではないか。まずは、しっかりと、丁寧に記録を取っておきたい。その人は山頂に向かった。自分は下山。次は室林道だ。
2024 1 28 羽根・長根方面
今週は、北日本・北陸方面では吹雪となり、その名残の雪雲がどんどんと東海地方にも流れてきていた。当然風も強くて、あちこちに立っている「あいさつ」旗も引きちぎられそうなくらいにバタバタと音を立てていた。その様子を見ると、探鳥会が思いやられてならなかった。ところが、当日の朝になってみると、旗も竹藪も何もかも全く揺れていない。太陽の方向には中層の雲が立ち込めて薄日が差している。西の方向から青空が広がり、好天を約束しているようであった。参加者は9名。そのうち萩小の児童は4名で大人の方が多かった。校庭で見られたのがイソヒヨドリである。もう、この鳥は珍しい鳥ではなくなったようだ。明らかに各地で見られるので、繁殖をしているのは間違いないと思う。竹やぶや神社の杜ではヒヨドリが鳴いている。時折、ペアで飛んでいるのを見ることができた。民家のそばで最初のツグミを確認した。その後はあちこちで見られたので、ツグミの話をすることができた。山陰川を渡る際、カルガモが2羽水面で休んでいるのを見る。その後、水鳥を見たのは、アオサギ・ダイサギ・オオバンであった。オオバンがいたのは長根の大池。釣りをする人も今日の天気には喜んでいるだろう。そこで、水面に揺れていたのはのんびりとした風景であった。昨日までの強風だったならが、波立った水面で大いに揺れていたであろう。オオバンにとっても嬉しい日であったか。運動公園で一休み。こんな良い天気なのに利用されていない。我々だけが独り占め。みんなで持ち寄ったお菓子をほおばって楽しい時間を過ごす。帰途にも色々野鳥が現れたが、時間も無くなって、ひたすら歩くだけになった。天気にも助けられ、この日は、20種以上を観察できた。悪条件ならば、半分程度しか見られなかったであろう。
下萩の通学路を、音羽運動公園まで歩いた。好天に恵まれて、21種もの野鳥を観察。
①-③ツグミ、⑤カルガモ、⑥ムクドリ、⓻⑮ノスリ、⑯、⑰オオバン
2024 1 23 室林道ラインセンサス
林道の入り口には、例よって、伐採作業通行止めの看板が出ている。「確か、1月19日までと掛かれていたハズなのだが」「しかし、休工中のワッペンも張られていないし」「伐採しているのなら、チェンソーのエンジン音が聞こえるハズだ。」「気配はないので、行けるところまで行こう」、と道具を持って(首から下げて)歩きハジマタ。ヒヨドリ・メジロの声が多い。もともと、両者は、室林道に多い鳥なのだから当たり前ではあるが。コースを折り返したことからその他の鳥も鳴きだした。ヤマガラ、シジュウカラ、カケスが鳴いた。けれども少し物足りない。冬鳥を見たい(聴きたい)。コースも終盤近い。あきらめ始めたら助け船がでた。ウソの声、ルリビタキの声、シロハラの声などが続けざまにあったのだ。
赤色を探してみた。 道に落ちている小枝に、虫が巣くった瘤(虫癭)があった。拡大してみると?
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2024 1 12 室林道ラインセンサス
早くも正月明けから10日以上経ってしまった。そこで、室林道の1月中旬の記録を取るべく室林道へと車を走らせた。一瞬、伐採中の立て札が目に入りドキリとしたが、よく見たら「休工中」というお馴染みの「磁石付きワッペン」が張られていたのでホッとする。対象物までの距離の近い山中の場合、自分は8倍を使うことが多い。逆に対象への距離が遠い平地では12倍を使っている。8倍40口径のポロを首に下げて(記録用カメラも)センサスを開始。ダハ全盛の中でポロを使っている。単に好きだから。特に、ダハよりも遠近感が強調される所が良い。いつか、Swarovskiハビヒトを覗いてみたいものだと思っている。新品では20万円近くもするので夢の夢である。本来の観察に戻る。今日は運が良かったのか色々なことに出合えた。まずはアオバト。数羽のハトが一斉に飛び去るのを見た。その色がキジバトのそれではなく緑色をしていたのだ。アオバトであった。アオバトは留鳥なのか渡り鳥なのかいまいちよく分からない。ほとんどの場合その特異な鳴き声で存在を知るのであるが、今日は姿を観察することができた。ラッキーだと思っている。次に、シジュウカラのさえずりを聴いたこと。2日ほど前に、小学校のすぐ近くでヤマガラのさえずりを聴いたのに続いてのさえずり記録である。もっとも、イカルはもっと早くからさえずりを開始するのが普通なので除外して考えると、繁殖行動の象徴とも言えるさえずりがシジュウカラやヤマガラの口から聴かれると、「ああ春も近いなー」と思えるのである。シジュウカラと共に代表的な鳥であるヤマガラも既にさえずりを聴いている。今朝の室林道では地鳴きしか聴かれなかったが、ヤマガラのさえずりも直ぐであろうと思う。シジュウカラ、ヤマガラと共にエナガ、コゲラも確認できたので、たぶん、混群であったと思う。冬季の室林道の一番の見所である。混群に出合うと本当にワクワク・ドキドキしてしまう。何回経験しても同じ状態になるのはなぜなのであろうか。最後はルリビタキ。この鳥も地鳴き(たまにさえずりも)ばかりであるが、今日は、茂みの中に潜む姿を見つけた。多分、オスの若鳥だと思う。
室林道の森林整備 何気ない風景ではあるが、毎週訪れていると直ぐに変化に気付く。 ⑤切り株から再生 ⑦幹よりも存在感のある根っこ
2024 1 8 自宅周辺ラインセンサス
正月明けに、自分としては精力的に野鳥の観察を行ってきた。明日から再び日常生活が戻ってくる。そうなるとそうそう野鳥観察に時間を費やせなくなるだろう。遠くは茶臼山まで車を走らせた。往復で5時間の道のりである。最後は、最も身近な自宅周辺の野鳥を見るのが真っ当というものであろう。首にniponkougaku7x35(古いものだ)を下げフラフラと歩き回る。澄んだ空は気持ちよいのであるが風が冷たい。手袋をしていないのが恨めしい。それというのも、作業用の軍手を愛用していて手のひら側に滑り止めが付いているため、大事な双眼鏡に擦り傷が付くのを恐れたためなのだ。最近のものは樹脂のコーティングでおおわれているから大丈夫なのであるが。コーティングがマゼンタなのは古い証。それを反映して少し暖色系に色着く。このスペックは30年以上まに初めて購入したものと同じであるが、その当時でもコーティングはもちろんマルチコートであった。だから今持っているのは50年以上も前のものであろう。視度調整リングが渋いのみで後は問題ない。見え味は流石ニコンである。コンパクトで手になじむ。ポロの良さが出ている。立体感がよくわかるのである。自宅から北側1キロメートルほど、山陰川を中心としたエリアを自宅周辺として記録している。田んぼや川原ではセグロセキレイ、ハクセキレイ、キセキレイを確認した。森からはハシブトガラス、トビが舞い上がり私の頭の上でパフォーマンスを繰り広げる。今日の見所は、コースの最北端に位置し、耕作放棄地が一面に広がる景観上は思わしくない所であった。ここはホオジロ科の楽園のようだ。先ず現れたのは2羽のオスのホオジロである。丈の高い草(セイタカアワダチソウと思われる)に止まって周りを見渡していた。次いで見たのはアオジ。こちらは数羽ほど確認できた。すぐそばには3面張りの川があって、ホオジロやアオジにとってはまことに居心地の良い場所であるように思える。双眼鏡で覗くとアオジの黄緑色のお腹がよく見られた。改めて美しいと思った。
耕作放棄地が目立つ。そこは野鳥のたまり場である。ホオジロ・アオジが多いようだ。
⑪⑫キセキレイ
2024 1 4 寺の入林道ラインセンサス
豊川市の中心地から寺の入林道へどのコースで向かおうか。3つ考えた。その中からいちばん楽しそうなのを選んだ。国道301を本宮山に向って登ってゆき、旧作手村に出るというものだ。一気に500メートルの高度を稼ぐのだ。林道は午後の日を浴びていた。大規模な伐採を行っている最中なので、「まさか正月三が日明け早々仕事をすることもあるまい」と勝手に決めてやって来たので、通行止めの表示もなく、だれ一人といないのを確認してホッとしたのであった。一山向こうから間断なく聴こえるのは鉄砲の音。猟ではなくて射撃場からの音である。それが風に流され増幅されてこちらに届くのである。ここでもスタートはヒヨドリの声であった。それから徐々に色々な声がしてきた。ヒガラの地鳴き。ミソサザイの地鳴き。ヤマガラ、シジュウカラの姿と声。こうしてみると、自分にとっての野鳥観察の1番は、季節は今で、できるだけ静かな場所を歩き、微かな鳥の声を聴いて、あれは何々だと思いめぐらすことに尽きる。
伐採で木が間引かれ、心なしか林道が明るくなった。
2024 1 4 ふるさと公園ラインセンサス
朝早くから公園で鳥を見た。朝日が町を照らし公園の梢を照らす。寒いけれども私には好きな時間だと思う。ヒヨドリの声がすごい。個毎の音量もあって数も多い。パワーというか圧を感じる。その他の鳥についてはほとんどヒヨドリに埋もれてしまうくらいであるが、カワラヒワの声だけはしっかりと確認できた。何故かというと、その声がさえずりだったからだ。どの鳥もそうだが、さえずりは耳に良く残るのだ。特に今の季節には。ほとんどの鳴き声は地鳴きである。そんな中にさえずりを一声聴かされたらたまらないものだ。
朝焼け!
2024 1 3 茶臼山ラインセンサス
年末に歩いたばかりなのに、茶臼山の引力が強いためなのかは分からないが、早くも、正月早々の茶臼山を歩いた。たった1週間の違いなのに道は大きく違っていた。雪が全て消えてしまったのだ。スキー場の降雪も進んでいない様子。一般のゲレンデには芝が半分くらい見えていてとてもスキーができる状態ではない。ファミリーゲレンデにも滑っている人はいなかった。気温が下がらないのであろう。このことは、野鳥の世界にも何らかの影響があるのではと想像する。コースを通してウソの声や姿が多かった。私の地元でもウソがやって来るが、茶臼山にもいるのだ。想像ではあるが、気温が下がれば、茶臼山のウソは私の所に下がってきて、気温が上がれば、私所のウソは茶臼山に戻っていく、そうはならないか。最後にアトリの群れに出合った。道具を車に戻し、水を飲んで一服していた時、目の前の木に鳥が群れていた。慌てて双眼鏡を持って眺めた。アトリであった。その後、一斉に鳥たちが飛び立った。楕円形の群れはおよそ50羽くらい。アトリ科の鳥の群れに出合うとドキドキする。ほぼ同タイミングでヒガラのさえずりを聴いた。
12月末に来た時には、部分的ではあるが道路に雪があった。今は全て消えてしまっている。
⑮ホオジロ ⑰⑱ヒガラ ⑲20ウソ ㉕ノスリ
2024 1 2 羽根・長根ラインセンサス
室林道での野鳥観察を終え、そのまま羽根・長根の田んぼへと下って来た。一見、鳥の姿は見られずセンサスを行っても仕方がないように思う。それでも、歩くだけ歩いてみようと。確かにどの田んぼを覗いても鳥の姿は無い。今度は、付近の、電柱や電線を絨毯爆撃。それが当たった。一本の電柱でノスリを見つけた。この個体は何度か見た。(正確には見たかもしれない。)ようやく田んぼで鳥を視る。セグロセキレイであった。セグロセキレイとなるとどうしてもアルビノを期待してしますが、そんなことはまず無い。ハクセキレイは声だけ。冬にはタヒバリもやって来るが姿はおろか声すらも無い。暖かな冬の影響はあるのであろうか。カワラヒワの大きな群れを期待しいるのであるが、近ごろは滅多に見なくなった。積雪で白くなり採餌も大変な田んぼの上を旋回する、100羽近いカワラヒワ。頭の中で思い浮かべる光景である。
野鳥の姿がなかなか見られない。
2024 1 2 室林道ラインセンサス
2024年最初のセンサスはやはり室林道から始めようと思う。正月元旦は用事で1日が終わった。ようやく自分の時間が取れる。とはいえ、気持ちは複雑だ。その理由はもちろん能登半島地震のためだ。自然はなんと無慈悲なことをする。ヒヨドリの喉の裂けるような声。今までは普通に聴いていた声が、今日は、悲しい叫びに聴こえてくる。外界からの声(刺激・情報)は耳から脳に伝わり、脳が過去の情報と照らし合わせ、これは聴いたことがある。これは〇〇だと判断すのであろう。その時に、少しの捻りを加えて(震災で暗くなった気持ちを付け加えて)ヒヨドリだけども苦しい叫びをしていると、解釈を付加するであろうか。そして、今の室林道はヒヨドリの鳴き声が最も多数派なのである。冬の野鳥観察は楽しい。落葉樹で遊ぶ小鳥たちが見られるからだ。その中の代表者はエナガで決まりだ。体の半分は尾羽。小さな体で枝から枝へと駆け回る。宙返りもお手の物。大概は10羽以上の群れでいる。そのエナガに引っ張られるようにして他の鳥たちも動く。コゲラの間延びした声を聴かないことはあるまい。こうして1年のスタートを切ったのであるが、ここでサプライズがあった。サンショウクイの鳴き声を聴いたのだ。実は、11月22日にも聴いていた。サンショウクイは東南アジアから飛来する夏鳥で、11月までいるのは初めての経験であったと記録したのである。それが、さらに遅い、年を越しての記録となると、越冬と考えてもおかしくはないと思ったのだ。「サンショウクイ越冬」でググると「リュウキュウサンショウクイ」の名が挙がって来た。「近年繁殖地域を拡大し、本州でも繁殖している。」とあった。3種の図鑑でも、亜種として、サンショウクイ・リュウキュウサンショウクイが記載されていた。今日の個体は声だけであったが、11月20日は姿も声も確認していた。しかし、姿は肉眼だけで写真は無い。幸い、声は録音できていた。再びネットでリュウキュウサンショウクイの声を調べた。サンショウクイとの違いはほとんど分からなかった。だから、今いる個体がリュウキュウサンショウクイであっても不思議ではない。何と言ってもサンショウクイは夏鳥であるから今時分いるのはおかしい、と思うのが自然なのだろうか。もう一つ証拠を積み上げたい。姿を捕まえることだ。できたら写真に収めたい。こうして正月早々新たな課題が浮かび上がったのである。
綺麗な空、冬季の山歩きはスカッとして気持ちがよい